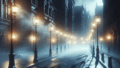かつて繁栄を極めた街が、今では廃墟同然に成り果てている様は、誰しもに薄ら寒さを抱かせるであろう。曇った空の下、冷たい風が古びた窓ガラスを悲しげに揺らしている。道を歩いても人影はなく、ただ木々がざわめく音ばかりが耳に残る。そんな荒れ果てた街に足を踏み入れた一人の若者、彰人は、胸の内に何とも言えない不安を抱きながら、辺りを見渡した。
ここは、かつて家族と共に暮らしていた場所。だが、奇怪な感染症によって街全体が襲われ、人々は次々と姿を消した。最初はただの風邪のようだった。それが徐々に命を蝕み、やがて不可解な形で意識を変容させていった。人々は病に冒された者を恐れ、街を去るか、または何もかもを棄てて閉じこもった。
「死者が蘇る」
そのような噂が広まったのは、感染が始まってから数ヶ月後のことだった。住民たちは、今もたびたび聞こえてくる低い呻き声に、何か不穏なものを感じずにはいられなかった。かつての住人が形を変え、生者と死者の狭間で彷徨い続けているというのだ。
彰人の目的は、廃墟に取り残されたという妹の安否を確かめることにあった。妹の美咲は、彼にとってかけがえのない存在だった。感染症の影響でこの街を離れざるを得なかったが、美咲だけは何かに取り憑かれたかのように、この場所に残ることを選んだのだ。
彼女がどこにいるのか、消息はつかめない。携帯電話は既に繋がらない。彰人はただ、彼女がかつてお気に入りだった教会へと歩を進めた。
足元の枯れ枝がパキリと音を立てる。日が暮れかけ、街は薄い闇に包まれていく。廃れた家々の影が伸び、細く不気味なシルエットを描いている。そんな中、彼の耳に聞こえてきたのは、微かに響く祈りの声だった。すぐそばに、何者かがいる。
呼吸を抑え、声のする方向に向かう。教会の側に立ち、扉の隙間から中を覗くと、そこには奇妙な光景が広がっていた。本来ならば、誰も居るはずのないその場所に、白いドレスを纏った女性が一人、祭壇の前に座っている。長い髪が優雅に垂れ、まるで夢の中の幻影のように揺れていた。
「あ、彰人兄さん……」
不意に女性の声が空間を包み込む。彼女の声はどこか夢遊病者のように物憂げで、しかし確かに妹のものだった。決意を決め込むように彰人は扉を押し開け、中へと駆け込む。
「美咲! 生きていたんだね!」
彼が駆け寄ると、美咲はゆっくりと顔を上げた。だがその時、彰人は恐ろしいほどの異様さを感じた。妹の顔には確かに微笑みが浮かんでいた。だが、その目は普通の人間のものとは明らかに異なり、闇を抱え込んでいる。それは、死者が持つまなざしだった。
「ありがとう、来てくれて……でも、もう遅いの。わたしはここでしか、生きることができないの」
状況を飲み込めずにいる彰人に対し、美咲は立ち上がり、彼の頬にそっと手を触れた。その手は冷たく、まるで亡者の指のように肌を這う。
「ごめんなさい、兄さん。あなたもここに来れば、そのうち理解できる……」
そう囁くと、美咲はゆっくりと後退りし、やがて暗闇の中へと溶け込んでいった。そしてその姿は、まるで霧のように儚く消えた。
教会内には、信じられないほどの静寂が訪れた。弟たる彰人は、ただ立ち尽くすだけであった。彼の心には、失ったはずの妹の姿が今なお鮮明に残っていた。だが、現実の妹はもう、そこにはいない。
外の風がまたひとつ激しく吹きつけ、古びた薔薇窓のガラスを震わせた。その音はどこか、哀しい調べを奏でているようでもあった。彼はその場を離れることができない。ただただ、失ったものの大きさに打ちひしがれていた。
そして彼は知ることとなった。人々の噂は真実であったのかもしれないと。この荒れ果てた街のどこかに、かつての住人たちが今も彷徨い続けているのかもしれないと。そう考えると、彼の背筋にぞくぞくと冷たいものが走った。
しばらくの後、彰人は心を落ち着け、教会を後にした。かつての街を振り返ると、微かに立ち昇る煙が夜空に溶けゆく。彼はもう二度と戻るまい、この恐ろしい街へは。
しかし、彼の後ろからはまたしても低いうなり声が聞こえてきた。それは風のなせる業か、それとも本当に何者かの声か。彰人は振り返ることなく、ただ一心不乱にその道を歩き続けた。薄暗い街の中で、彼の心にはただ一つだけ確かなことが残された。それは、この街が今も謎と恐怖に満ちているということだった。