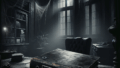古ぼけた神社の鳥居をくぐる時、陽介はふと立ち止まった。どこかで何かが始まりを待っているような、そんな気配がしたからだ。それは深秋の夜、連れ添う友人達が彼を急かす声に混じる形で現れた。不気味な静寂を突き破るかのように、彼は再び歩みを進めた。
その神社は、街外れの誰も通らぬ道の先にひっそりと佇んでいた。古事記にもないような、名も無き神を祀るその場は、いつしか「呪いの神社」と呼ばれるようになっていた。一度その名を耳にした者は、興味本位で訪れることも少なくなかった。しかし、目の前で打ち捨てられた鳥居の柱は、何代もの人々の警告を物語っているかのごとく、重く垂れ下がった苔に覆われている。
「行こうぜ、陽介。こんなところにずっといる気か?」友人の一人である直樹が声をかける。他の者もそれに同調し、神社の奥へと続く階段を昇り始めた。
陽介は、背中に冷やりとした感覚を覚えながらも、それに逆らわず友人達の後を追った。石段は苔むし、足元を掬われそうになる。不規則なリズムで響く彼らの足音が、山奥の静けさの中、妙に耳障りだった。
境内に着くと、かつて賑わいを見せたであろう拝殿が、今は無言の抗議の貌を晒していた。拝殿の前には古い石碑が立っており、その刻まれた文字は風化により読み取り辛くなってはいるが、なおも不吉な響きを保っている。
「どうする、肝試しとかしちゃう?」冗談半分で直樹が言う。陽介は何か不吉な兆しを感じながらも、「やめておこう」と言いだす勇気が湧かなかった。誰もが恐れと好奇心に心を揺らしたまま、その場を見回す。
すると誰かが小さな石を手にし、ふざけるようにそれを石碑に投げつけた。刹那、空気が異様な緊張感に包まれる。それはまるで、何かが動き出そうとしている悪寒のようだった。そして、それはただの気のせいではなかった。
「なんだ、今の?」直樹が首を傾げて呟く。風が一陣吹き抜け、紙垂が宙に舞った。その時、陽介は自分の背後に誰かの視線があるのを感じた。振り返るが、そこには誰もいない。それでも何かがいるとしか思えない恐怖が、彼の心を凍らせた。彼は慌てて視線を戻し、震える手をポケットに押し込む。
その夜以来、陽介の日常は次第に狂い始めた。家族や友人と過ごす時間がどこか霧がかかったようにぼやけ、特に理由もなく心が重く沈む。そして何よりも、その視線をひしひしと感じるのだ。それは夜の闇の中で、鏡の中で、そしてふとした瞬間に現れた。
ある夜、あの神社へ行った仲間たちと再会しようと街に出た彼は、一様に顔色を失くした彼らを見て、ようやく気付いた。彼らもまた、何かに取り憑かれているのだ。直樹を含む全員が、口を重くしてその恐怖を語らなかったが、陽介にはその恐怖が手に取るように伝わってきた。
それから数日後、直樹が行方不明になったという知らせが入った。警察は何も手がかりを見つけられずにいたが、陽介はかすかな手がかりを見つけたような気がしてならなかった。神社に戻れば何かが分かるかもしれない。おそらくそれは、到底払うことができない代償を伴うものであることは明白だったが、それでも彼は神社へ向かうことを決意した。
再び神社の鳥居を潜った時、今度は視線だけではない、明確な囁き声が耳に届いた。それは掠れた、しかし否応のない力を持つ声だった。「過去が現に変わり、罪は再び生じる」その意味するところに、陽介は逃げ出したくなる思いに駆られたが、あと戻りすることは許されなかった。
拝殿の前に立つと、巨大な影が彼を迎えた。それはかつて祀られし何者かの姿であり、今はただの呪いの存在であり続けるものだった。陽介は、その影の前に膝をつき、何も返事が無いことを願いながら、心の中で友人達と共に見逃してくれることを祈った。
その瞬間、地面が震え、陽介は意識を失った。気がつくと、彼は自分の部屋の床に倒れていた。夢とも現ともつかぬ状況で、しかし確かに何かが変わっていた。視線も囁き声も消え去り、ただの静けさが残っていたのだ。
後日、直樹は前触れもなく町へ戻り、彼の記憶からあの数週間の出来事がきれいに消え去っていた。陽介は、一連の出来事を振り返ることなく、ただ恐る恐る平穏を享受することにした。
しかし、夜毎に夢の中であの囁きを耳にする。「過去が現に変わり、罪は再び生じる」その意味するところを知る日は、まだ来ることはなかった。しかし、陽介は、再び同じ過ちを犯さぬよう、その一歩一歩を慎重に選ばざるを得なかったのだ。その選択が未来を救うのだと、彼自身信じたいと願っていた。