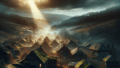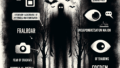木々の囁きが風に乗って、夏の晩の涼しさを一層引き立てる田舎の一角。月明かりが差し込む薄闇の中で、どこか懐かしい匂いが漂っていた。その匂いに誘われるように、遥は幼い頃を過ごした祖母の家を訪れていた。
農村特有の静けさが支配する辺り一帯には、古びた木造の家々がポツポツと点在している。遥の祖母は数年前に他界していたが、築百年を超える古い屋敷は、未だに彼女の温もりを感じさせた。「時には不気味にさえ思えるが、それでもこの家はやはり私を引き寄せるのかもしれない」と遥はふと思った。
家の中に足を踏み入れると、微かに埃の匂いが漂う。それは無用心なまでに残されていた祖母の思い出の品々に包まれていた。入り口の近くには、今は誰も使っていない箪笥や代々伝わる骨董品が鎮座している。音を立てて軋む床板や、ほのかに甘い木材の香りが、時間の流れを遡るような感覚に誘う。
部屋を一通り見て回ったあと、遥は奥の部屋にある古ぼけた書斎に足を運んだ。そこには祖母がよく座っていた揺り椅子が置かれ、彼女が書きかけのまま遺した日記が無造作に置かれている。遥はその日記を手に取り、ページをめくり始めた。
日記には祖母の生活や思い出が綿密に記されている。だが、あるページに差し掛かると、文章の調子が不意に変わった。震えた字で、「何かが私を見ている」という文が慎重に綴られていた。遥はその部分を何度も読み返し、何とも言えない冷たい感覚が背中を走るのを感じた。
その瞬間、一陣の風が止んで、軋む音と共に窓が閉じた。部屋の空気が急に重くなり、遥は自然と視線を背後に向けた。彼女の目に映ったのは、窓ガラスに映る彼女自身の姿。しかし、その姿の背後には、得体の知れない影が静かに立っていた。それは人の形をしているようにも見えたが、詳細を識別することは不可能だった。
遥は意を決し、振り返ってその場を注視した。しかし、そこにはただ月光が薄らと差し込むだけで、何もいないように見えた。彼女の胸は高鳴り、何かが確かにそこにいるという確信が残った。
夜が更けるにつれ、彼女は謎めいた存在がこの家に潜んでいるのではないかという考えに囚われていた。そして、どうにも落ち着かない気持ちのまま、遥は居間の床に身を横たえて目を閉じた。
幽かな物音に目を覚ますと、まだ薄暗い早朝の時間だった。彼女はまた書斎へ行き、日記の続きを読み始めた。祖母は信じがたい出来事に繰り返し遭遇していたらしく、薄気味悪い足音や誰もいないはずの部屋から聞こえる低い囁き声について書き記していた。
その後も遙は日記とにらめっこを続ける。しかし次第に、彼女は文面に記された事柄が現実味を帯びてくると感じ始めた。というのも、夜の帳が降りると、静かだった家に再び不気味な音や影が出現し始めたのだ。
彼女はそれらを幻覚だと片付けようとしたが、毎晩同じことが続くうちに、どうしようもなく恐怖に追い詰められていった。しかし、元の生活に戻る選択肢もなかった。と言うのも、彼女は祖母の思い出を胸に抱きながら、この家で何かを探し続ける宿命に縛られているように感じたからである。
やがて、ある晩のこと。居間で眠りについていた遥は、明確に何者かに体を揺すられるという感覚で目を覚ました。慌てて飛び起きると、目の前にはうすぼんやりとした光の人影が立っていた。その影は、祖母の優しさを感じさせるような、人間味溢れるような存在に見えたが、それでも何か冷たく、不気味な雰囲気を纏っていた。
遥は口を開こうとしたが、声が出ない。そんな彼女の様子を見て取ったのか、影は淡く微笑むと、そのまま静かに消えていった。遥が恐る恐る振り返ると、もう影の姿は消えていた。だが、その瞬間、確かに感じたものには、生前の祖母の何とも言えない温もりのようなものが混じっていた。
翌朝、窓辺に朝日が昇るころ、遥は再び書斎に向かい、日記の最後のページをめくった。そこには祖母が遺した最後の言葉が記されていた。「恐れることはない。ここにいるものはあなたを護る者でもある。ただ、忘れ去られることを何よりも悲しんでいるのです。」
遥はその言葉を心に刻み、最後に祖母が伝えたかったことを確かめるように、家中を見て回った。そして彼女は、目にし得た怖ろしい出来事の数々を、祖母やこの場所にまつわる思い出が生み出したものだと再解釈し、その夜以来、遥はこの不思議な館を本当に「帰るべき場所」と感じることができるようになったのだった。