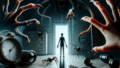町は静寂に包まれていた。朝、カーテンを開けると、静かな通りの向こうに薄曇りの空が広がり、まるで日常そのものが色褪せたかのような風景が目に飛び込んできた。いつものように、私は珈琲を淹れる音に耳を傾け、一日の始まりにふさわしい穏やかな気配を感じていた。しかし、その日は何かが違っていた。いつもの朝とは異なる、微細な違和感が空気の中に漂っていた。
小さな町のいつものカフェへ向かう途中、私は通りの角でひとりの老人に声をかけられた。顔には深い皺が刻まれ、眼鏡の奥の瞳はどこか不安げに揺らいでいる。「君、この町は何かがおかしいと思わないかね?」彼は唐突にそう問いかけてきた。私は何と答えてよいのかわからず、曖昧に笑ってその場を後にした。しかし、彼の言葉は心に残り、頭から離れなかった。
カフェに到着すると、いつも通りの顔触れが楽しげに朝食を摂っている。しかしどこか空気が重い。窓から見える風景はいつもと変わらないはずなのに、どこか違って見える。煙草の煙が漂う中、友人たちが笑い声をあげるが、それもどこかぎこちない。誰も口にはしないが、確実に何かが異なるのだ。
数日後、町で奇妙な出来事が起こった。商店街の中程にある古い屋敷が、ついに取り壊されることになった。住民たちはそれをただ観光の拠点と見なしていたが、その屋敷の早朝の崩壊が始まった時、静けさの中に不協和音が響き渡った。そしてその瞬間から、町全体が少しずつ崩れていくのを、私は感じ始めた。
屋敷の取り壊しが進むにつれ、町の人々の振る舞いが変わり始めた。いつもの道を歩いても、すれ違う人々の顔にはどこか影が差している。目が合うと、皆何かを隠しているような、そんな視線を送り返してくる。町全体がまるで見えないベールで覆われたかのように、次第に透明になっていくように感じた。
ある夜、私は眠れずにベッドを抜け出して、町の中を歩き始めた。月明かりの下、静かな通りは普段と変わらずそこにあるはずだったが、歩いてみると足音が吸い込まれるように消えてしまう。そして、何を見ても触れても、まるで夢の中にいるかのように現実感がない。不安に駆られながら、私は町を一巡りして家に帰ったが、その不気味さは薄れることなく、むしろ私の中で大きくなっていった。
日が経つにつれて、日常の中にもその不協和音がますます浸透していった。町の人々は言葉を交わす度に躊躇し、その場を急ぎ足で去っていく。ふと窓を見れば、表情のない顔が私を見つめているような錯覚が頭を離れない。テレビのニュースでさえ、どうということもない話題がただの雑音にしか聞こえなくなった。
それでも私たちは、日常を続けるしかなかった。変わらぬ朝の始まり、変わらぬ挨拶、変わらぬ仕事。それが一体何の意味を持つのか、全く分からないままに。それでも、人々が寄り添いながら小さな町を支え合っているように見えた。
だがついに、あの不協和音が頂点に達したのだろうか、私はある日突然、町の中で全く見たことのない場所に立っている自分に気づいた。周りを見回しても知っているはずの建物はなく、むしろそこには全く違う何かが広がっていた。そしてその場所は、まるで自分だけのために用意された舞台のように、ただ静かに私を見つめているのだった。
逃げるようにしてその場を立ち去り、再び自分の知る道へと戻った時、確信した。この町は私を変えようとしている。同じ風景の中に隠された異物が、私の心を蝕んでいるのだと。
それからというもの、私の日常はますます壊れていった。見知らぬ場所は増え続け、知っていたはずの町は次第にその輪郭を曖昧にしていった。人々は顔を適度に反らし、言葉すらも忘れてしまったかのように沈黙する。まるで町全体が人々を飲み込み、その形を変えつつあるようだった。
そうして、私の中に生まれたのは、得体の知れない闇への恐怖だった。町が何をしようとしているのか、どれほどの影響を受けることになるのか、それは全くの未知数だった。だが、この静かで息苦しい日常の中に潜むわずかな変化が、確実に自分自身を侵していると確信せざるを得なかった。
そんなある日、私は再びあの老人に出会った。彼は静かに微笑んで、ただひと言、「分かるかね?」と呟いた。その意味を理解しようとするほどに、私はこの町の一部になっていくような気がして、言葉を返すことができなかった。あの取り壊しの日から始まった日常の崩壊に、私はただ無力な観察者として立ち会うしかなかったのだ。
そして、町は今も冷たく私たちを見つめている。誰もその微かな変化を止めることはできない。それはまるで、暗黒の中に投じられた光が抑えられているかのような、そんな不気味な感覚を私たちにもたらしている。今、この町は静かに、確実に、我々の日常を崩壊させつつあるのだ。