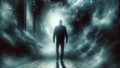廃れた孤島に建つその研究施設は、かつて科学の最前線を担っていたが、今では取り残された過去の遺物となっていた。周囲を睨むように峻険な波が打ち寄せ、咆哮する嵐の中でなお静寂に包まれたその施設には、何故か足を踏み入れた者の心を異様に沈ませる力があった。
寺田という名の男は、薄暗い昼過ぎにその孤島に降り立った。波止場に着いた船乗りたちが、何か暗いものに目を細めながら、その場を去って行ったのを背にして、彼は一人、静かに歩き出したのだった。施設の門は錆びつき、重く彼を拒むように軋んだ。その音は、鳥の叫びのように空虚で不吉であった。
寺田はその日、新たなプロジェクトの調査のために訪れたのだった。島に笑顔も言葉もないのは知っていたが、何か enemmänctionで培った彼の技術を、過去の遺産に応用できないかとの頼みがあったのだ。施設の内部は冷たく静まり返り、淡い光が低い天井の隅々まで届いている。階下から微かに響く、機械の唸りが孤独を誇張する。
少し経って、彼の耳に不可思議な音が届いた。風音に混ざり、遥かに小さな囁きが聞こえる。「……来ている…やっと……」。寺田は立ち止まり、音の源を探そうと耳を澄ませた。だが、次の瞬間には呑み込まれたように消えてしまった。空耳に違いないと自ら納得させる以外に、彼は歩みを進めることができなかった。
彼の目指す部屋にたどり着くと、そこは真っ直ぐな廊下で、数々の部屋が無機質に並んでいた。そのうち一部屋の扉に手をかけると、ノブが生々しいほど冷たく、その感覚が彼の指先まで伝わってくる。躊躇しながらも扉を開くと、そこには打ち捨てられた調度と、フローリングの上を這うか細い影があった。
拳を握りしめ、前を向いた瞬間、彼はかつての職員の写真が壁一面に貼られていることに気づいた。その中には、どの顔も何かを知ってしまった顔、決して笑わない双眸でこちらを見る、幾重にも連なる瞳たちがあった。
やがて、震える従業員室を後にし、地下階へと続く鉄製の隙間に身を投じる彼の背中に、森の奥で枯れ葉がこすれるような、微かな声が響き渡った。「行かせない……戻れ……」
彼はさらに深く、施設の腹部へと足を踏み入れた。下層の設備室には、既に用意されているはずのない機械が幾何学的に組まれていた。もはや何に使われるかも解らないその機械たちは、ただそこにあるだけで、時間を止めるようにしていた。
突然、灯りが明滅し始め、機械の中、深い奥に暗闇の入口が開いたようだった。寺田は呼ばれているというより、何かに誘われている感覚を覚え、尚も地下へと進んだ。音は次第に大きくなり、その声の持ち主たちがすぐ側にいるような現実感があった。
灯りが完全に消え、また点いたとき、彼は異質な冷気の影を垣間見た。伝統と科学の摩擦が生んだ歪な空間、そこには何千もの小さな手が伸びているように感じられた。次々と彼を追いつめる陰影は、天井の端、床の裂け目、部屋の隅々に潜んでおり、彼が動き出すことを待ちわびていた。
寺田は逃げるようにして突き進んだ。しかし、どこへ行っても同じ構造が繰り返され、見えるはずの光はどんどん遠ざかるようであった。嵐の音が突然に強まり、壁が震える。何か巨大な存在が息を潜めるこの場所で、彼は逃げ場を失った。館内の不気味なエコーは、不在の何者かの足音が彼を追う音へと変じた。
最後の扉を開けると、待ち構えていたかのように、突然寂寥が濃密に広がった。そこには部屋の中心に、楕円形の木製テーブルが一台。テーブルの上には、埃を被った古い写真アルバムが一冊。中には、数え切れないほどの家族たちが微笑んでいるが、それは寺田の見るところ、全く知らない人々だった。彼はその薄笑いさえ、何かしらの意図を持ったものと感じて恐ろしくなった。
それでも、なぜかその場所が彼には馴染み深かった。手を伸ばせば容易く届く凍りついた未来は、彼の予測を越えて想像を蝕む。このままここに居続けるならば、自らが何者であるかさえ失うかもしれない恐怖が、彼の背筋を貫いて通る。
突然、扉の向こうから聞いたことのない静かな音が聞こえてきた。ふと視線を移し、彼が見たものは、やっと気づいた虚ろな顔の一群だった。障子裏から、密かに見つめていたつぶらな瞳。彼が流れのままに求めた逃避先は、全てがゆっくりと、しかし精確に彼を包囲するのだ。
彼は無自覚に、一歩ずつ後退し始める。逃れねばならぬ強迫感が膝を震わせ、ついに壁に背が触れる。彼の夢が何であれ、一息、息を潜めるように彼は窮地に立っていた。その時、何かがしっかりとした重みを持って彼を見つめ返した。目を閉じることなく、彼は彼方のそこに潜むものの悲しいまでの幻を見出す。それこそが、彼の孤独の支配する場所だった。
寺田は、ここに自分だけの救いはないと悟り、外の嵐に身を投じる決意をした。だが、島が彼を無限に引き寄せる。どの影の中にも、彼の過去の名残が潜んでいる、この場所が、彼が逃げたかったすべてを具現化したのだ。そして、それこそが最も恐ろしい事実であるということを、彼は心の底から理解した。
やがて、嵐が静まり返り、影が彼の上に厚く垂れ下がる。彼はその場で立ち尽くし、すべてのことが自らの意志の及ばぬと知った。テーブルの奥、突如として現れた小さな光が、彼の全てを捉えて離さない淋しさの象徴であることを、完全に理解したのであった。