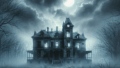深い山々に囲まれた小さな村。その村にはかつて恐ろしい噂があった。言い伝えによれば、夜な夜な村の者が一人ずつ姿を消し、その者は二度と戻ってこないという。その村に住む者は、皆この話を忌避し、日が暮れると誰もが家に閉じこもり、外をうかがうことさえなかった。
その村に、ある男が住んでいた。名を宏といい、彼は幼い頃から変わり者として知られていた。夜になると山奥の奥深くまで一人で歩き、何かを探すような様子で、村人たちは彼を「幻を追い求める者」と呼んでいた。宏の父は村で唯一の神主であり、言い伝えの「神隠し」の話が広まるのを嫌い、息子の奇行に悩んでいた。
その年の夏も、宏はいつもと変わらず山奥に足を運んでいた。ある夜、村は不穏な空気に包まれた。月が異様に明るく、その光に照らされた山は、まるで生きているかのように揺らめいているように見えた。宏は、その月光の下、村の外れにある神社の奥へと進んでいった。
神社の奥には、村人の立ち入ることを禁じられた「禁忌の道」があった。その道は年月を経て荒れ果て、自然と人の痕跡が入り混じる不思議な空間を作り出していた。宏はその道を何度も往復しながらも、決して禁忌を犯すことはなかった。しかし、その夜、何かに吸い寄せられるようにその道に足を踏み入れてしまったのだ。
道沿いには苔むした石碑がいくつも並んでいたが、何か異様な気配を感じた。石碑には、古代文字が刻まれており、それが何を意味するのかを理解する者は村にはもう誰もいないという。「ここはどこにつながっているのか」と思いながらも、宏はなおも奥へと進んだ。まるで何かに導かれるように、その足取りは確信に満ちていた。
やがて、月光に照らされた森の奥に、不思議な空間が広がっているのを見つけた。そこには、長い年月を経て朽ち果てた祠があり、その周囲を奇妙な彫刻が取り囲んでいた。森の静寂が彼の心をざわつかせ、風がざわめく度に、何かが囁いているかのような錯覚に陥った。
その時、宏は背後に人の気配を感じた。振り返ると、そこには古い着物を纏った女性が立っていた。彼女は優しい微笑を浮かべながら、「この道をたどる者よ、幾星霜を越えたる日の訪れを待て」とのみ言った。その声が耳に心地よく響く一方で、得も言われぬ恐怖が宏を包み込んだ。
その女性の姿は、次の瞬間には消え去っていた。彼は、ただ不安を抱えたまま祠の前に立ち尽くすことしかできなかった。そこには、かすかな音楽が風に乗って聞こえてきた。それは地を揺るがし、彼の心の奥底にまで届く、古代の旋律のようだった。
その夜を境に、宏は村から姿を消した。毎夜耳にした祠からの声が、彼を異界へと誘ったのだろうか。村人たちは森の奥深くへ彼を捜しに行ったが、ついに見つけることはできなかった。ただ、祠に施された古代の彫刻が、かすかに光を放っていたことだけが確認された。
何日かが過ぎ去り、村には再び平穏が訪れたかに見えた。しかし、幾晩か経ったある夜、宏は突然村に戻った。彼は笑みとともに語ることができたが、その目には確かに何かが欠けていた。戻ったはずの彼は、以前と何かが著しく異なっていた。
宏は村人たちとの会話も少なく、時間が経つにつれて、彼の声は次第に祠から聞こえてきた囁き声に似たものに変わっていった。その声は不気味で、日に日に彼の存在は影のように薄れていった。村人たちは彼の姿を見ることを恐れ、彼は次第に村の外れにある家に引きこもるようになった。
年月が流れたある日、宏は再びその森へと消え去った。村人たちは彼の後を追ったが、深い霧のようなものに阻まれ、道を見失ってしまった。それ以来、彼を再び目にすることはなかった。そして、彼が消えたあの晩、再び祠からはかすかな光が漏れ出し、森は不気味な静寂に包まれた。
それ以来、村では「神隠し」の話が再び語られるようになり、村人たちは森に近づくことを避けるようになった。宏がかつて幻を追い求めていたのか、それとも彼自身が幻となったのか。その答えは、誰にもわかることはなかった。
ただ一つだけ確かなのは、宏のいない村は何かが欠けてしまったということ。そしてその何かは、誰にも埋めることのできない深い虚無であった。宵闇が降りる度に村に漂うその虚無は、再び神隠しが行われたときまで消えることはないだろう。村の者たちはただ、その恐れを胸に、今日もまた繰り返し訪れる日々を、忘却の中で生き続けていくのであった。