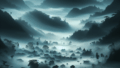雲のない秋の夜、空にぽっかりと浮かぶ満月が白銀に輝く中、村から少し離れた山奥にある古びた神社が、その荘厳な佇まいをひっそりと見せていた。村人たちは、代々伝わる数々の伝説や噂を信じ、この神社には近づかないようにしていた。ある者はこの場所を「触れてはならぬ地」と恐れ、ある者は「神々の領域」として畏敬の念を抱いていた。
だが、高校生である優也は、そうした禁忌にこそ興味をそそられていた。彼は都会育ちで、村の伝説や習わしを迷信と片付けるような性格だった。ある夜、冒険心と好奇心が募り、彼は一人で神社を訪れることを決意した。
山道を登るうち、静けさが圧し掛かるようにして優也を包み込む。風が彼の頬を撫で、森の隙間からは微かな月光が洩れていた。やがてその朽ち果てた鳥居が目の前に現れると、彼の胸中に一瞬だけ奇妙な感覚が走った。それは心のどこかでこの場所の異質さを感じ取り、ためらいを生じさせるものだった。
しかし、彼はその感覚を無視し、進み続けた。長い年月を経て湿気を吸った石畳を踏みしめながら、彼は手に持った懐中電灯を左右に振る。この道は夜の霧がかかり、まるで別の世界に誘われているかのようだった。
やがて、杉の木々が切れ、神社の全貌が月明かりの下に浮かび上がる。それはまるで時が止まったかのようにひっそりと立っていた。破風屋根は苔むし、拝殿の扉は風化した木製で、か細い鎖で閉ざされている。優也の呼吸がかすかに響きわたる。
彼は拝殿の前で立ち止まり、おもむろに手を合わせた。心のどこかで祈りを捧げるように、あるいはただの偽善的なポーズとして。彼の耳には、微かなざわめきが風の音に混じって聞こえる。思わず振り返るが、そこには何もない。ただの風が落ち葉を舞い上げただけだった。
そこで、優也は神社の境内をさらに調べることにした。彼は裏手へと回り込むと、朽ちた祠を見つけた。それは神社の陰に隠れるようにして鎮座していた。誰かが長らく訪れていないことを物語るかのように、祠は蜘蛛の巣と枯葉に覆われている。
優也はその祠に手を伸ばし、扉を開けようとした。しかし、その瞬間、背後から声が聞こえた。それは人間とは思えぬ、低く、掠れた声だった。「触れてはならぬ…」
驚いて振り返るも、そこには何の気配もない。ただの夜の静けさが彼の周りを取り巻いていた。優也の呼吸は荒くなり、手のひらに冷や汗が滲む。しかし、彼の好奇心は恐怖に打ち勝ち、再び祠の扉に手をかけた。
扉が開くと、そこには古びた木彫りの像が鎮座していた。それは何を象っているかも判然としない、ただただ異様にねじれた形をしていた。その瞬間、優也の背筋に冷気が走り、彼はこの像に何かしらの力が宿っているのを直感した。
それと同時に、空気が変わった。風が止み、蝉の声すら消え去り、静寂が支配する中、再びあの低い声が囁く。「戻れ…ここはお前の来るべき場所ではない…」
しかし優也は後戻りできず、祠の中を更に覗き込む。そして、一歩、また一歩と足を進めると、地面が揺れたかのように立ち眩みが彼を襲う。優也はその場に倒れ込み、視界がぶれる中、異形の像が彼を見下ろしてくる。
気を失う寸前、彼の耳には不気味な囁きが響き続けた。それはまるで数えきれぬ声が重なり合って、彼に何かを訴え掛けているようであった。「この地を汚す者よ、報いを受けよ…」
やがて、目を覚ました時、彼は薄闇の中に横たわっていた。空はすでに曙光が差し込み、彼の身体は冷え切っていた。現実と夢の境界が曖昧な中、彼は何とか立ち上がり、フラフラと神社を後にした。再び鳥居をくぐる時に感じたあの不思議な感覚は、今はより強烈な恐怖に変わって優也を縛っていた。
村に戻ると、優也の足取りは重い。彼は皆に、特に親友たちにこの体験を話すことはなかった。何故なら、その日を境に、彼の心には常にあの神社の声が響き続けていたからだ。それは「戻れ」とのささやきではなく、もっと深い場所で共鳴する、脈動する恐怖だった。
月日が流れ、優也は大学進学のために村を離れることになったが、彼の心の片隅にはいつもあの夜の記憶がこびりついていた。そして、誰にも話せないまま、彼は一生その恐怖と共に生きていくのであった。
村では未だに、古びた神社は「触れてはならない聖域」としてひっそりと存在し続け、人々の噂話に彩を添えている。それは、神秘と禁忌が絡み合う、得体の知れない恐怖を呼び覚ます場所として。