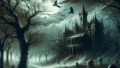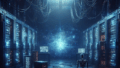【視点1:私、隆史の視点】
ある秋の夜、僕はいつものように駅から帰宅するために自転車を漕いでいた。空気は肌寒く、風が木々を揺らして不気味な音を立てていた。いつも通りの道を選んでいたけれど、その日は妙な感覚に襲われた。背後から何かがついてきているような、じっと監視されているような視線を感じたのだ。振り返っても誰もいない。しかし、確かに何かがいる——そんな気がしてならなかった。その夜以来、僕は家に帰るたびにそうした感覚に悩まされるようになった。
【視点2:友人、梶原の視点】
隆史から最近おかしな話を聞いた。夜道を歩いていると、何かに見張られているような気がするというのだ。普段は冷静な彼が、そんな話をするなんて珍しい。それに、彼はどうも疲れているように見えた。彼の話を聞いて、僕は冗談半分で「幽霊でもいるんじゃないか」と言ったが、隆史は冗談と受け取らず神妙な顔をしていた。それからというもの、隆史は日に日にやつれていった。電話をしても反応が鈍く、何かに怯えているようだった。不安に駆られて彼を訪ねると、彼の部屋は散らかり放題だった。彼は「部屋に誰かいる」と言い出した。そこには誰もいなかったが、何か異様な冷気を感じた。
【視点3:隆史の同僚、直美の視点】
会社での隆史は、以前の元気さを全く失っていた。仕事中にもぼんやりしていることが多く、ミスも増えてきた。何があったのかと聞いても曖昧に笑うだけで、理由を教えてくれない。ある日、彼は「夜道が怖い」とぽつりと言った。彼は極度のストレスを感じているように見えた。同僚たちとのコミュニケーションも減り、どこか異次元を漂っているかのようだった。彼の変化に私は心配になり、彼の様子を見るために数人の同僚と一緒に隆史の家に行くことにした。
【視点4:隆史の視点】
その夜、僕の部屋に立ち込める異様な雰囲気はますます強くなっていた。何もかもが鈍く冷たい。そして、一番確実なことは、この部屋には僕一人ではないということだ。僕が目にした姿は影のようにぼんやりしていたが、確かに何かが見える。耳元に冷たい風が流れ、一瞬だがはっきりと何かが話しかけてくる。本当に何かがいるのだ。僕は寝室から飛び出し、リビングで震えていた。
【視点5:直美の視点】
私たちが隆史の家に着いたのは、ちょうど彼がリビングで震えている時だった。彼は何かに取り憑かれているように見えた。そして、私たちは不可思議なものを目の当たりにした。隆史が示した寝室の方から、ひんやりとした冷気が漂ってくる。その冷気の中には、私が今まで経験したことのない異様な圧迫感があった。しばらくすると、突然電気が消えた。闇の中で、何かが動く音がする。隆史は「いる、そこにいる」と繰り返し叫んだ。
【真相:背景の説明】
実はこの家、かつて惨劇があったと聞く。数十年前、ある一家が突如行方不明になったが、その後一人がこの家に戻り、ここで険しい人生を送り終えたという噂があった。その亡くなった人物は孤独の中で自然死を迎えたが、彼の孤独な魂がまださまよっていると言われていた。そして、隆史が感じていた視線は、その魂のものだったのかもしれない。真相が明らかになったとしても、恐れはなぜか消えることはなく、ただひたすらに肌寒い。それは、多くの人が話したがらない、説明のつかない事実だった。