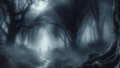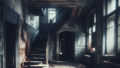はじめに断っておきますが、これは私が実際に体験した話です。誰かに話したことはありません。なぜなら、それはあまりにも奇妙で、一歩間違えば狂気の沙汰だと思われるかもしれないからです。しかし、今ここに記すのは、あの奇怪な出来事を思い出そうとすると、恐怖よりも不思議な安心感があるからなのです。
それは、昨年の梅雨の時期でした。まとわりつく湿気と延々と続く雨に、一日中家にこもる生活に苛立ちを覚えていました。そんな時、私はふとしたきっかけで、ずっと気になっていた山の奥にある廃村を訪れることにしました。「閉ざされた村」と呼ばれるその場所は、地元では有名な心霊スポットでもありました。でも私は心霊や幽霊など信じるタイプではありませんでしたし、単に廃墟の写真を撮ることに興味があったのです。
当日は小雨が降っていましたが、それでも出発しました。最寄りのバス停で降りてからは、山道を歩くことになります。道はぬかるんでいましたが、逆にそれが廃村探検の雰囲気を一層高めているような気がして、私はエキサイトしていました。しかし、思った以上に道のりは険しく、かつては道だったであろう道がすっかり雑草に覆われていて、迷ってしまいました。
しばらくして、私はふと一軒の古びた民家を見つけました。ちょうど雨が強くなってきたので、雨宿りをしようとその家に入ることにしました。玄関の扉は鍵もかかっておらず、少し力を入れると開きました。中は薄暗く、一歩足を踏み入れると湿気とお香のような少し甘い匂いが鼻をつきました。
中に人の気配はなく、少なくとも数十年間は誰も住んでいないように思えました。しかし、奇妙なことに家具や調度品は昔のままの形で残されていて、テーブルの上には湯呑みが置かれ、襖もきちんと閉じていました。なんだか生きた家のようでした。
雨が一層激しくなり、私はもう少しここで過ごすことにしました。ふと気づくと、いつの間にか雨音が遠ざかり、静寂が家の中を満たしていました。しかし、その静けさの中で、何かが見ているような視線を感じました。振り返っても誰もいません。しかし、その感覚はどうしても拭えませんでした。その時、ふと家の奥からかすかな音が聞こえました。それは何かを擦るような音でした。
不安になりながらも、私はどこから来ているのか確かめようと音のする方へと歩を進めました。廊下の突き当たりにあるふすまを開けると、小さな座敷がありました。だが、その部屋には誰もいませんでした。音はやみましたが、襖を開けた瞬間に何か大きな存在がそこにいたかのような感覚がしました。私はなぜか急に息苦しさを覚えました。そして、その息苦しさは次第に自分が見ている風景に違和感を感じるほどにまで増していきました。
戸棚の引き出しにかかれた錆びた鍵穴、机の引き出しには何も入っていない紙石鹸の箱、そこにあるものすべてが時間を止めたままそこにあるようでした。でも、もっとおかしいのは、私がここにいてはいけないのではないかという予感がしたことです。ここにいると私もこの場所とともに時間が止まる、いや、もっと言えば今の自分でなくなってしまうような感覚に襲われたのです。
私は急いでその座敷を後にしようとしましたが、奇妙なことにどの部屋の扉も廊下に繋がる入口も閉ざされているのです。同じ道を引き返したはずなのに、なぜか家の構造が変わっているようにしか思えませんでした。逃げるルートを探しながら、私はパニックになり、そしてついに玄関に辿り着くことができました。そして飛び出した先は、いつもの森ではなく、一面の真っ白い霧が漂う異質な風景でした。
その先はどうやって帰ってきたのか、もうよく覚えていません。ただひたすらに霧の中を彷徨い、気がつけばバス停に戻っていたのです。時間はどれだけ過ぎたかもわからず、その日は薄暗い夕暮れとなっていました。そしてバスに乗り込む際、私は再び異様な感覚にとらわれました。乗客たちの顔が、どこかしら私が入った家の中の調度品に見えてならなかったのです。目を閉じて次に開けたときには、その違和感は薄れていましたが、それでもどこか説明できないままでした。
あれからあの家のことは一度も調べに行っていません。しかし、時折、夏の蒸し暑い夜にはあの家の冷たい廊下と、異様な視線をもう一度感じることがあるのです。今回こうしてこの体験を書き記したのも、この不気味な体験を誰かと共有したい気持ちと、自分がいかにあの時正常さを保っていたかを確認したかったからかもしれません。
誰にでもこんなことが起こりうるとは言えません。ただ、もしまたいつの日か冒険心からあのような場所に踏み込むことがあれば、そしてそこで時間の流れが狂ってしまったかのような感覚に襲われたとしたら、自分の身を案じてください。その違和感こそが最も恐ろしいものの前触れかもしれません。