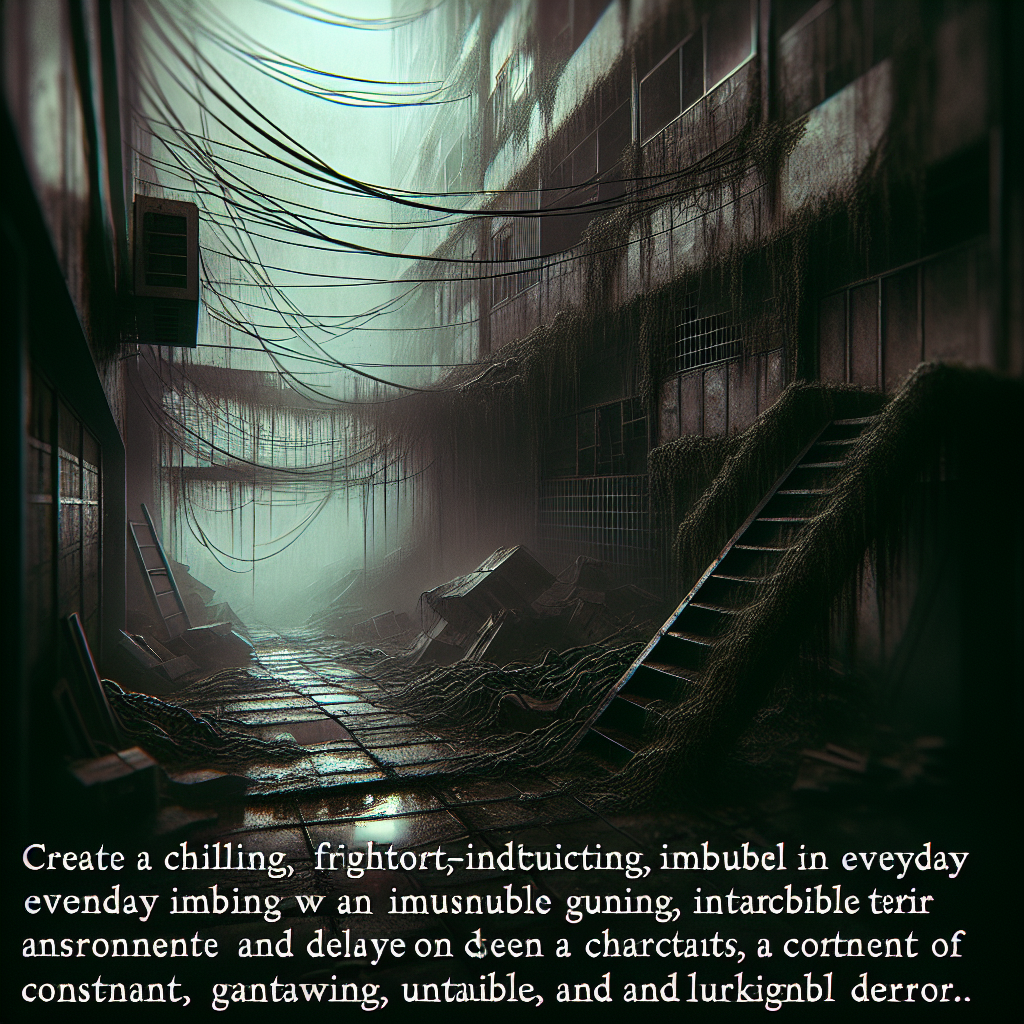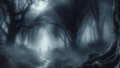彼女が最初に気づいたのは、追跡されているという怠惰な安心感だった。鈍い不安がじわじわと心に広がり、まるで無数の小さな虫が肌を這うように彼女を包みこんでいた。みちるは、数週間前から不気味なメッセージが届くことに気がついていた。どのメッセージも匿名で送られてきており、最初はただ「見ている」という短い文だった。それが次第に詳細になり、彼女の日常生活の些細な部分を言い当てるようになっていた。
彼女が誰かに監視されているのだという確信は、通勤電車の中でも、職場のオフィスでも、そして自宅の安全だと思っていた空間でも、彼女の心を苛み続けた。電車の窓から見える景色はどこか曖昧で、いつもの道のはずがどこか捻じれて見える。視界の片隅で感じる視線に、彼女は息を呑む。周りを見回しても、誰も自分に注目しているふうではない。それでも、この圧倒的な不安感が消えることはなかった。
翌朝、彼女は目覚まし時計が鳴る前に目を覚ました。まるで眠りが一瞬だけ途切れてしまったかのように、それまでの決まり文句の夢が砂のように崩れていた。無意識にベッドから這い出ると、彼女は窓を閉めたままにしていたカーテンを開けた。朝日が部屋を満たすが、どこか冷たさを感じる。彼女はため息をつき、昨日と同じルーチンを無意識にこなしていった。
会社に着くと、彼女の机の上に一枚の紙が置かれていた。そこには見知らぬ手書きの文字で、「今日は青い服を着ているね」と書かれていた。彼女はその文字をじっと見つめた。「彼」がすでにそこにいたような不穏な感覚が彼女の背筋をぞくりと冷たくした。振り返ると、同僚が何も気にならないように仕事を続けているのを見て、孤独感が彼女を襲った。
ソーシャルメディアのアカウントは閉じたにもかかわらず、メッセージは消えることなく続けられ、むしろその匿名性が増していた。中には、彼女が昼食を取ったカフェの写真や、家に帰る途中の彼女の後ろ姿の影が写った写真も送られてきた。それは、彼女の空間に徐々に侵入してくる影でもあった。誰も信じることができず、誰にも相談できなかった。最小限のコミュニケーションを保ちながら、この見えない襲撃者に耐えるしかなかった。
ある夜、彼女は友人の莉沙にこの不安を打ち明ける決心をした。誰にも知られずにずっと抱え込むことに耐えきれず、彼女は莉沙に電話した。莉沙はすぐに駆けつけてくれた。親友の温かさに少しだけ安心感を覚えた彼女は、これまでの出来事をすべて話した。莉沙は彼女の話をじっと聞いてくれたが、その目の中には微かな恐怖の色が見て取れた。
「うん、それは普通じゃないね」と莉沙は声を潜めて言った。「警察に相談してみるのもいいかもしれないよ」とアドバイスをくれた。みちるは深く頷いたが、何も解決しないのではないかという不安が残った。警察への相談は、事態がどこか別の次元へと突き進んでしまう恐れがあった。
その夜、彼女は一人で帰宅した。誰かを頼ることで誰かを巻き込むことが恐ろしかった。暗いアパートの廊下を歩きながら、後ろから足音が聞こえるような気がしたが、振り返る勇気はなかった。鍵を開けて部屋に入ると、ドアをすぐに閉めた。彼女の心臓は激しく鼓動していた。
部屋の静寂に包まれた彼女は、リビングの電気をつけ、そして何かがおかしいことに気がついた。家具の配置が微妙に変わっている。誰かが彼女の家に入ったことが疑いなくわかり、彼女は凍りついた。それは侵入者が残した証拠であり、その影がさらに近づいてきていることを暗示していた。
彼女はすぐにドアロックを確かめ、全ての窓を確認したが、全てのものが正常に見えた。それでも、この過去とは決して言えない不安感が彼女を締め付け続けた。絶え間ない不安と一緒に過ごす時間が耐えきれなくなってきて、彼女はついに警察に相談することを決断した。
警察署の薄暗い灯の中、彼女は自分の身に起きた出来事を淡々と語った。担当した警官は親身になって話を聞いてくれたが、証拠が少ないために大きな進展を期待することは難しかった。みちるは失望感を隠しきれず、何か罠にはまったかのような気分で家路についた。
日々は無機質に過ぎていった。メッセージは一層執拗になり、彼女の行動をすべて見透かしたような内容が増えていく。緊張は彼女の生活の隅々まで蝕んでいき、輝きを失った日常をさらに撃ち抜いていった。
ある晩、彼女はSNSでしばしば見慣れた風景の写真を見つけた。匿名アカウントが投稿したそれは、彼女のアパートの近くにある公園だった。そして、次の写真には彼女の部屋の窓が写っていた。それは明確なメッセージだった。彼はすぐそこにいる。
恐怖の感情はついに圧倒的となる。彼女は震えながらカーテンを閉め、覆い被さる無力感を払いのけるように携帯を手に取った。警察に再び連絡を取り、事態の緊急性を伝えた。やがて初動捜査が進むことを期待しながら、彼女は心細い一夜を過ごした。しかし、彼女の心の隙間には依然として不安と恐怖が残っていた。
その翌朝、彼女は再び目を覚まさざるをえなかった。空気は鉛のように重く、窓から差し込む光には容赦ない現実が続くことを示していた。彼女は駅へと向かう道すがら、これまで以上に周囲の風景を警戒した。周りの人々の顔は何かを隠しているようにしか見えなかった。
「監視者」はいまだ特定されておらず、彼の動機や正体は闇の中である。どこかの誰か、あるいは身近な誰かかもしれない。彼女の生活はさらなる不安と恐怖に満ち、そしてその存在は今もなお影を落とし続けている。現代の網の目に絡め取られたこの恐怖は、いつ終わるとも限らず、いつ襲い来るともわからない。彼女はただ、その日が終わることを祈ろうとした。