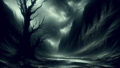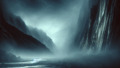数年前、夏の休暇を利用して日本の田舎を旅行することにしました。都会の喧騒から逃れ、静けさを求める私にとって、それは理想的な旅でした。インターネットで偶然目にした小さな山村、その自然の美しさに魅了され、ぜひ訪れてみたいと思いました。
名前も知らないその村。地図にも詳しくは載っておらず、詳細な情報もほとんどありませんでした。それでも観光地よりも静かで人の少ない場所をじっくり歩きたかった私には、ぴったりの行き先に思えました。
JRの地方線を乗り継ぎ、最寄りの小さな駅に降り立ちました。どこか昭和の雰囲気を残す駅舎で、駅員もいない無人駅です。ここから村までは徒歩で数キロ。道中は田園風景が広がり、普段の私の日常とは全く違う光景に胸が躍りました。
しかし、そこに到着してみると、その村は予想以上に独特な雰囲気を持っていました。村に入る手前で「よそ者歓迎せず」と書かれた古い看板を目にしましたが、特に気にせず進みました。村に入ると、民家が立ち並ぶ通りには人影がほとんどありません。たまにすれ違う村人も、私を一瞥するだけで、すぐに目を逸らしてしまいます。
村の中心にある小さな広場。そこには大きな鳥居があり、奥には古びた神社が佇んでいました。写真を撮ろうとカメラを向けたとき、不意に肩を叩かれました。振り向くと、いつの間にか私の後ろに村の老婆が立っていました。
「ここで写真はやめたほうがいいよ。」
老婆は低く、しかしはっきりとした声で言いました。その言葉に少し違和感を覚えましたが、礼儀正しくカメラを下ろしました。老婆は私をしばらく見つめた後、ゆっくりとどこかへ歩き去っていきました。
言葉にできない妙な不安感を抱えたまま、その場を後にしました。村の奥に進むと、やがて小さな宿泊施設を見つけました。この村で唯一の宿泊所らしく、営業中であることを示す看板も掲げられていませんでしたが、とにかく泊まる場所を見つけたことに安心しました。
若い女性が出迎えてくれました。彼女は私を見ると、少し驚いた表情を浮かべた後、無言で部屋まで案内してくれました。宿は古びた日本家屋で、どこか懐かしい香りに包まれています。
部屋に通されてからも、彼女は何も話そうとしません。ただ、何か重い空気が漂っているようで、私は妙に居心地の悪さを感じました。しばらくして彼女が口を開きました。
「夜になると、この村ではあまり外に出ない方が良いです。」
「どうしてですか?」と私が尋ねると、彼女は少し考え込むような素振りを見せた後、遠い目をして答えました。
「この村には古くからの風習があって、夜に外を歩くと、あなたもその風習に巻き込まれてしまうかもしれません。」
具体的に何が起こるのかは教えてくれませんでしたが、その言葉には奇妙な説得力がありました。私はその夜、部屋で静かに過ごしていました。しかし、不思議なことに、夜が更けるにつれて、どこからともなく太鼓や笛の微かな音が聞こえてきました。音のする方に目を向けてみましたが、窓の外は暗闇が広がるばかりでした。
音楽はまるで祭り囃子のようで、しかしどこか不協和音が混ざっているようにも聞こえます。その音に引き寄せられるように窓を開け、外を覗きました。遠く、神社の方でぼんやりとした光が揺れているのが見えました。
その瞬間、急に背中に寒気が走り、慌てて窓を閉めました。心臓の鼓動が早鐘のように鳴り響きます。あの音楽、あの光景、見てはいけないものを見た気がして、胸が締め付けられるような恐怖を感じました。
次の日、私が宿を出ると、昨日の老婆が再び姿を現しました。彼女は私に一枚の御札を手渡し、ひとことだけ、こう言いました。
「これを持っていなさい。」
一体何が起こっているのか、尋ねたいことは山ほどありましたが、それ以上何も言うことなく、老婆は立ち去って行きました。私にとってそれがこの村での最後の記憶です。
帰り道、振り返って村を見ると、そこはもはや現実とは思えないほど他の世界の一部のように感じました。電車に乗り込むと、再び都会へと戻って行く中で、あの村はまるで幻だったかのようにポツリと消えていきました。
東京に戻ってからも、あの村のことが頭から離れません。あの異様な雰囲気、老婆の警告、夜に聞こえたあの音…すべてが私の記憶に深く刻まれています。そして、家に帰っても、あの御札は捨てることができず、今もなお私の部屋の片隅に置かれています。
あの村の風習が何であったか、それを知る術はありません。ただ、私は二度とあの村を訪れることはないでしょう。そして、あの体験が現実であったのか、それともすべて夢だったのか、今も尚わからないままです。