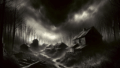ある日の朝、村の背後にそびえる山々は、目覚めた者たちにとって、いつもと変わらぬ光景を映していた。木霊のさえずり、朝露に輝く葉、そして山肌に立ち込める薄雲。しかし、その日、村の賢者であるエルダー・シムは、かつてなき不安を感じた。
彼は、山に向かい合い、静かに祈りを捧げた。すると、風に乗って不可視の声が彼に告げた。「目に見えぬものにこそ、真の変化が訪れる」と。その声に畏れを感じつつも、エルダー・シムはその言葉の意味を悟ろうと試みた。
それから数日、村は穏やかな日々を保っていた。しかし、やがて村人たちは徐々に不気味な変化に気付き始めた。はじめは小さなものだった。朝、顔を洗おうと汲んだ井戸の水が、微かな赤みを帯び始めた。「日光のいたずらか」と、誰もがその場では流したものの、心のどこかに不安が残った。そして、その不安は次第に形を変えていった。
夜になると、村の境界にある林から、ありえぬ音が聞こえるようになった。名もなき生物の呻き声、それに混じるように響く、低く深い、何かを訴えるような囁き。その調べは夜毎に強くなり、ついには村の中心にまで届くようになった。村人たちは寝室の窓を閉じ、その音から耳を塞いだが、やがては夢の中にまで侵入してくるのであった。
策に困り果てた村人たちは、再びエルダー・シムに助けを求めた。彼はひとり瞑想にふけり、古の書を紐解いていた。そこには、山の精霊が目覚める時期についての古代の逸話が記されていた。精霊は人間の行いを裁き、その定めに応じた天変地異をもたらすと。「しるしを見落とすな」と書かれたそれは、まさに今の状況を予言しているかのようであった。
エルダー・シムは村人たちに告げた。「我々の周りで起こる異変は、始まりに過ぎぬ。私たちは、日常を織り成す小さきものの変化に注意を払い、正しき行いを求めねばならぬ」。しかし、その言葉に耳を傾ける者は少なく、多くの者は自らの日々の営みを続けた。
離れに住む一人の女性がある日、愛猫の姿が鏡に映らないことに気付いた。それは彼女にとって小さな恐れであったが、時間とともにそれは周囲の動物たちにも拡がり始めた。影のない生物たちは、次第に眼に見えぬ存在が囁く言葉に耳を傾け始めた。
やがて、村は昼夜の区別を失い、空は常に薄明るく、時の観念は崩壊するかのようであった。夜光虫のように輝く虫たちが無数に集まり、昼でも夜でも、空間は奇妙な緑の光に包まれるようになった。村人たちは幻覚の如く、目に見えぬ存在を、その光に導かれるかのように浮かんで見た。
エルダー・シムは、自らの役目が近づいていることを悟った。古の巻物に従い、村の神殿にて祭壇を築き、山の精霊に捧げるべく、祈りを捧げた。「我々の罪を許し給え、この異変を納め給え」と。しかし、返ってくる声は変わらぬ無二の囁き、ますます増していく不安の声であった。
最終的に、村の周囲に立ち込める霧が晴れることはなく、その存在の中で、日常の境界は完全に崩れていった。村人たちは誰もが無言となり、その目にかつての光は失せていた。エルダー・シムは命の火を全うし、神殿の中で一人祈りの中に消え去った。
彼の祈りが届くことはなく、あるのみは、再生されぬかの地に住む者たちが、見えぬ日常と思考の中、永遠に囚われ続ける様相だけであった。それでも、風の中に響く何者かの囁き声は、終わることなく続けとどまる。村は、いつの世も変わらぬ「今」の中で、文明を紡いで行く者たちの孤独な試みの象徴として、終わりなき物語を静かに語り続ける。
そして、その村は、人々の記憶からまるで神話の如くに薄れゆき、やがて語り継がれることもなくなった。しかし、伝説として残された一つの教えがある、「目に見えぬ変化に、常に耳を傾けよ」、それは、どれほどの時を経てもなお、世界のどこかで耳を澄ませ続ける者への警告として囁かれ続けるであろう。