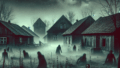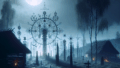これは古の時代から語り継がれる物語である。かつて、彼の地において人々が広大なる森を畏れ、敬った時代があった。その森は、神々の住まう聖域とも、異界への門とも言われた場所で、多くの伝説がその地の神秘を伝えていた。
ある時、一人の若者、名をユズルという者が村にいた。彼はその森に魅了されていたが、村人達は口を揃えて森に近づくことを禁じた。「森は神の領域、立ち入れば戻らぬ」と。しかし、ユズルの好奇心は日を追うごとに増し、乾いた喉が水を求めるように、森への渇望を募らせていった。
或る夜、月がその冷たい光で村を包む中、ユズルは一人森の縁に佇んだ。星々が彼に囁きかけるように瞬き、風が背を押すように吹いていた。その夜は特別であった。なぜなら、長老たちもたびたび語る「年に一度の夜」だったからだという。「今夜は二つの世界が交わる。何かが変わる夜だ」と忠告されていたにも関わらず、ユズルは森の奥深くへ吸い寄せられるように足を進めた。
森の中程に達した時、突然風が一切の音を奪った。静寂が深まる中、ユズルは奇妙な感覚に襲われた。彼の周囲の木々は、目に見えぬ力によって波打ち、古の言語で何かを語り始めたかのように聞こえた。その瞬間、森の中心より光が降り注ぎ、その中から白髪の女が姿を現した。彼女の目は星々のごとく輝き、声は天からの響きの如くあった。
「求める者よ、帰る者よ、汝の意志を示せ」と。ただの言葉として聞こえるものではなく、その声は彼の魂に直接語りかけるかのようであった。ユズルは心の奥底から「知りたい」という声を発した。女は微笑み、ユズルを光の中に包み込んだ。
次の瞬間、ユズルは見知らぬ土地に立っていた。そこはこの世のものとは思えぬ光景、人知を超えた風景が広がっていた。木々は歌い、風は絹のように肌を撫でた。すべてが美しく調和しているが、それ以上に彼を圧倒するものがあった。それは彼の存在自体が拡がる感覚、そして何か大いなる意図の中に組み込まれているような感覚であった。
時が経つにつれ、ユズルはこの新たなる世界の法則を理解し始めた。ここでは時間の流れが異質で、あらゆるものが互いに連結し、そしてそれらは一つの大きな意志によって動かされているように思えた。ユズルはその一部となり、次第に外の世界のことを忘れていった。
しかし、全ての時間の概念を超えた瞬間に、突然彼の目の前に再び白髪の女が立っていた。「汝の夢と現実を知れ。選ばれし者よ、元の場所に戻る時が来た」と告げると、彼の体は忽然と空に持ち上げられ、元の世界へと引き戻されていった。
ユズルが目を開けたのは、故郷の村のはずれの地であった。しかし、村の人々は彼を見て驚愕の表情を浮かべた。彼の姿は変わり果て、髪や目の色までが異なっていた。村人たちは彼がユズルであるとは信じられず、「偽りの者、異形の者」と呼ぶようになった。ユズル自身、故郷がもはや自分の知っていたものとは違うことに気付き始めた。
彼の内には森で得た記憶が燦然と輝き、それによってこの世界はかつての姿を失い、あらゆるものが偽りに見えた。村人たちは彼を忌み嫌い、そして恐れた。何よりも、彼自身が自分の身に起こった変化を恐れていた。
日が経つにつれ、ユズルは次第に言葉を失い始めた。外界の音は彼の耳には苦痛となり、世界は色褪せた虚空となった。彼はまるで自身が亡霊となり、自らの存在をすら見失っていくようであった。それでも、彼の心の中で森での経験は依然として輝きを放ち、戻ることのない現実に対する抗い難い欲求を増幅させた。
そして、村から姿を消す日が訪れた。人々は彼の名を忘れ、彼が再び姿を現すこともなかった。しかし、森のふところで、伝説はまた一つ加わった。今もなお、あの夜、行方不明になった誰かが森の濃霧の中で道を探し続けているのだという。
かくして、物語は語り継がれる。人が人であり続けることの脆さと、異界の魅惑が呼ぶ声との狭間に立つ、永遠の探索者たちの物語である。この世の理を超えた何かへの畏敬が、静かに語り継がれていくのである。