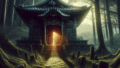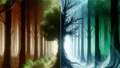夕暮れ時、薄紅色の光が街を包む頃、私はいつもの帰り道を歩いていた。通い慣れた路地には、古びたアパートの薄暗い影がいくつものっぺりと引き伸ばされていた。身の回りには、何もかもが変わらぬ姿をしている。それこそが私にとっての日常の風景であり、そこには何の恐れも不安もないはずだった。
しかし、その日の帰り道はどこか異様だった。アパートの壁には古いひび割れが新たに一本、垂直に刻み込まれており、その裂け目がまるで不気味に笑う男の顔のように見える。我が家の玄関のドアノブも、どういうわけか手にしっくりこない冷たさを帯びていた。凍えるような金属の感触が手のひらに食い込み、私の気分を乱した。
家に戻り、コートを脱ぎ捨てると、いつものようにテレビをつけた。ニュースキャスターの端正な顔がスクリーンを満たす。今日も何事もない一日だったと、いつもなら結論づけるところだ。だが、その日のキャスターの目はどことなく遠く、虚ろで、私の知らない別の現実を映し出しているように思えた。
風邪でも引いたのかと思い、早々にテレビを消してしまう。奇妙に静まり返った部屋は、私の気持ちをさらに不安にさせた。身の回りの物音に敏感になる。時計の針が一秒一秒を刻む音すら、心臓の鼓動に合わせて異常に大きく響いてきた。
次の朝、目覚めると、枕元で何かが私を見つめている気配がした。飛び起きて周囲を確認するが、そこには誰もいない。ただ、いつもの窓から差し込む光がどことなく青みを帯びて、まるで魚を浮遊させる水槽の中のような、ひんやりとした感覚を与えていた。
会社へ出勤する電車の中でも、違和感は続く。車内の乗客たちがどこか無表情で、その皮膚はローションを過剰に塗ったように不自然に光っている。まるで彼ら全員が、何かから逃れようとしているかのように見えた。次の駅に到着すると、いつもと同じアナウンスが流れるが、声が妙に濁り、語尾が震えているのが気になった。
職場に着くと、上司や同僚たちもまた、普段と違った雰囲気を漂わせていた。彼らは何かを隠しているようで、会話の合間に相談めいた視線を交わした。彼らの笑顔は、どことなく歪で、無理に作られた仮面のようだった。デスクに座り、パソコンに手を伸ばすと、妙に冷たいキーの感触が指に嫌な感覚を与えた。画面の青白い光が私の顔を無情に照らし出す。
時間が経つにつれ、私の中で膨れ上がる違和感は、次第に明確な恐れへと変わっていった。日常が、徐々に壊れていくような不安が胸を締め付ける。街の景色は確かに同じなのに、内部から何かしらの変質が進んでいるように感じられ、私はそれに抗えずにいた。
昼休み、デスクを離れ、休憩室でランチを取ることにした。いつも通りのランチボックスを開くが、食材の色がどれも不自然なほど鮮やかで、どこか新鮮さを欠いているように思えた。味もまた、どこか空虚で、私の体が受け付けず、すぐに食べるのを止めてしまう。歯が立たないゴムのような噛み応えと、人工的な風味に嫌気が差した。
午後の業務に戻るまでの間、デスクの前で微睡む。しかし、夢の中でも現実と同じ景色が広がり、その平坦さが何よりも私を悩ませた。場面が変わらない悪夢から目覚めるように、私の心も現実へと引き戻されたが、変わらない日常の束縛から完全には解放できなかった。
仕事を終え、帰宅の途につくときには、街の風景は一層に異質さを増していた。アパートの窓には無数の影が蠢いているようで、その影の主たちはじっと私を見下ろしている錯覚に襲われた。道行く人々もまた、ただ黙々と足を運び、誰もが同じ方向を向いているのに気がつく。それはまるで、行進する無意識の群れであり、街そのものが統制された機械のように動いているようだった。
帰宅しても安心感は得られず、むしろその代わりに、家の内部で感じる圧迫感は増すばかりだった。壁の微かなきしみ音が、いつもよりも鋭く耳に届き、空気に漂う僅かな湿り気が、私の皮膚に張り付き、逃げ出せない感覚を植え付けた。
そして、その夜。ベッドに横たわりながら、私はふと、天井の隅を見た。目に映るべき何もないはずのそこには、ぼんやりとした人影が現れ、それがじわりとこちらを覗き込んでいるように見えた。恐怖に凍りついた私は、動くこともできずにただその影を見つめ続けた。
影は徐々に形を成し、やがてそれが私自身の姿に似ていることに気付き、私は恐慌に陥った。その影は、私の日常が崩れ去る過程で生まれた、もう一人の私のように思えた。そうして、気がつけば、私は自身の影にとって代わられたのかもしれない、という不安に包まれていた。
こうして私の日常は、静かに、しかし確実に崩壊へ向かって進んでいた。見慣れた景色の中に潜む得体の知れない何かに気付きながら、それでも私はその日常を壊れた一部分として受け入れる以外に道はなかった。それはまるで、今まで信じてきた現実が一瞬にして偽りに変わるかのような、そんな恐怖だった。日常の中に潜む崩壊の予感――それこそが、最も恐ろしいものだったのかもしれない。