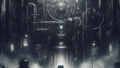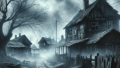山々の間に隠された片隅に、その神社は静かに佇んでいた。誰がいつこの神社を建立したのかは不明だが、地元の人々は「触れてはならない聖域」として長らく敬遠し続けていた。代々伝わる噂話は、その場所に近づいた者には不幸が訪れるという戒めの言葉を含んでいた。
その日、町の若者たちの中でも特に勇敢な一団が、この神社を探検しようと集っていた。彼らは学校の帰り道、互いにその意図を高らかに叫び合い、互いの勇気を鼓舞しながら向かって行った。その一員である達也は、内心の恐れを隠しつつも、好奇心に駆られてかつてない冒険に心を踊らせていた。
夕暮れ時、彼らはついにその場所に到着した。神社は鬱蒼とした森に囲まれ、まるで時が止まってしまったかのような静寂に包まれていた。鳥のさえずりも、風のささやきも、そこでは何処か別の世界の出来事のように遠のいていた。達也は鳥肌の立つ腕を静かに撫で下ろした。
古びた鳥居をくぐった瞬間、乾いた枯葉が足元にささやくように音を立てた。何かに見られているような錯覚に陥り、達也は仲間の一人、優奈の腕をうっかりと引っ張った。彼女は驚きで目を見開くも、すぐに微笑みを浮かべ、「ほら、大丈夫だから」と心配を和らげようとした。
神社の奥へと進むほど、周囲の空気は重く、そして冷たくなっていった。空に浮かぶ月は巨大な眼のように、無言の警告を与えるかのごとく彼らを見下ろしていた。やがて、苔むした石段を登り切った先に、本殿が姿を現した。そこには、その時代を遥かに超えた古めかしさと圧倒的な存在感があった。
「何もないじゃないか。」浩志がふと漏らした言葉に、一瞬の安堵が広がる。だが、その瞬間、突如薄暗闇の中、本殿の戸がきしんで開く音が耳に届いた。達也の心臓は否応なく跳ね上がった。風の仕業だと思い込もうとする自分がいたが、どうにも心の奥底でそれを否定する声がささやき続けていた。
彼らは緊張感を持ちながら、本殿の縁に近寄った。そして達也は、自分の勇敢さを証明せずにはいられない感情に突き動かされ、戸を完全に開いて中に足を踏み入れた。中は薄暗く、香の残り香が異様なほどに濃い。祭壇に近づくと、何かが心に訴えかけてくる音がした。それは、言葉ではなく感情そのものだった。
「何かいるのか?」優奈の声が震えていた。「いや、分からない。ただ…」達也は言葉を探したが、それ以上何も口にすることができなかった。その時、彼の視界の隅で何かが動くのを捉えた。反射的に振り返った彼の目に映ったのは、一瞬だけ現れた白い影だった。
その夜、若者たちは不思議なことに、神社に訪れたことについて一言も口にしなかった。何かに導かれるようにして各々の家に帰って行った。そしてその日を境に、彼らの日常はほんの僅かずつだが確実に狂い始めた。
達也は夜になると必ず、神社のことを夢に見るようになった。それはいつも同じ夢で、神社の本殿の中にいる自分が見知らぬ何者かに囲まれ、ただ静かに見つめ返されるというものだ。その眼差しは冷たく、しかしどこか懐かしささえ感じさせるものだった。
次第に、彼は夢の中でその存在に問いかけられているのだと感じ始めた。「なぜ来たのか。」「何を求めているのか。」毎晩心中で繰り返されるその問いの意味を考えるうちに、達也の心は不安に蝕まれていった。それと同時に、彼の周囲では奇妙な出来事が頻発するようになった。物音がするはずのない場所から聞こえる声、誰もいないはずの暗がりで感じる視線。現実と夢の境界が曖昧になっていった。
ある晩、ついに彼は耐えられなくなり、神社のことを優奈に打ち明けた。彼女も同じ夢を見続けていることを知った達也は、安堵と共に恐怖を新たにした。「あそこに行った時から何かが始まってしまったんだ。」達也が言うと、優奈は静かに頷いた。
「どうすればいいの?」彼女の問に、達也は答えを持たなかった。ただ、何かしなくてはならないという衝動に駆られていた。そしてついに、彼らは再び神社に足を運ぶことを決意した。目的は分からぬまま、ただその場に引き寄せられるようにして。
再訪の夜、月明かりがまるでかつての仲間を歓迎するかのように彼らを導いていた。そして再び鳥居をくぐり、本殿へと至る道を歩いた。達也の心中には、この神社の守り手の怒りを鎮めることができるという思いがかすかにあった。
本殿についた彼らは、戸を開け、再びその中に足を踏み入れた。祭壇の前に立ち、達也は言葉を探していた。「僕たちは、触れてはならないものに触れてしまった。どうか赦してください。」その一言が口から零れた瞬間、静かだった本殿に風が吹き抜けた。
その夜を境に、彼らの生活は少しずつだが正常を取り戻し始めた。達也は再び夢を見ることがなくなり、優奈もまた安らかな眠りを取り戻した。しかし、それでもなお時折、彼は無意識に神社の方向を見やることがあった。あの白い影が、今もそこにいて彼らを見守っているのかもしれないと思う時、かすかな寒気が背を通り抜けることもあったが、それが未知の恐怖から来るものではなく、どこかしら郷愁に似たものであることに彼は気づいていた。
神社は、再び山間に隠されたその役目を静かに果たしていた。訪れる者はない。しかし、達也にとってそこは、もう二度と触れてはならない聖域ではなく、ただ静かなる尊厳を保つ謎の地として心に刻まれていた。彼は、自らの無謀が招いた恐怖を忘れまいと誓いながらも、その地には一種の親愛感を抱くようになっていたのだった。