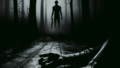静かな秋の夜だった。澄んだ空には銀色の月が輝き、風は冷たいが心地よく、枯葉がかさかさと音を立てながら道端に転がっていた。そんな夜に、町外れの小さな集落では一つの祭りが催されていた。古びた神社の境内には色とりどりの提灯が並び、妖怪たちの影絵が揺らめく。だがその夜、奇妙な事件が起こることを知る者は誰もいなかった。
祭りの主役である美少女、沙織は浅葱色の着物を纏い、友人たちと笑い声を響かせながら境内を巡っていた。彼女は人気者で、その無垢な笑顔は誰の心も惹きつけた。しかし、神社の裏手の林に差し掛かったとき、一瞬違和感を覚えた。何かが、耳鳴りのように微かに聞こえたのだ。それは、まるで呼んでいるかのような声だった。
「沙織ちゃん、どうかした?」友人の一人が心配そうに声をかける。しかし、彼女は体を震わせ、その声には答えなかった。ただ、何か魅入られたように、林の奥へと足を進めた。
「大丈夫だってば。ただ、ちょっとその辺散歩してくるね。」
友人たちは祭りの帰りに彼女を迎えに行くと言い残し、沙織は果敢にその黒い林の中へと消えていった。
その後、沙織は姿を消した。彼女を見送った友人たちは、約束の時間を過ぎても戻ってこない彼女を探しに行ったが、僅かなおぼろ月夜の中でその姿を見つけることはできなかった。祭りの喧騒が静まり返った境内に漂うのは、不気味な静寂だった。
翌日、地元の住民たちは総出で捜索を行った。林の奥深くまで踏み込んで見つけたものは、折れた枝、足跡、そして彼女のものと思しき小さな髪飾りだけだった。沙織は神隠しに遭ったのだと、誰もが口を揃えて言った。
時が過ぎて季節が移り変わっていく中、沙織はついに戻ってこなかった。だが、人々の噂話が静かになることはなかった。彼女の家族は深い悲しみに包まれ、友人たちの間では、あの祭りの夜の出来事について何か奇妙なものを体験したという証言が次々と出始めた。
ちょうど一年後、その集落に一人の旅人が舞い戻った。彼の衣服はずたずたに裂けており、追いつめられた目をしていた。その姿が沙織に似ていると気付くまで、村人たちは彼の周りに不安な視線を向けていた。まるで絵本から抜け出してきた幽霊のようだった。彼女が何を訴えようとしても、その声は何故かとても遠くに感じられ、何かが彼女の周りに纏わりついているようだった。
「あの世界から戻ってきた」と彼女はぽつりぽつりと語った。どんな世界なのか、それを述べるたびに彼女は目を背けていた。「そこは、色のない森だった。いつまでも夕暮れが続き、音ひとつしない。だけど、目の端に何かがちらつくの。」
沙織が語るその世界は、彼女が連れて行かれる夢の異界のようだった。人も動物もいないが、確かに何かがそこに潜んでいる。しかし、彼女はその何かを明確に言葉にすることができなかった。ただ、彼女が言うには、その異界に留まるほど、現実世界に戻る意志が薄れていき、別人格に支配されそうになったと告白した。
戻ってきた彼女を迎え入れても、何か通常とは異なる雰囲気は消えなかった。まるで彼女自身が別世界の番人のように存在しているかのようだった。友人たちと話すときも、昔の記憶を辿るときも、何かが浮上して消えていくのを感じる。その感覚は、やがて彼女の周囲を取り囲むように伝わり、村人たちの中にもどこか違和感を感じる者が増えていった。
村の人々は次第に彼女を避けるようになり、彼女もまた次第に孤立していった。神社の祭りももう二度と開かれることはなかった。そして、彼女の中に宿る異界の記憶は、現実世界の未来を侵食する運命を秘めているという噂がささやかれるようになっていった。
律義に現実世界に存在し続けるこの奇妙な違和感。それが何をもたらすのか予兆することもできぬまま、時は流れ続け、村はすっかり様変わりした。いつか、この地を訪れる者が、その秘密を解き明かすのか、それとも、また新たな神隠しが村を襲うのか。宙に浮かんだまま、沙織の言葉は風に乗って夢うつつの中に消えていった。