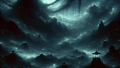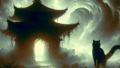あれはもう何年前になるだろうか。まだ僕が大学生だったころの話だ。ある夏のこと、僕は友人たちと一緒に心霊スポット巡りをすることになった。どうしようもない若気の至りで、いくつかの心霊スポットを回る計画を立てていたんだけど、その中でも特に有名な場所があった。
その場所は市内から車で二時間ほどの山奥にある廃村で、かつては炭鉱で栄えていたという。しかし閉鉱後は人口が減少し、いつしか完全に人が住まなくなってしまったというのがその廃村の歴史だ。地元では「何かが出る」と噂されていたけれど、具体的に何が出るのかは誰も知らなかった。ただ、行方不明者が多いという話だけが妙にリアルで、僕たちをその場所に引き寄せた。
当日は晴天だった。しかし、山道を進むにつれ、だんだんと雲行きが怪しくなってきた。車の窓から見える景色は、生い茂る草木で薄暗く、太陽の光も届かないような鬱蒼とした感じがあった。その時点で引き返すべきだったのかもしれない。でも、僕たちはそんなことを考えず、ただ興奮しながら車を進めていった。
ようやく目的地に到着すると、そこは予想以上に荒れ果てていた。いくつかの家が残っているものの、どれもこれも朽ち果て、今にも崩れそうな様子だった。特に目を引いたのは、村の中心にある小さな祠だ。そこには粗末な鳥居と、苔むした石碑があり、まるで何かを鎮めているようだった。気味の悪いことに、その周囲だけは雑草が一切生えていなかった。
僕たちは徒歩で村内を探索することにした。一人がビデオカメラを持ち、残りの数人は写真を撮ったり、メモを取ったりしていた。廃村とはいえ、昔の人々の生活の痕跡がそこかしこに見える。壊れた窯や、錆びた農具などがそのまま放置されていて、なんとなくその場を去った人々の思いを感じた。
しばらく探索していると、ふとした瞬間に誰かの視線を感じた。振り返ってみても、そこには友人たちしかいない。気のせいだと思い直し、再び探索を続けたが、どうにもその視線を振り払うことができなかった。
そのうち、僕らの間で何かしらの異変が起こり始めた。友人の一人が突然気分が悪くなり、さらにもう一人がひどく寒気を感じると言い出した。妙なことに、車に戻ろうとすると、その後を追いかけるかのように何かが背後に迫ってくるような感覚があったんだ。振り返っても何も見えないのに、その存在感だけは消えることがない。
そのとき、僕たちはある家の前に差し掛かった。そこだけは他の建物とは違い、まるでつい最近まで誰かが住んでいたかのように清潔だった。古びているはずの家具や食器には、埃一つついていない。おかしいと思いながらも、僕たちはその家に足を踏み入れてしまった。
中に入ると、一瞬だけ誰かの笑い声が聞こえた気がした。だがそれも、一瞬だけだった。僕らはお互いに何事もなかったように振る舞い、次第に誰もが黙り込んでしまった。全員が何かを感じていたに違いないけれど、それが何なのかは誰も口にしようとはしなかった。
そのとき、ふいにビデオカメラを持っていた友人が声を上げた。「見て! これ…。」
彼が指差した先には、カメラの液晶画面があった。そこに映し出されているものは、僕ら自身だった。だが、薄暗い映像の中、確かに僕たち以外の何かがそこにいたんだ。明らかに人影がいくつも揺れている。それは、僕たちを取り囲むように移動しているようだった。
「もう嫌だ、ここを出よう。」
誰からともなく声が上がり、僕らは恐怖心に駆られるまま、その家を飛び出した。外に出ると、先ほどまでの重苦しい空気が嘘のように、少しだけ晴れやかに思えた。それでも、僕たちは一刻も早くその場を後にしたくて、慌てて車に向かった。
車に戻ると、すぐにエンジンをかけて村を後にした。僕たちの顔には安堵と恐怖が混じっていた。道中、誰も口をきかなかった。ただ、それぞれが何事もなかったかのように振る舞い、無事に帰り着くことだけを考えていた。
しばらく経ってから、ビデオカメラの映像を確認することになった。あのとき、あの場所では鮮明に見えた人影が、撮ったはずの映像にはかすかにしか残っていなかった。ピンボケしているのか、それともただのホコリか、そう思えば納得できないこともない。
だが一つだけ、どうしても説明がつかないものがある。最後に外に出た瞬間、確かにカメラは僕たちだけを映したはずなのに、大勢の人間がこちらを見ているような映像が一瞬だけ記録されていたんだ。それはまるで、あの廃村の住人たちが再び戻ってきたかのように。
その後、僕たちは二度とあの場所を訪れることはなかった。あれ以来、少しでも不気味な噂のある場所へ行くことは避けている。みんなでそのことに触れることもなかったが、それからしばらくは何かに追われているような気がしてならなかった。
今こうして思い返すと、本当に恐ろしい体験だったと思う。心霊スポット巡りが趣味の友人たちも、あの日のことについては口を閉ざしている。しかし時々、何かの拍子にあの視線を思い出してしまうことがある。それは何とも言えぬ、冷たさと暗さを伴うものだった。
もう二度と味わいたくはないけれど、それが現実からかけ離れているのかと言われれば、疑問に思うことがある。あの瞬間、確かにそこに「何か」がいたのだから。