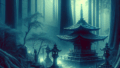霧の深く立ち込める晩秋の夜、古びた旅館の姿は闇に溶け込むようにひっそりとしていた。外界と隔絶されたようなこの場所には、かつてその名を広めた温泉が湧き出しているはずだったが、今では誰も寄り付かない。木々に囲まれた道を進むと、風に舞う枯葉があたりを支配する静寂を一層際立たせた。
誰もいないはずのこの旅館に、若き作家である斎木智哉が一人足を踏み入れる。それは出版が決まった短編集の仕上げに集中するための、静かな執筆環境を求めてのことだった。斎木はこの孤独な環境を心から求めていた。日常の喧騒から逃れ、静謐な場所で考えをまとめることが必要なのだと信じていた。
受付に立ってみると、古い木造の建物からは不思議な魅力が漂っていた。時代を経た木の香りが鼻孔をくすぐり、薄暗い照明の下、埃を被った調度品たちが寂しげに佇んでいた。受付には誰もおらず、鍵だけが無造作に置かれている。首を傾げながらも鍵を手に取り、案内板の指示に従い自分の部屋へと足を向けた。
部屋に入ると、古いものの掃除は行き届いていて、不快な印象はなかった。それどころか、どこか懐かしささえ感じた。窓の外を見れば、霧が薄くなり、月明かりが遠く山々をぼんやりと浮かび上がらせていた。斎木は机に向かい、原稿用紙にペンを走らせ始めた。静寂の中、ペン先が紙を擦る音だけが微かに響く。
その時、不意に廊下から音がしたように思えた。耳を澄ませるが、続く気配はない。気の所為だろうと自分に言い聞かせつつ、斎木は再び創作に没頭した。しかし、それから数分も経たないうちに、再度廊下から物音が聞こえた。低く唸るような風の音、または遠くで何かが軋む音とも取れる。
気になってドアを開けてみたが、廊下には誰の姿もなかった。ただ、長く伸びた廊下の端が闇に呑み込まれて見えない。ふとした不安に駆られ、部屋に戻ってからドアをしっかりと施錠した。鍵が確かに掛かる音を確認し、斎木は再び作業に戻った。
しかし、その夜、斎木は奇妙な夢を見た。旅館の廊下を、誰かに追い立てられる夢だ。振り返ると、視界の端に白い人影が過ぎる。声を上げようとすると、声はかき消され、廊下の先へ引き込まれるように走らされる。目が覚めた時、心臓が激しく鳴り響き、冷たい汗が背にびっしょりと張り付いていた。
翌朝、斎木は重苦しい頭痛を感じながら目を覚ました。窓の外は濃い霧に覆われ、世界の輪郭が曖昧に溶けている。昨晩の夢のせいだろうか、どことなく現実感が揺らいでいる気がした。気分転換にと館内を散策するが、どの部屋もがらんとし、人の気配が微塵もないことに初めて気付いた。
不意に、廊下の床板がきしむ音がした。あの白い影が、夢の中から現実に忍び寄りつつあるようだ。斎木は恐怖に駆られ、何の考えもなく他の部屋のドアを次々と開けながら、助けを求めるように叫んだが、誰も応えない。この旅館にひっそりと立つのは、彼一人だけなのだ。
しばらくして、階段を上がった先の踊り場で、愕然とする光景に出くわした。それは、大きな鏡がかけられた壁だった。鏡のこちら側に映るべき斎木の姿は、ぼんやりと霧の中に溶け込んでいるかのように不鮮明だった。そして、その背後には彼が認識していないはずの白い影が、静かに佇んでいる。
心臓が冷たい何かに握り潰されるような感覚を覚えたその瞬間、斎木は振り返った。しかし、そこには何もいない。ただ、闇に沈む廊下が続くだけだった。
不気味に静まり返る館内では、斎木の抱く恐怖が徐々に現実のものとなっていった。彼は焦燥感に苛まれつつ、出口を求めたが、なぜか旅館の構造は変わり果て、無限に続く混沌の迷路のようになっていた。どこをどう歩いても元の場所に戻され、どこからともなく感じる視線と、耳元で囁く風のような声に怯える。
彼の心は、極限の恐怖に蝕まれていった。逃げ場を失い、自らがこの狂気を作り出しているのではないかという疑念さえ頭をよぎる。だが、この旅館には確かに何かが潜んでいる。
夜が訪れると、斎木は再び机に向かった。逃げ出すこともできず、途方に暮れた彼は、夢中で手を動かし続けることで現実から目を逸らしたかったのだ。彼の描く物語は歪んだ現実を映し出し、いつしか彼自身の運命をも左右するものとなっていった。
その時、不意に肩を叩かれる感触がし、斎木は悲鳴を上げて後ろを見た。しかし、そこには誰もいない。ただ彼の孤独と恐怖が静かに微笑んでいるかのようだった。それから数日経っても、斎木が旅館から戻ることはなかった。探索に訪れた人々が彼の荷物だけを発見し、彼の姿はどこにもなく消えうせた後のことだった。彼の行方を知る者は誰もいない。月のない夜、かの古びた旅館は静かに佇み続ける。斎木が残した原稿だけが、彼の存在を伝える唯一の痕跡として、今も旅館の奥の一室に眠っている。