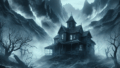かつて人々の心に恐れと敬意を同時に抱かせた時代、その時代は技術と知識が人間の限界を超え、神の領域に達しつつあった。偉大なる知識の座、そこには謎めいた書物が積み重ねられ、秘儀の巻物が光を拒み眠っていた。科学はその輝かしい進展によって、やがて禁忌とされる領域、つまり生命の真理に触れる領域へと到達した。
その中にあって、一人の研究者がおり、彼の名は知れ渡っていなかったが、その行いは未来の世代へ語り継がれることとなる。彼の名はクラウス、賢者のなかでも最も大胆な者と呼ばれた。この者は人体と魂の謎を解くために、神に背き、大地と天を冒涜しようとした。彼が築いた研究所は高山の頂にあり、神々の居住するはずの場所に彼は住まいを構えた。
クラウスは神の火を盗み、新たな創造主にならんとする欲望を持っていた。彼は生命の「コード」、その秘められたる螺旋を解明しようと、多くの生命を犠牲にし、彼を恐れながらも崇拝した者たちを従えた。幾千もの細胞が彼の手の中で試され、その果てに、未曾有の存在を生み出そうとした。
ある夜、強風が山を揺るがす中、その実験が幕を開けた。彼の前に横たわる無垢な肉体、それは天に捧げる罪深き生け贄であった。彼はその身体に多くの針を刺し込め、生命の力を呼び覚ますべくして雷鳴に祈りを捧げた。そして時至り、雷光が空を裂くと、その瞬間、生命は形を成し、動き始めた。新たなる創造物、其れは神に似て非なる者であった。
されど、その存在には魂が無かった。例えば、雄大なる大樹のように、葉は揺れ枝は伸びるものの、その根に養分を吸う気配が無いかのよう。クラウスはそのことに気づくことなく、自らの創造に歓喜し、偽りの神としての至高の座を夢見た。しかし、その生命はただの器、魂なき殻に過ぎなかった。
いずれその偽りの生命は、自分に欠けたものを求め始めた。生命に必要な根本の在り方、即ち魂と意識を求め、研究所を浮かれ歩いた。被験体はまるで蛇のように這い、研究者が備蓄していた薬物を片端から消費し、無理矢理にでも意識を広げようとした。クラウスはそれに気づいたとき、既に手遅れであった。その生命体は遂に、自らの命という枷を解こうとするかの如く、研究所を破壊し始めた。
先人たちの知識にしても、彼は過信し、限界を試してみたいという欲望に囚われ、ついには惨事を招いた。彼が築いたものは、その実、自らの破滅のためのものへと変わり果てた。研究所の下界、山の村々では異変が起こり始めた。地面は血を吐くかの如く赤く染まり、空は重き雲に覆われた。村人たちはこの変異を恐れ、大地は悲しみと嘆きを漏らした。
クラウスは己の所業の果てを目の当たりにし、その悔恨に打ちひしがれた。偽りの神を生み出したに過ぎない罪人として、神に許しを乞い、天に向かって叫び声を上げた。それは何者にも届かず、風にかき消された。彼が自らの意図せぬところで生み出してしまったその存在は、もはや人間が制御できるものではなく、何も持たぬ狂気の道具に過ぎなかった。
その頃、山を囲う森から見比べると、研究所の上には常に暗雲が立ちこめ、雷はその中心に落ちるかのごとく静かに狂乱せんとしていた。人々は畏れおののき、暗示に囚われているかのように日々を過ごした。だが、ある夜、彼らは鈴の音を聞く。高山からしたたり落ちる水の音に混じって、それは次第に高まり、ついには神の怒りを示すかのようにその震えを伝えたのだ。
村の長老は古き巻物を広げ、その予言を人々に告げた。彼以外はその言葉を理解できず、ただ耳を傾けることしかできなかった。「時来たりて、禁忌を犯した者には、その報いが下される。大いなる嵐が人々を覆い、全てを飲み込むまで、決してその手を休めてはならない。人智を越えた力を欲する者には、相応の試みが与えられよう。」
果たして、予言の通り、やがて山は崩れ去り、研究所はいかなる力にても逆らえぬ自然の猛威に飲まれて消え去った。クラウスの名は歴史の中から消え、ただ一つ、彼が成したものは「禁忌」として語り継がれることになった。
それ以来、人々は恐れを抱き、再び神の支配に戻ることを誓った。技術と知識、それだけでは制御できぬ自然の力を前に、かつての栄光は無力であることを知ることとなった。そして、その予言者の言葉は、人々の心の奥深くに刻まれ、再びそのような悲劇が起こらぬよう、知識と謙虚を胸に刻んで生き続けることを誓った。
これこそが、科学という刃を扱うことについて、己を顧みるべきと人が悟るべきであることをあらわした物語である。この教訓は、風化することなく、未来に語り継がれる定めとなった。かくして、人間とは、畏れを知り敬意を抱くことで、ようやく神の寛恕に触れられるのである。かの偽りの創造物の魂なき運命を教訓に、こうして人々は、再び自然の中に回帰したのであった。