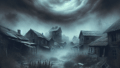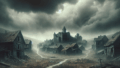彼女の名は、静香であった。どこにでもいる、ごく普通の大学生。しかし、その日常は一通のメッセージで唐突に崩れていくことになる。日々、当たり前のように使っていたSNSの世界に、その侵入者は何の前触れもなく忍び込んできた。
メッセージは、ごく簡潔なものであった。「見ているよ—あなたの全てを。」いつものように、寝る前にスマートフォンを手にとって画面を開いた静香は、送信者不明のその一文を目にした瞬間、全身にぞっとするような寒気を覚えた。最初は悪戯だと思った。しかし、その背後に潜む“何か”が、静香を次第に追い詰めていくことになる。
翌日から、彼女の日常は微細に変わり始めた。教室で、図書館で、カフェで、誰かに見られているような視線を感じるのだ。街を歩けば、路地の隅に佇む影が視界の端によぎることが増えた。スマートフォンを手にするたびに、新しいメッセージが届いている。「今日も綺麗だね。」、「その青い服、似合ってる。」送信者不明で、それでも静香の生活の細部にまで及ぶ内容だった。
最初は彼女も、ごく小さな不安に過ぎないと思っていた。しかし、時間が経つごとにその度合いは増していく。静香は周囲の友人たちに持ちかけた。何か知らないか、と。「もしかしたらストーカーかもしれないね」と軽い口調で返されるが、静香は笑って受け流すことができなかった。何故なら、その言葉が最も的を射ているように感じたからだ。
しばらくして、彼女の周囲に変化が訪れる。夜、帰宅途中でバス停に立っていると、乗り込んだバスの後ろの席に誰かが座ってきて、降りるとその影もまた静香の後をついてくる。静香は、振り返った。そこには、いつものように通り過ぎる人々の姿しかなかった。
不安は恐怖に変わりつつあった。静香は、スマートフォンを置き去りにして、しばらくの間SNSからも距離を置こうとした。だが、それが益々彼女を恐怖の深淵へと押しやってしまう。それでも不断に届くメッセージの通知音は、まるで静香の心を締め付ける蒸気機関のように響き渡った。「どうして無視するの?」、「今日はどこへ行っていたの?」
次第に、静香はすべてに怯えるようになった。日差しが差し込む教室の静けさも、図書館の閲覧室に満ちるページをめくる音も、腕時計の刻む秒針の音さえも、彼女にとってはただ恐怖を掻き立てる要因でしかなかった。SOSを発信するすべは何も持たず、ただ彼女は不安の沼に沈んでいった。
ある夜、ついに静香は決意した。これ以上の困惑に身を委ね続けるわけにはいかない。友人であり、唯一信頼を得ている人物である涼へ相談することにした。涼は静香の言葉を真剣に受け止め、計画を立て始めた。「君の周りを監視している人間がいるのなら、先にその動向を探るべきだね」と。
静香と涼は手を組み、一歩慎重にその真相を追っていく。涼は情報技術に詳しく、ネットの知識を駆使して不審者の足跡を掴もうとしたのだ。しかし、そこには彼らの予想を超える闇が広がっていた。メッセージの発信元を探り当てても、その不審者は巧妙に痕跡を消し去っていた。
それでも彼らは諦めなかった。ついに、涼は何かを掴んだ様子だった。ある日、彼は静香のもとに駆けつけてきた。そして、メッセージの一部から抽出したデータを示し、「この送信者、君の身近に潜んでいる可能性が高いよ」と語った。涼が手にしたノートパソコンの画面には、どこか見覚えのある名前が表示されている。
その名前を見た時、静香は心臓が凍りつくような感覚に襲われた。それは、彼女が普段通っている大学の同級生、そして時折言葉を交わす程度の間柄であった青年のものであった。彼は社会的には大人しそうで目立たない存在だったが、だからこそ誰も疑わなかったのだ。
今、全てが繋がり、辿り着いた現実に静香は戦慄した。後日、静香と涼は警察に相談することを決意し、問題はあっという間に警察の手で処理されることとなった。しかし、静香の心の中に刻まれた深い傷は、簡単に癒えるものではなかった。彼女は以前よりも慎重に全てに歩み寄らねばならなくなった。
SNSの新しい投稿は、もう二度と彼女の手から生まれなかった。その安全であるはずの日常は、今もどこかで彼女を追う影に怯えている。失われた安心感、壊れた現実。それらは、彼女にとってあまりにも大きな代償となった。
現代の情報社会には、匿名性と言う名の甘美な罠が潜んでいる。目に見えぬその闇は、誰にでも影を落とす可能性を秘めているのだと静香は実感した。ただ、その事実を身をもって知らされたとき、その代償が何であるか、誰も知り得なかった。