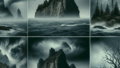錆びついた鉄格子の向こうに、ひっそりと佇む洋館があった。古びた木々が生い茂り、一見すると自然に飲み込まれた遺跡のように見えるその建物は、かつて裕福な商家が暮らしたと言われている。しかし、今では住む者もなく、ただ風がその隙間を通り抜けるだけの存在となって久しい。この地に伝わるいくつかの噂が、その理由を詮索する。
ある秋の夕暮れ、大学で民俗学を専攻する青年、達也は、一人静かにその洋館を訪れた。彼の目的は、その洋館にまつわる怪異の真相を解き明かし、卒業論文に活かすことであった。周囲の人々は一様に、その洋館には何か邪悪なものが宿っていると囁いたが、達也はその真偽を確かめたくてたまらなかった。
玄関への道は荒れ果て、草が足首を掴むように生えている。達也はその小径を進み、重厚な扉の前に立った。取っ手に触れると、冷たい鉄の感触が肌にじんわりと伝わる。不思議と、扉は音を立てずに開いた。館内に足を踏み入れると、長い間風雨に晒された匂いが鼻をつく。目を凝らしても薄暗い室内、達也は懐中電灯を取り出し、辺りを照らした。
家具はそのままに残され、豪奢さを物語る。しかし、埃が全てを覆い尽くし、時の流れとともに忘れ去られた過去の影でしかなかった。彼は静かに階段を上り始めた。微かに軋む音が、階下の広間に反響する。その音が、どこか異世界からの囁きのように達也の耳に忍び込んだ。
二階の廊下に出ると、ふと、達也の心に不安が芽生えた。光を頼りに奥へと進む彼には、壁に掛けられた肖像画が、不気味にこちらを見下ろしているように思えた。黒い瞳はどこまでも底の知れない深淵そのもので、その人物の意志がそこに宿っているかのごとく感じられた。
歩みを止め、画をまじまじと見つめる。全身をゾクッとした寒気が走る。なぜだか、その瞳が感情を持っているかのように、達也には感じられた。だがここで引き返すわけにはいかない。彼は意を決し、最奥の部屋の扉を開けた。
その瞬間、不可解な光景が目の前に広がった。部屋の中央には、丸いテーブルがあり、その周りには椅子が並べてある。どの椅子も人が座っているかのように角度が微妙に異なっている。達也は背中に冷ややかな汗を感じた。机の上にある古ぼけたノート、そのページは自然に開かれていた。
手を伸ばし、恐る恐るノートを手に取る。開かれたページには、何者かの筆によるスケッチが描かれていた。中央に一人の男性――どこか既視感のある顔立ちで、達也は再び先ほどの肖像画を思い出した。その周囲には、何人もの人物が描かれており、それらは空虚な笑みを浮かべ、中央の男を取り囲んでいる。
その絵に目を凝らしているうちに、急に足元がふらつくような感覚を覚えた。まるでこの部屋全体が彼を飲み込もうとしているかのようだった。達也は急いでノートを閉じ、呼吸を整えた。しかし、沈黙の中で微かに響く声――それがどこからともなく聞こえてきた。
「帰らなければならない。彼が待っている。」
その声は確かに彼の耳に届いた。男の声、それも遥か遠い過去からの響きのように感じる。達也は即座にその場を離れようとしたが、足が重く、まるで何かに引き摺られているように動けない。部屋の空気は変わり、急速に冷たくなった。
やがて一つの影が、部屋の片隅から滲み出るように現れた。その姿はあの日の肖像画で見た男、そのものだった。達也は立ちすくみ、歯の根を噛みしめた。なぜか、その男の瞳と合った瞬間、目が離せなくなる。
「ここにいるのは…おかしい。」男は囁いた。彼の表情は、何故か憂いを帯びている。
その言葉に意味を見いだせず、達也はただ怖れおののいた。彼はふと、館の外から聞こえないはずの風の音を感じた。それが幻聴でないとしたら、この奇妙な邂逅は現実だということを彼に知らしめた。
そして、次の瞬間、男の影はそのまま淡く、部屋の薄明かりとともに溶け込んで消えていった。彼は振り返りもせず、その場から駆け出した。階段を駆け下り、玄関を出ると、外の冷たい空気が彼を包み込んだ。
ここから二度と戻らないと決めた達也は、ひたすら走り続けた。振り返ることはしない。真実を追い求めた彼はその土地の秘密を知り尽くし、手を伸ばしたが、彼が目にしたものはただの影の交錯であり、自分の想像力が生み出した一瞬の闇でしかなかったのか。それとも、あの館には本当に何者かの思いが囚われていたのか。
彼はその答えを追い求めることを諦め、二度と戻ることはなかった。しかし、あの夜、彼の心には決して消えることのない恐ろしい記憶だけを残した。それは、確かに実在した光景が紡ぐ、彼の人生に深く刻まれた闇だった。