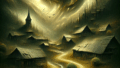あれはまだ、僕が大学生だった頃の話だ。季節は夏、蝉が狂ったように鳴き、夜の風が蒸し暑い最中である。ゼミの仲間たちとは、しばしば夜遅くまで飲み歩くことが常だったが、その日も例に漏れず、私たちは深夜の街を徘徊していた。
「知ってるか?この辺には、ちょっとした噂があるんだ」
そう切り出したのは、ゼミ仲間の中でも一番のおしゃべり、斉藤だった。風が少し強くなり、不気味に木々を揺らす中、彼はどこか楽しげに続けた。その話の内容は、彼の友人が実際に体験したという、なんとも奇妙な出来事だった。
「俺の友達の、さらにその友達なんだけどな、ある夜、帰宅中に妙なものを見たらしいんだ」
彼の言葉に半信半疑ながらも、私たちは少しずつ興味を引かれていった。話によると、その友達は深夜過ぎに自宅へ帰る途中、人気のない公園を通り抜けようとしていた。夜の公園は暗く、昼間には賑やかな子供たちの声が消え去り、静寂だけが支配している。
「公園の中にある錆びたブランコがさ、誰もいないのに揺れてたんだってさ」
斉藤の話は続き、私たちの想像力は徐々に働き出した。可動を繰り返しているブランコには、誰かが座っているように見えた。けれども、公園には他に誰もいなかったという。
「なんだか、気味悪いなって思うかもしれないけど、その友達は怖いもの好きで、そのまま近づいていったんだって」
未知のものに対する好奇心は強くもあり、危険でもある。彼の友達は、ブランコのさらに向こうに薄っすらと見える原形に目を凝らし、そこに何か奇妙なものを見つけた。
「そこにね、座ってたんだって。女の人がさ」
その一言に、私たちは一斉にびくりとなった。深夜の公園に、一人きりで座っている女性。それは、どう考えても普通ではない。
「目が合ったら、すぐに去った方がいいって、婆ちゃんが言ってたんだよ。理由は分からないけど、目が合うと呪われるって」
噂話の類いだと思いつつも、その話には奇妙な重みがあった。女性と目が合えば、どうなるのか。震えるような恐ろしさを想像しながら、私たちはつい口をつぐんでしまった。
「でも、友達は逃げなかったんだよ。その女性の顔が、まるで仮面のように無表情で、何か言いたげな感じだったんだってさ」
その時の友達の心境を想像すると、背筋に寒気が走るようだった。近づいてみると、彼女の顔は淡白で、目だけが異質に輝いていたという。周囲の暗さに対して、その目は、まるで闇夜に灯る異端の光そのものだった。
「なにか、声をかけたら?って思ったらしいんだけど、その声をあげる瞬間、急にその女が立ち上がって、無表情のままこっちに向かってきたんだって」
一瞬の判断の誤りが招くのは、一体どのような結果なのだろうか。逃げるべきか、立ちすくむべきか。その選択が命を左右することを、この世代の私たちはそんなに実感したことがなかった。
「足がすくむって、こういうことなんだろうな。まったく動けなくなってしまってさ、心臓がめちゃくちゃに鼓動したって」
斉藤の友達が感じた恐怖は、聞いただけで鮮明に伝わってくる。その場の空気が重くなり、誰もが次の言葉を待っていた。
「女が目の前まで来たとき、彼は初めて気付いたんだって。その女、足が無いんだ」
その瞬間、私たちの脳裏には、恐ろしい想像が容赦なく広がった。深夜の公園に、浮かぶように立つ女性。それは、この世のものとは思えない。
「その後は、もう記憶があやふやなんだけど、結局なんとか逃げ帰ったんだってさ。でも、その日から、何度も夢に出てくるんだとか」
彼の話が終わった後、私たちはしばらく無言で歩いた。都市伝説にすぎない、と思いたいが、どこか自身の身の危険と重なって、不安を拭いきれなかった。
その夜の話は、私たちの間でしばらく話題となったが、やがて忘れ去られ、つまらない日常に戻っていった。だが、積もりに積もった不安は、ふとした瞬間に沸き上がる。例えば、夜遅くに帰宅するとき、ふと背後を振り返る自分を感じるたびに。
人は怪談話を楽しむ生き物なのかもしれない。けれども、それが現実に起こり得る瞬間があると知ると、途端にその魅力は恐怖に変わる。そんなことを考えつつも、私は今も、夜の公園を避けるようになった。
果たして、その話が本当に友達の友達の体験だったのか。確かめようもなく、知りようもない。ただ、あの夜、斉藤が語ったその話が、私たちの心に小さな影を落としたことは確かである。そんな影はいまだに薄っすらと消えず、私の中で微かに息づいている。