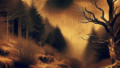ある時代、ある場所において、天地の間の境界は薄くなり、真昼でも夜の如き恐ろしき時が訪れたり。主なる神の慈愛すら、この時を隔て給えず、それゆえに人々は畏怖に震え、この神隠しの時を「静寂の哭泣」と呼び恐れたり。
その静寂の哭泣の時、村の者たちより見えぬ声が響き、何かが失われていくことを告げたり。この声を聞く者は皆、心に不可解の恐怖を抱き、身体は己の意に反して震え、何処とも分からぬ影がその存在を喉元に感じたり。声の主は人の理解を超えており、昼と夜、善と悪、光と影を分かつ神とは異なりき。
それは、目に見えぬがゆえに偉大なる存在たり。見ようと求め海を渡り、光の当たる山を越え、星の数を超えるほどの年月を費やした賢者たちですら、その存在の影すら捉えることはできず。それでもなお、人々はその存在を「蒼き嘆きの者」と呼びたり。
あるとき、この村にエリヤと呼ばれる少年が住みたり。エリヤはその好奇心旺盛なる魂により、森の奥深くにある、かつての祭司たちが恐れを抱き「帰らぬ異界」と名付けたる場所を目指す決心をしたり。その地には蒼き嘆きの者がおわすと語られ、それらの力に魅入られた者は帰還する者少なかりき。
エリヤの行路は暗夜の如く困難に満ちたり。その歩みは森の中、千々なる命の囁きと、消えゆく道の彼方に曙光を求める蝶の舞うが如し。エリヤはその心を奮い立たせ、失われたる全ての者たちの夢を携え、迷いの森の奥へと進みたり。
やがて、エリヤは時空の軋む音を聞き、深き静寂が天より降り注ぎ、彼を囲む世界が変わりたるを知りたり。その地は異界の門を潜る者のみに与えられる景色なり。それは光を失い、音も無き夢の中の如き世界たり。エリヤの耳には囁きが満ち、世界の秘密を語る神秘の言葉が広がる。
「我こそ蒼き嘆きの者なり」とその声は告げたり。「汝、求めるが故、かの地の秘密を授けん。だが汝の命、我が世界に支払われば得られざるべし」と。
彼の答えを待たずして、蒼き嘆きの者は自身の影を広げ、エリヤを包み込みたり。彼は異界の夢の中で全てが変容する感覚を覚えたり。かつて少年であった存在は影の中で再構築され、未知の叡智を抱いたる眼が新たな世界を見る能う如くに。
村へと戻りたり時、エリヤの姿は変わらざりき。然れども彼の内側、霊の深奥において何かが変わり果てたり。彼の視る世界はもはやかつての如く鮮やかならず、囁きと影の声が響く世界となりたり。帰還を歓声で迎えた村人たちは、エリヤの何かが失われし事を直感したるも、それを問うことを恐れたり。
エリヤは村に留まり、生き続けしも、彼の内なる世界は異界の残響に満たされたり。時折、彼はぼんやりと空を見上げ、その眼には語らぬ知識と理解が宿りたり。彼が見たもの、知りたるものは己に課されたる宿命を超え、未来の預言者の如き無言の教訓と為ったり。
そして人々は、エリヤが何者か知れたる者に変じたるを畏れ、彼を敬して遠ざけたり。蒼き嘆きの者は再び姿を現すことなく、然れどもその影は村にとどまり続けたり。そして、何者かの、どこぞ遠く、深き静寂より帰還する者の姿もまた、今までと違うのが村の者には感じられたり。
時代を超えて、エリヤの物語は神話として語り継がれ、彼の経験したる異界の知識は、何世代も後の神託を授かる者たちに啓示を与えたり。斯くして、人々の畏敬と恐怖は深まり続け、彼の教訓は巫女や預言者の口を通じて伝わり行きたり。かくして、蒼き嘆きの者は永遠に語り継がる者となり、彼の影は人の記憶の深奥に残り続けたり。
然れども、畏れを知らぬ者たちよ。静寂の中を彷徨う者たちよ。神隠しの時は再び訪るかもしれぬ。されば、そなたらの魂がこの異界に引き込まれることなかれと願うなり。蒼き嘆きの者の影響が未だに我らを包むことを忘れるべからず。そして、心するべし。視ることのできぬものを視る者は、帰るべき世界をすら越え、異界の新たなる住人となりぬる、多くの賢者たちが残せしる警告は、決して無視すべからず。