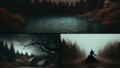その話を最初に耳にしたのは、ある雨の夜のことだった。私は友人の集まりに参加した帰り道、都心から一時間ほど離れた郊外の駅で電車を待っていた。夜のホームは冷え込みが厳しく、冷たい雨が薄暗いプラットフォームを叩いていた。誰もいない駅のベンチに腰を掛け、うっすらと霞む向かいのホームをぼんやりと眺めていると、不意に声を掛けられた。
「君もあの話、知ってる?」
声の主は、ホームの隅に身を潜めるように立っていた中年の男だった。やや薄汚れたコートを羽織り、手に持った黒ずんだ傘を手すりにもたせ掛けている。どこか陰鬱な風貌に、初めは少し身構えたが、彼の隣に座るうちに、彼は昔からこの駅で働いている職員だと言った。自分がいつもこの辺りを巡回していると話す彼は、やがてじわじわと、霧のように不気味な話を語り始めた。
それは知人の友達が体験したらしい奇妙な出来事だった。
「まあ、よくある都市伝説の類いだよ」と、彼は一笑するように言った。ただその夜、どうしてもその話を聞かせたくなったのだと語る。
物語の始まりは、知人の友達Aが、ある日突然失踪したという事件から始まる。Aは普段から明るく社交的な性格で、失踪するような兆候はなかった。彼の友人たちは、心配しながらも直ぐに彼の行方を捜し始めたという。しかし、手掛かりとなるものが一向に見つからない。ただ、Aが最後に目撃された場所は、町外れにある古びたビルの一室だった。
そのビルは、かつては賑わいを見せていたが、今ではほとんど廃墟と化している。Aがそのビルに通っていたことを知った友人たちは恐る恐る現地を訪れた。すると、周囲には得体の知れない不信感が漂っており、幾度探してもAの姿は見当たらなかった。そこで、ふと思い出したように彼らは、Aが失踪する前に頻繁に口にしていた「青い部屋」のことを思い出した。「青い部屋」とは一体何を指しているのか? まるで謎めいた呪文のように彼らの心に引っかかるその言葉の意味を、彼らはどうしても確かめたくなった。
そしてその場所を探し始めると、ビルの中で異様に青く光る一室を発見した。そこは、かつては事務所だったらしき狭い部屋で、明かり一つないのに、何故か壁が青白く光るのだ。その光は壁紙ではなく、壁そのものが放つ不気味な輝きだった。彼らは恐る恐るその部屋に足を踏み入れ、気が付くと全身に鳥肌が立つのを感じた。そこに漂う空気は異常に重く、まるで異次元に迷い込んだかのように現実感が薄れていく。
そして、部屋の中央には、奇妙な机と椅子がある。どこかから浮かび上がったようなその家具には、埃ひとつない。まるで誰かがつい先ほどまでそこで時間を過ごしていたかのような錯覚を覚える。
不意に友人たちは耳を澄ませた。聞こえてくるのは、鈍い足音。そしてかすかに響く、低く囁く声。それは、部屋のどこからともなく、青い光の中から聞こえてくる。「ここにいるよ」と、その声は言い始めた。そして、「ずっと待っていたんだ」と続けた。
友人たちは、その声の中にAのものを聞き分けてしまい、思わず動けなくなる。彼らが振り返ると、どこにもAの姿はない。ただ、部屋の片隅にある古びた鏡が、青い光を反射しながら揺れて見えた。その瞬間、彼らは背筋が凍るような感覚を覚え、ここに居てはいけないという本能的な恐怖に駆られた。
急いでその場を離れ、外に駆け出した彼らの背後で、青い部屋の扉が音もなく閉まるのを一人が振り返りながら目撃した。それからというもの、彼らは再びAの失踪を追うことを諦めた。ただただ、あの青い光の部屋のことを心の中から追い出すことで必死だったのだ。
話を終えた男は、あの部屋の謎は実は自分も知らないのだと言った。ただ、時折、そのビルを訪れる人々はその朧げな噂を耳にし、絶対にその部屋には近づかないようにと忠告されているらしい。それでもどうしても気になる人もいて、別の行方不明者が出たり、異様な体験をした者が数人いるのだと彼は力なく笑った。
その話を聞いた私はぞくっとするものを感じた。だが、駅に程近いそのビルには申し訳なさそうに街灯が灯り、雨のせいか、ほとんど人の気配がなかった。あの青い部屋とは本当に存在するのだろうか? それとも、それは単なる噂でしかないのか。曖昧なその境界にこそ、物語の怖さが潜んでいるのかもしれない。
雨が小降りになった駅を後にしながらも、私は友人たちとの帰り道、その不思議で不気味な話が頭から離れなかった。誰も確認できないからこそ、心の中でその話はいつまでもその怖さを保つのだった。