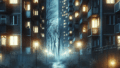深い山奥の村に、その峠を越えた先には人が誰も住んでいない廃村があるという噂が広まっていた。霧の深い夜になると、村の誰一人として踏み入れないというその場所では、夜に何かが動く姿を見た者がいるというのだ。
村の若者、蓮太郎はその噂に興味を持ち、友人たちと共に探検することを決めた。彼らは星明りも届かない厚い雲の夜を選び、懐中電灯の灯りを頼りに踏み出した。村を抜け、峠道を登る途中、蓮太郎は昔、この廃村で暮らしていたとされる老女の話を思い出していた。「何もない。ただの忘れ去られた場所さ」と言ったその言葉が、心のどこかで引っ掛かっていた。
峠を越えてしばらくすると、霧が足元を這うように立ち込め始めた。友人の一人が懐中電灯でその霧を照らすと、微かに人影のようなものが浮かび上がる。「何かいるぞ」と囁く声に、皆の息が詰まった。耳を澄ますと、確かに微かな足音が乾いた草を踏む音が霧の中から漂ってくるのだった。
その音が近づいた瞬間、蓮太郎の心は冷たく凍りついた。音の正体が何であれ、それは人間のものではないと直感的に悟ったからだ。「戻ろう」と彼は振り返った。だが、その時すでに彼らは深い霧の中に飲み込まれていた。目印になるものは何も見えず、ただ淡い光が彼らの足元を照らすばかりだった。
どれぐらい歩いただろうか。蓮太郎たちは、やがて一軒の古びた木造家屋にたどり着いた。扉は半ば開け放たれ、打ち棄てられたかつての住処からは、冷え切った空気と消えかかった生活の痕跡が漂っていた。蓮太郎は、胸に不安を抱えつつも中に入ることを選んだ。古ぼけた家具や、色褪せた写真が投げ置かれたその空間には、過ぎ去った時の影が色濃く残っていた。
友人たちと部屋を見て回ると、一つの部屋の隅に、古い日記が置かれているのを見つけた。何気なく手に取ったその日記は、廃村で暮らしていた家族の記録で、最後のページにはこう記されていた。
「ここには何かがいる。それが何なのかは誰も知らない。ただ、それは夜にだけ姿を現し、そして、私たちを見ているのだと。」
その一文を読んだ瞬間、蓮太郎たちは背後に異様な存在を感じた。振り返ると、そこには隙間風のような冷たい空気と共に、ぼんやりと揺らめく影が立っていた。濃い霧が一つの形を成したかの如きその影は、まるで蓮太郎たちをじっと見つめているかのようだった。
恐怖が彼らを動かし、廃村から逃げ出さずにはいられなかった。再び峠を目指して懸命に走る。しかし、霧はますます濃くなり、視界を閉ざし続ける。心臓の鼓動が耳を打ち、息が詰まるような絶望感が彼らを襲ってきた。
やがて、友人の一人が悲鳴を上げた。「何かが!」彼の声は恐怖で震えていた。蓮太郎が振り向くと、その友人は何か見えない力に引き寄せられるようにして霧の中に消えていった。
蓮太郎は、震える膝を抑えながら、とにかく歩みを止めなかった。不安と恐怖が交錯する中、彼はようやく見知った峠の切れ目に差し掛かった。振り返ると、霧の向こう側で、友人たちも同じように必死で進んでいる姿が見えた。
しんと静まり返った村に戻ってきたとき、彼らはようやく息をつくことができた。しかし、その心の深奥には、決して消えることのない影が刻まれていた。村の者に語ることもなく、あの霧の廃村のことを誰も聞くことはなかった。
それからというもの、蓮太郎は夜に耳鳴りがするようになった。風の音かと思うそれは、実のところ、人の話し声のようで、その一言一句が理解できるものではなかった。それはまるで、彼の心の奥深くに何かが囁いているかのようであった。
ある夜、蓮太郎は夢の中で再びあの霧の中に立っている自分を見た。手には例の日記が握られ、その文字が何度も浮かび上がる。彼は、再び訪れた恐怖の淵で、ふと本物の静けさに気づく。耳障りな囁きは消えていたのだ。
目を覚ますと、部屋の隅に何かが佇んでいる。彼が思わず声を上げようとしたその瞬間、それは風に溶けるように、音もなく消えてしまった。残されたのはわずかな冷気だけだった。
蓮太郎はしばらくの間、何事もなかったかのように日常を過ごしたが、心の奥底にはあの廃村の記憶と、姿なき影の訪れた夜のことが深く刻まれていた。誰に言うこともできず、彼はその秘密を胸に抱え続けた。
それから歳月が流れ、蓮太郎は村を離れた。遠くの街で新しい生活を始めたが、それでも時々、背筋をなでるような冷たい空気を感じることがあった。彼はもう恐れを乗り越えていたが、あの夜の霧の向こうで、何者かが彼を見ているという感覚は、決して消えることはなかった。
そして、彼はただ静かに生き続けた。あの日の霧の村で、彼が見たもの、感じたもの、それが一体何であったのかを誰も知ることはなかった。しかし、それは彼にとって、決して忘却の彼方に消え去ることのない現実の一部となったのだった。