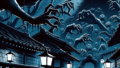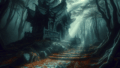霧が深く立ち込める晩秋の夜、都心から少し外れた郊外の小さな街に、一軒のカフェがあった。そこは、古い洋館を改装したおしゃれな佇まいで、昼間は賑やかに人々を迎えていたが、夜になると、誰も寄りつかない不思議な場所として知られていた。
カフェの名前は「露月」。その夜、都会の喧騒に疲れた私は、わけもなくそのカフェに足を運んでいた。店内は静まり返り、店主らしき初老の男がカウンターの向こうで微笑みを浮かべていた。彼の瞳はどこか遠くを見つめるようで、少しばかりの違和感を覚えたが、それが何なのかはわからなかった。
椅子に腰を下ろすと、店主は静かにメニューを差し出してくれた。そのメニューには、コーヒーやハーブティーといった普通の品々と共に、見慣れない奇妙な名前の飲み物がいくつかあることに気づいた。あまりにも異なる名前に、私はしばらく言葉を失ったが、何かに引き寄せられるように「月夜の影」という一杯を頼むことにした。
店主は微笑を崩さないままカウンターの奥へと消えていった。店内には、微かなピアノの旋律が流れており、その音色はどこか懐かしさを帯びていたが、やはり何かが少しずれている気がしてならなかった。時間がゆっくりと流れる中、私はその微細な不協和音に耳を澄ませていた。
しばらくして運ばれてきた「月夜の影」は、その名の通り、暗い青紫の色をしていた。カップに鼻を近づけると、香りは悪くないが、どこか胸騒ぎを覚えるような不思議なものだった。興味半分、怖さ半分で恐る恐る口に運ぶ。最初の一口は何の変哲もない、しかしどこか馴染みのない味だった。
一息つくと、不意に店内の空気が変わったように感じられた。先ほどまで棚に並んでいたアンティークの本や小物の一部が、まるで客人を見つめるようにこちらを向いている気がする。視界の端にちらつく影にとらわれながら、私は再びカウンターを見た。そこには確かに店主がいたが、その姿は前と少し違って見えた。彼の眼差しはやはりどこか遠くを見ているままだったが、その瞳の深淵には何か得体の知れないものが潜んでいた。
カフェ全体が異様な静けさに包まれている中、私の鼓動だけがやけに大きく感じられた。ほかに客はおらず、店内の時計も音を立てることなく時を刻む。突然、誰かが耳元で囁いたような気がして振り返るが、そこには人の気配はない。ただ、外の霧が窓をなめるように流れていくのが見えるだけだった。
徐々に感覚が麻痺し始め、身体が少しずつ重くなった。飲んだものが原因なのか、それともこの場所そのものに何かが潜んでいるのか分からない。ただ、そこは見えない糸が絡み合う迷宮の中、私はただ一人取り残されたようだった。何か大きな力が背後から私を静かに押し下げているようで、膝がガクガクと震え始めた。
「いかがですか?」
店主の声が突然、静寂を破って響いた。私は驚きと恐怖で声も出せずに、ただ首を縦に振るだけだった。彼は優しく微笑みながらも、その目が何も言わずにすべてを見透かしているようで、ますます胸が締め付けられるようだった。
その時、床に響く靴音に気づいた。振り返ると、いつの間にか一人の女性が店内に入ってきていた。彼女はゆっくりと私の隣に座り、静かにメニューを開く。その仕草に不自然さはなかったが、彼女の存在自体がどこか不安を誘った。何故なら、その顔立ちは、今日私がこの場所に来る理由となった遠い記憶を呼び覚ますものだったからだ。
その女性の横顔には見覚えがあった。けれども、一体どこで会ったのか、と気が付きそうでつかめない。記憶の中でぼやけている彼女の名前を思い出そうとしたが、一向に浮かばない。その不安定な記憶の欠片をつなぎ合わせようと悩むうちに、彼女は穏やかに微笑んでこちらを向き、静かに話しかけてきた。
「初めてですか?このカフェは不思議な魅力がありますよね。」
私は彼女の言葉に曖昧に頷きながら、心の中では声にならない問いを投げかけた。果たして、この場所のどこが魅力と呼べるのか。しかし、彼女の視線はどこか魅惑的で、その奥にある秘密をのぞき込むようで、私も答えを探りたくなった。
気づけば、不思議な一体感が心の中で芽生えていて、店内の異様さも、女性の存在も、全てが一つの目的に向かって進んでいるような気がした。その目的が何なのかは、自分でも全くわからない。ただ、確かなことは、一度外に出たならばすべてを忘れ去ってしまうであろう、霧のように朧げな感覚だけが残っていた。
最後に、再び店内を見渡した。棚に並ぶ古びた本、優美なカップ、そしてカフェの奥に続く廊下の影が、心の奥底に埋もれている記憶をそっと刺激した。胸につかえる不安を振り払うように、私は静かに立ち上がり、初老の店主に別れを告げた。
「またお越しください。次は違う何かが見つかるかもしれませんよ。」
彼の言葉に曖昧な微笑みで応え、私は霧の中へと足を踏み出した。背後でドアが静かに閉じる音が、まるで夢から覚める一瞬にも似た感覚を呼び起こした。カフェはまるで何事もなかったかのように、再び静寂に包まれた。
外の霧がすべてを覆い隠す中、私は今夜体験したすべてが一つの夢だったと信じたかった。しかし心の片隅に、あの違和感とその意味を知るのはまだこれからだという思いが、刃のように刺さったまま、薄明かりの街を彷徨い続けることになった。
その結末が、どのようなものであるかは、決して知ることができない予感を引きずったまま、私はなおも歩き続けた。やがてすべてが又ぼやけて消えゆく日に、本当の恐怖が私を再び訪れるのかもしれない。それまでは、霧に覆われたこの街と共に、心の奥に潜む微かな波紋を感じながら過ごすことになるだろう。