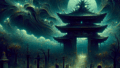闇夜の森は静寂に包まれている。月明かりが木々の間から差し込み、地面に揺れる影を落としている。まるでその影が生き物のように、暗闇の中で歪な形を作り、不気味な動きで揺らめく。それは自然の息吹ではなく、むしろ森そのものが何か恐ろしい秘密を抱えているかのようだった。
人里離れたこの山奥には、一つの古い伝説が語り継がれていた。かつては風光明媚な景色を楽しむため、多くの旅人が足を運んだこの地には、ある一家が暮らしていた。優しい妻と快活な夫、そして美しい娘だった。しかし、ある夏の日、娘が忽然と姿を消した。そしてそれ以来、この森には誰も近づかなくなった。
ある好奇心旺盛なジャーナリスト、藤村健二は、その失踪事件を追うためにこの森に足を踏み入れる決意をした。彼の興味は、娘が残した薄暗い記録によってさらに掻き立てられていた。地元の人々は黙殺したが、その記録には家族の壊れゆく過程と、狂気に陥る父親の姿が詳細に書かれていたのだ。
森の入り口に立つ藤村は、漂う静寂に神経を集中させながら進む。朽ちた小道を辿り、彼はついに噂の古い家に辿り着いた。家の扉は半ば崩れ落ち、中からはかすかに金属音が聞こえる。何かが蠢いているのだろうか。その音に引き寄せられるように、彼は深く息を吸い込み、重たい扉を押し開けた。
家の中は、異様な静けさに包まれている。埃を被った家具、壁には不気味に舞い落ちる影…。その瞬間、彼の視線は鋭い光沢に捕えられた。それは床に転がる無数の刃物だった。
手入れされた刃物は、誰かがここで何かをしていた証拠だ。藤村の心拍は徐々に速くなる。この場所が一度凶器となったことを彼は直感的に悟った。そしてその予感は正しかった。
階段を上ると、すぐに腐臭が彼を出迎えた。その悪臭は、思わず息を止めたくなるほど強烈であり、藤村は背筋に悪寒を覚えた。朽ちた扉を開くと、暗い部屋の隅に何かが蠢いているのを見た。木造のベッドの上には、血にまみれた布団に隠されている死体があった。藤村はその光景に目を背けたが、どうしても視界から消すことができなかった。
それはまさに、失踪した娘の遺体だった。彼女の柔和な顔は血に染まり、かつての平穏さはそこにはなく、残っているのはただ無残にも打ち砕かれた姿だけだった。
藤村はしばらくその場に呆然と立ち尽くしていた。彼の頭の中で何かが目まぐるしく回り出している。それは記録に残っていた狂気の父親の姿と重なり、次第に明快に明らかになる。父親は娘の失踪に深い罪悪感を感じ、その精神的重圧に耐えきれず、ついには狂気に駆られてしまったのだ。死んだ娘を愛し続けるあまり、その遺体を捨てることができなかったのだろう。
その時、不意に背後で床が軋む音がした。藤村は反射的に振り向いたが、影の中に動くものは何も見えなかった。しかし、彼は確かに何か異質な気配を感じた。耳を澄ますが、再び静寂が彼を取り囲むだけだった。
再び異様な気配を感じた藤村は、直感的にこの家を離れるべきだと悟った。この場所には、単なる狂気を超えた何かが存在するのだろう。藤村の心は恐怖に凍りついた。彼の体は、生存本能によって動かざるを得なかった。
家を飛び出し、暗い森の中を走る藤村の目には、無数の木々が嘲笑っているかのように見える。月明かりの下、彼の影は歪に揺れ、まるで彼を追いかける悪夢そのもののように見えた。
森を抜けた藤村は、ようやく人々のいる村に辿り着くことができた。しかし、彼の心は安堵することなく、むしろ新たな疑念に捕われていた。彼はこの経験を通じて、人間の狂気の深淵を覗き見てしまったのだ。
藤村は手記を書き始めることにした。その全てを記録することで、彼はかつての自分から何かを取り戻そうとした。しかし、彼の心は既に取り返しのつかない壊れ方をしていたのかもしれない。森で見た光景と、感じた狂気の残像は、彼を決して解放することはなかった。人間の狂気が生む恐怖は、決して忘れ去られることなどないのだ。