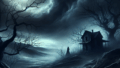私がその村を訪れたのは、秋の日が短くなり始めた頃だった。都会の喧騒を逃れ、一人で静かな時間を過ごすために計画していた旅行の一環だったが、目的地に選んだのがこの「古谷村」と呼ばれる、地図でも見つけるのが困難なほどの小さな集落だった。
この村について事前に多くを知っていたわけではなく、ただ写真で見た紅葉の美しさに魅せられたに過ぎなかった。しかし、村に到着した時に感じたのは、その紅葉の美しさとは裏腹に、何か得体の知れないものが静かに流れているという感覚だった。
村に到着して最初に目に留まったのは、その静けさだった。人一人見当たらない。唯一現れたのは年老いた女性で、私が宿を訪ねると、彼女は微かに笑みを浮かべて、村の唯一の宿を指差した。その宿に足を踏み入れたとき、古びた木の床がきしむ音が妙に心に響いた。
宿は小さな家庭旅館のようで、ご主人は物静かな中年男性だった。「あら、お客さんですか」と彼は歓迎してくれたが、その笑顔の裏には何かしらの重さを感じた。その夜、用意された夕食を済ませ、眠りに落ちかけた時、不意に遠くから聞こえる太鼓の音に目が覚めた。まるで夜の静けさを裂くような、その音は、どこか人間の心をざわつかせる何かがあった。
翌朝、村を散策していると、破れかけた石畳の道を進むうちに、古びた神社が現れた。苔むした鳥居の向こうには、朽ちかけた社が静かに佇んでいる。その周囲には、異様な数の石碑が立ち並んでいた。まるでそこに何かを封じ込めるかの如く。しかし、それ以上に不思議だったのは、村人たちがその方角を決して見ようとしないことだった。何か禁忌に触れたかのように目を伏せ、素早く通り過ぎていく。
興味を惹かれた私は、宿の主人にその神社について尋ねた。彼は少しの間黙り込んだ後、静かに口を開いた。「あそこは、昔からある村の神様を祀るところです。でも、今では誰も近づくことはありません」と言う彼の声には何かしらの恐れが含まれているかのようだった。
それ以上深く聞くことはできず、私はただますます謎めいて感じるだけだった。日が暮れると、またあの太鼓の音が聞こえ始める。夜空に響くその音は、次第に私の中で一種の不安を杓子定規に刻み始めた。
気味の悪い興味から、その音の発する方向へ足を向けた私は、村の端にある広場にたどり着いた。そこには何の変哲もない土の広場が広がり、中心には古びた大木が佇んでいた。その木には、無数の紙垂が付けられていた。まるで何かを象徴しているかのような、その光景に立ちすくむ私の元に神妙な顔をした若者が声をかけてきた。「よそ者は、ここに近づかないほうがいいですよ」と忠告する彼の声は、真剣そのものだった。
「この村には昔からの風習があるんです。村の平和を保つためのものです。だから、どうかあなたは関わらないでください」と真剣に訴える彼の瞳には、全てを語ろうとしない何かが潜んでいた。だが、それ以上に彼から伝わる未熟な悲痛さは妙に私の心を引っ掛けた。
その夜、宿に戻ると、再びあの太鼓の音が聞こえてきた。音は次第に近づき、遠くでちらつく灯りが見え始めた。村の人々が何者かを運んでいるようだった。その行列は神社に向かって進み、私は無意識に後を追うように足を進めた。
神社に到着した時、私は息をのんだ。薄闇の中で村人たちは儀式を始めようとしていた。何かを捧げるように、その中心にはあの大木が立っている。まるで長い眠りから目覚めるかの如く、畏怖に満ちた静寂が広がる。
そして、村長と思しき老人が、何か古い言葉を唱え始めた。背筋が凍るような恐ろしいくらいの沈黙。やがて、彼が持つ杖がかざされ、太鼓の音が一際大きくなった。まるでその場に空気が振動するような感覚。そして――
何かが動いた。それは、樹の根から顕(あらわ)れたかのようだった。あの静かな夜の中で、ぎしぎしと軋むような音と共に何かが這いずり出てくる。それが何なのか、知覚した瞬間に私の心は凍りついた。
それは、人の形をした何かの影。木の魔物とでも呼べそうな、それが満月の明かりに照らされ、村人たちの唯一の希望であるかのようだったが、私にはそれはまったくの異質、それ以上に恐怖の象徴に思えるだけだった。
震えるような恐怖に駆られ、私はその場から逃げ出した。気がつけば、村人たちもそれに追随するかの如く、私を追いかけてきた。息も絶え絶えに走り抜けた先で、日の出を迎え私は唯一の観光客用のバスに駆け込み、村を後にした。
古谷村を出てから、あの静かな悪夢から覚めるようだった。宿で体験した出来事、神社で見た儀式の光景が、私の中で一つの恐ろしい現実として刻まれていたが、それを証明する術は何一つない。ただあの村が確かに存在するという事実だけが、次第に薄れゆくそれらの記憶を現実に留めていた。
都会に戻ってから、私は何度も夢にあの夜の情景を見た。あの村の風習、村人たちが何を守ろうとしていたのか。いまだにその答えは知る由もないが、あの村で見た全ての光景は、私の心を二度と戻れぬ世界へと閉じ込めたままなのである。とどのつまり、あの村には帰れない。それが今でも私に囁く無言の約束だ。