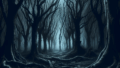ある夏の終わり、私は友人の亮介と共に、長野県の奥深い山村に向かった。そこは人里離れた静かな場所で、夜になると街灯すらない暗闇が辺りを包み込む。私たちの目的は、古い寺社仏閣を巡ることで、風情のある秋の景色を楽しむことだった。しかし、心のどこかで未知の恐怖が私たちを待ち構えているとは、このとき夢にも思わなかった。
私たちが訪れた村は、地元の伝説や妖怪話が残る場所として有名だった。村人たちは口々に、「注意しなさいよ」と諭すように言った。「夜、山には近づくな。何かがいる」と。私たちはその言葉を笑い話として受け流したが、内心では何か不吉な予感がしていた。
一日の観光を終え、私たちは村のはずれにある古びた旅館に泊まることにした。旅館の女将は高齢の女性で、私たちが泊まる部屋に案内しながら、「この部屋には昔から色々な噂があるんですよ」と曖昧な笑みを浮かべて言った。部屋自体は普通の和室で、特に変わったところはなかったが、その言葉が妙に引っかかった。
夜中、私はなぜか目が覚めた。時計を見ると午前二時過ぎで、亮介の寝息だけが静寂を破る。外は虫の声も聞こえないほど静まり返り、不気味なほどに暗い。私は再び眠りにつこうとしたが、どこからか微かに声が聞こえる。男とも女ともつかない、小さな囁き声だった。
最初は自分の気のせいかと思った。しかし、その囁き声は次第に大きくなり、部屋の中を漂い始めた。私は恐怖に駆られ、隣で寝ている亮介を起こそうとしたが、そのとき、畳の上に座る何者かの影が見えた。月明かりに照らされて、はっきりと人の形をしていたが、やはりどうしてもその声の持ち主の姿を確認することができなかった。
そのときだ。その影が不意に動き、私の方に向き直った。顔のないその姿は、見てはいけない何かを見てしまったという恐怖を一瞬で私に植え付けた。私は声を出そうとしたが、その影は指を唇に当てて「静かに」と言っているように見えた。私は背筋に冷たいものを感じ、何とか亮介を揺すり起こしたが、彼は一向に目を覚まさない。
私は思い切って立ち上がり、影の正体を確かめようとしたが、影は突然スッと消えた。現実のものとは思えない光景に、私はただ立ち尽くすしかなかった。翌日、旅館の女将にその出来事を話すと、彼女は目を細めて静かにうなずいた。
「この村では昔からいますよ」と、彼女は言った。「あれは『影の主』。夜になると現れ、迷った魂を導くんです」。私は戦慄したが、同時に妙な納得感を覚えた。亮介もこの話を聞き、冗談半分に「いい経験になったよ」と言った。
その日は何事もなく過ぎ、私たちは翌朝、村を発つことにしたが、不思議な感覚は消えなかった。村を後にする車中から、さりげなく振り返ると、遠くの山の中で何かがこちらを見ているような気がした。
それからというもの、私はそれを思い出すたびに背筋が寒くなる。もしももう一度この村を訪れることがあるなら、私はもう少し彼らの言葉に耳を傾けるだろう。そして、もし再び『影の主』に会うことがあるなら、彼の告げる静寂の意味を理解する自信がない。