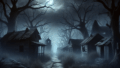暗い秋の夕暮れ、葉が舞い落ちる音すら静寂を破ることを躊躇うかのような、静まり返った小さな町に、彼女の不安の種は芽吹き始めた。彼女の名は鈴木美咲、端整な顔立ちを持ちながら、心には常に影を宿していた。
美咲はこの町の古くからの住人であったが、何者にも負けない孤独を心に抱えていた。仕事は地元の図書館司書、日々、本の中に逃避し、現実の喧騒から自分を守る生活を送っていた。しかし、最近、彼女の中で何かが変わり始めた。心の中で、不可解な声が囁き始め、現実がまるで砂上の楼閣のように崩れ去る感覚を覚えるのだった。
彼女が勤める図書館は、町の外れにひっそりと佇む古びた建物であった。高い天井と古時計の響きが、訪れる者にどこか別世界のような錯覚を与えていた。美咲はそこで過ごす時間を愛したが、次第にその場所ですら居心地の悪さを感じるようになっていた。棚に並ぶ本の背表紙が、何か意味ありげなメッセージを形作ろうとしているかのように思えたのだ。
特に、一冊の古びた日記が彼女の目を離さなかった。それは誰の手によるものかわからないが、強烈な不安と狂気に満ちた文章が並び、読み進めるうちに明らかに執筆者の精神が崩壊していく様が見て取れた。「彼らがやってくる」「逃げられない」という言葉がリフレインのように何度も登場し、美咲の心に深い影を落とした。
その日から、美咲の生活の中で何かが狂い始めた。夜、夢の中で訪れる町は現実のそれと似て非なる場所へと変貌し、そこには奇妙な影たちが彷徨っていた。彼彼らは無声映画の登場人物のように動き、何かを訴えようとしているようであったが、美咲にはその意味がわからなかった。しかし、その夢の不気味さは現実にも侵食してきた。
日中、図書館の中で仕事をしていると、突然誰かに見られている視線を感じる。振り返っても人影はない。ただ棚の間から、何故か彼女を嘲笑うかのようなささやきが聞こえる。「お前もすぐに分かる、お前も彼の仲間になるのだ」と。その声は徐々に大きくなり、図書館内のあらゆるものに反響するように広がっていく。
彼女は次第に幻聴に苛まれるようになった。町の人々が日常の会話の中で、彼女のことを話している、彼女の狂気を笑っている、そんな錯覚を覚えるようになった。美咲の精神はどんどんと削られ、彼女は次第に人とも接触せず、図書館でひたすら本を読み漁るだけの日々に戻っていった。
ある日、美咲は不気味な誘導に導かれるようにして、いつもとは違う棚の裏側、一枚の古びたドアを見つけた。それまで見たこともないその扉には、何故か「彼方への道」という奇妙な文字が彫られていた。心に芽生えた恐怖を振り払おうとして扉を開くと、そこには一面に広がる闇が、彼女を飲み込むように待ち構えていた。
その佇まいに、彼女の背筋には冷たいものが走り去ったが、まるで引力に逆らえないかのように、その暗闇の中に一歩一歩、足を進めていった。その先に何があるのかという不安、心臓の奥から溢れ出す妙な興奮が、彼女をその闇へと誘った。
やがて、美咲は少しずつ現実の輪郭を失い、どれが本物の世界でどれが幻影なのか、その区別すらつかなくなっていった。かつて心を支えていた本の世界は、今や彼女をねじ伏せ、恐怖と狂気の檻へと閉じ込めるための道具になり下がっていた。彼女の目はもう、人間の言葉を意味することをやめ、ただその無数の文字と線の奔流の中を流されていくだけの存在と化していた。
美咲はついに自分自身の内側にある狂気と向き合うこととなった。自らの理性を手放し、虚実の軌跡を辿る旅路に没入するしか道はなかった。彼女の耳にはあの囁きが再び聞こえてきた。「お前はもう帰れない、そして帰りたいものだとしても、そこにはもう何も残っていないのだ」と。
美咲は閉じかけたそのドアの向こう側、際限のない夢の中を一人歩いていた。彼女の目には、全ての現実が今や一片の幻影となり果て、不確かな世界の住人となった自らにさえ、わずかな哀れみすら抱けなくなっていた。おそらく、彼女は再び光を目にすることはないだろうと誰しもが思うが、美咲にとってそれが恐ろしき事実でさえも、今やどうでもよいことになってしまっていた。
彼女の心は、もはや一本の糸でしか繋がれていないかのように、いずれその糸さえも風に揺れ、朽ち果ててしまうのだと——ただ、時間だけが知っている。