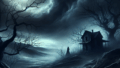僕の名前はユウタ。どこにでもいる平凡な大学生だ。普通の生活を送っていたはずなのに、ある日突然、僕の人生は予想もしない方向へと転がり出した。
始まりは些細なことだった。大学の講義が終わり、SNSを眺めていると、フォロワーの数が一人増えていることに気づいた。そのアカウントは「ミドリ」という名前で、プロフィール写真にはどこかで見たことのある風景が写っていた。最初は特に気にも止めず、リフォローした。
それから数週間、ミドリは毎日のように僕の投稿にいいねを押してくれたり、コメントをしてきたりした。彼女のコメントはいつもポジティブで、「今日は頑張ったんだね」や「素敵な景色だね」といったものが多かった。それだけならただの優しいフォロワーだが、次第に彼女のコメントには奇妙な違和感を覚えるようになった。
ある日のことだ。僕が大学のカフェテリアで友人と談笑している写真を投稿すると、ミドリは「その赤いシャツ、似合ってるよ」とコメントしてきた。投稿した写真には僕のシャツの色がわかるような情報はなかったため、些細なことながら気にかかるようになった。しかし、僕は深く考えず、適当に「ありがとう」と返事をした。
だが、その後も彼女のコメントは続いた。あるときは「今日は3限の講義が面白かったね」とか、「駅前の新しいカフェに行ったんでしょ?」などと、明らかに僕のプライベートを知っているかのような内容が増えてきた。
さすがに気味が悪くなり、友人に相談したが「ただのネットストーカーだろ、ブロックしちゃえよ」と軽くあしらわれた。でも、僕はその時すでにミドリの存在がどこか現実味を帯び始めていると感じていたので、無視できなかった。
その夜、寝る前にSNSを見ていると、ミドリからDMが来ていた。「今夜、よく眠れるといいね。夢の中で会えるかも」。そのメッセージを読んで、背筋に冷たいものが走った。なぜこの人が僕が今まさに布団に入ったことを知っているのか。
もう我慢できず、ミドリのアカウントをブロックしようとした瞬間、僕のスマホに通知が入った。それは「位置情報の共有を開始しました」というものだった。自分がそんな設定をした覚えはない。すぐに確認すると、ミドリに対して位置情報が共有されていることが判明した。
一体どうやってこんなことが起きたのかさっぱりわからず、とりあえず共有を解除し、アカウントを非公開にした。翌日、警察に相談しようと思ったのだが、何一つ具体的な証拠がないし、相談したところで「その程度」とあしらわれる気がして気が乗らなかった。
それからしばらく、ミドリのアカウントは動かなかった。しかし、少し経つと、状況はさらにエスカレートしていった。ある日、大学の最寄り駅に向かう途中、見知らぬ女性が僕の隣に座ってきた。彼女は何も言わず、ただ微笑んで僕を見ていた。そして、ふいに「今日はこのシャツを選んだんだね」と言われた。驚いて彼女を見やると、彼女は「あ、気を悪くさせちゃったかな?」と、どこか申し訳なさそうにしていた。
逃げるようにその場を離れた僕は、すぐに友人に電話をかけ、事情を話した。友人は笑い飛ばすかと思ったが、「それはさすがにやばいな、一緒に警察行こう」と言ってくれた。
その夜、警察署で事情を話すと、担当の警官は意外と真剣に聞いてくれた。僕が今までに遭遇したことを全て話し終えると、彼は「最近増えている手口だ。SNSや個人情報の管理にはもっと気をつけた方がいい」とアドバイスしてくれた。そして、万が一のため、連絡先を交換し、これから何かあればすぐに知らせるようにと言われた。
そうして、一旦の安心を得たはずだった。だが、次の日、思わぬ形でミドリの存在を感じることになった。郵便受けに手紙が一通入っていたのだ。それは手書きのもので、「あなたのこと、全部知ってる。これからもずっと応援しています」と書かれていた。シンプルな文面だが、これ以上の恐怖はないと思った。
もう限界だった。急いで警察に連絡を入れ、すぐにでも彼女が接触してこないよう対応してもらいたかったが、警察は「具体的な危害が加えられない限り動けない」と言われてしまった。仕方なくアカウントを完全に削除し、ネットから距離を置かざるを得なかった。
その後、特に大きな問題もなく、日常に戻りつつあった僕だったが、心のどこかで彼女の存在を感じずにはいられなかった。まるで影のように、隙間からこちらをじっと見つめているような感覚が、常に付きまとっていた。そしていつの日か、あの風景写真がどこで撮られたものか理解することになった。そこは、自宅から歩いてほんの数分の公園だったのだ。
僕がこれまで安全だと思っていたすべての場所と、無意識にシェアしていた情報が、知らない相手に利用され、危うい状況を引き起こしていたのだと思い知らされた。普段の生活に潜む恐怖。それは、誰の身にも降りかかる可能性があると感じた出来事だった。今、僕はSNSもやらず、情報を発信することをほとんどやめてしまった。
けれど、まだ時折、ふとした瞬間に感じる。誰かが、どこかから、僕を見ているのではないかという不安を…。