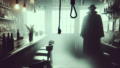僕がその研究所に入り込むことになったのは、科学に対する純粋な好奇心と、人が禁じられた領域に踏み込む瞬間に立ち会いたいという欲望からだった。研究所のことは、内部の人間しか知らないはずだったが、ある夜、偶然に耳にした友人の噂話が全ての始まりだった。
彼はうわ言のように、「人を超える何かを作っている」とだけ言った。興味をそそられた僕は、友人を問い詰め、その場所へ潜り込む方法を探った。結局、研究所でアルバイトをしているという友人の好意で、一晩だけ見学させてもらうことになった。
内部は想像以上に広く、無機質な雰囲気に満ちていた。廊下を歩くたびに、心臓の鼓動が鼓膜を打ち、緊張感が身体を締め付けた。僕は一枚一枚の扉の奥に何があるのか、想像するだけで身震いを覚えた。
友人は僕を手招きし、特に注意を引くドアの前に立ち止まった。「ここが、噂の研究室だ。」彼は慎重に周りを見渡し、誰にも見られていないことを確認すると、カードキーを使ってそのドアを開けた。扉が開いた瞬間、僕の鼻を刺激する薬品の匂いが漂ってきた。そして、その光景を目の当たりにして、今でもあの時の背筋が凍る感覚を忘れられない。
広い部屋の中央には、一台の手術台のようなものがあり、その上に人が横たわっていた。いや、正確には元人間と表現すべきだろう。皮膚は不自然なほどに白く、透明感があり、血管が透けて見えるほどだった。その体躯が微動だにしないことに異様さを感じ、僕は言葉を失った。
その時、白衣の男がこちらに気づき、僕に歩み寄ってきた。彼の瞳はどこか虚ろで、常軌を逸した狂気が潜んでいるようだった。「君は何を見た?」彼の問いかけに、僕は言葉につまり、ただ頭を振った。しかし男は不敵な笑みを浮かべ、「まあいい。どうせすぐに分かることだ。」と言って奥の部屋へと消えていった。
その後、友人は僕を外に連れ出した。彼の顔は蒼白で、声も震えていた。「知らなかった。あんなことが行われているなんて。」そんな彼の言葉を聞きながら、僕の心には恐怖と好奇心の入り混じった感情が渦巻いていた。
数日後、僕の体に異変が起き始めた。肌に痒みが走り、やがてそれは激しい痛みへと変わっていった。最初は些細な変化だと思っていたが、次第に身体全体に広がっていく感覚に焦り始めた。鏡の前に立つと、そこには明らかに異常な色を帯びた自分の姿があった。
皮膚は白く変色し、毛細血管が浮き出てきた。それに加えて、目の奥に何か熱いものが渦巻いている感覚があり、視界が時々赤く染まることもあった。恐慌に駆られ、僕は再びあの研究所に走った。友人に連絡を取ることはできず、あの白衣の男に説明を求めるしかなかった。
研究所のドアは容易に開いた。まるで僕を待ち受けていたかのようだった。中に入ると、あの男が姿を現し、不敵な笑みを浮かべていた。「ようこそ、人間であることの限界を超えた世界へ。」無意識に後退する僕を見て、彼は狂気の眼差しで僕を捉えた。「実験は成功だ。君の体は適応を始めている。」
その言葉の意味を理解する前に、体中に激しい痛みが走った。膝から崩れ落ちる僕を見下ろしながら、彼は楽しげに笑った。「君には特別な処置を施した。君の身体は、新たな段階に進むための貴重な試作品だ。」
その後のことは、断片的にしか覚えていない。意識が朦朧とする中、何度も手術台に乗せられ、ミキシングされた薬品が注入された。気がつけば、体は透明に近く、内側から輝くような状態になっていた。痛みや感覚が薄れていく中で、僕は次第に人間としての自分を見失っていった。
ある日、目が覚めると僕の周りには誰もいなかった。研究所の設備は動かず、辺りは静寂に包まれていた。何が起こったのかは分からない。ただ、僕は自由を得たのかもしれない。僕はそこを歩き去った。そして今、こうしてその経験を語っている。しかし、自分がどれほど変わってしまったかを述べるのは恐ろしい。果たして、僕はまだ人間と呼べるのだろうか。肌はまだ白く、血管は青く脈を打っている。そして、時折視界が赤く染まる瞬間、僕はあの男の笑い声を思い出さずにはいられない。
禁断の実験と、倫理を超えた科学の果てに僕が見たものは、人間の姿をした未知のものだったのかもしれない。この話を聞いたあなたが、その後何を見るかは…分からない。それでも、一つだけ忠告しておこう。決して、踏み入れてはいけない領域があるということを。科学がすべてを解決するわけではないことを知ってほしい。
そして僕は、今もその変化が終わらない身体と共に生き続け、いつか完全に自分を見失う日が来るのではないかという恐怖と共に暮らしている。倫理を超えた科学とは、決して触れるべきではない恐ろしいものだと痛感したあの日から、僕の心には決して消えない影が差しているのだ。