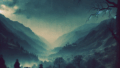丘の上に古ぼけた神社があった。町から少し離れたその場所は、地元の人々の間で「触れてはならない聖域」として語り継がれていた。何世代にもわたる禁忌が、その存在を謎に包み込んでいた。霧がかった早朝、圧倒的な静けさの中、霊場の薄暗い道を歩くと、遠くから風鈴のか細い音が響いてくる。木々の葉擦れが、まるでこの世ならぬ者たちの囁き声のようで、背筋に冷たいものが走る。
信仰を捨てたわけではなかったが、都市化の波に飲み込まれつつあるこの時代に、深く信心深い者は少なくなっていた。だが、ある年の秋、都会からとある若者、翔太がこの町に引っ越してきた。翔太は町外れの静謐さに心奪われ、週に一度は神社の境内へ足を運ぶようになった。彼にとってそこは、現実の喧騒から逃れるための穏やかで神秘的な避難所だった。
が、そこにはただならぬ噂があった。村の長老たちは、古い伝承を語り継いでいた。神社を護る松の大木には、かつてそこに祭られていた神が、祟りの形でその姿を現すと。神を冒涜する者には恐ろしい罰が下るとされ、皆、恐れ敬っていた。
それでも秋の夕暮れ時、翔太は一種の好奇心と、信じがたき無神経さに導かれ、いつものようにその神社を訪れた。彼は境内の片隅で、信仰心の象徴であった石灯籠をそっと撫でてみた。不意に指先が氷のように冷たくなり、その瞬間、彼は何かが変わるのを感じた。
その夜、翔太は不思議な夢を見た。夢の中で彼は、薄青い霧に包まれた神社の境内に立っていた。声がした。それは、幾重にも重なる耳障りな囁きだった。彼の名前を呼ぶそれは、どこからともなく響き渡っていた。そして、声の主に導かれるように、彼は神社の奥へと進んでいった。そこには大木があり、その根元には未見の扉が開かれていた。翔太は迷わずその中に入っていった。
翌朝、目を覚ますと、夢の内容はなぜか鮮明には思い出せなかった。ただ、心の内に不安と焦燥が渦巻き、いたたまれない気持ちになった。何かに急き立てられるように、再び神社へと向かうと、静寂の中で語りえぬ恐怖を覚えた。
その日、犬の散歩中の老人が、翔太の様子がおかしいことに気づいた。彼の瞳は虚ろで、まるでこの世の物ではないものを見ているようだった。老人はそのことを村の人々に話したが、誰も勇気を持って神社へ足を運ぶ者はいなかった。
時は過ぎ、秋が深まるにつれ、翔太は次第に言葉数が減っていった。彼は霊場を訪れるたび、何かに縛られているような感覚に侵され、体から力が抜けていった。それはどこか浄化というよりも消耗に近かった。
ある晩、再びあの不思議な夢を見た翔太は、夢の中で扉の向こうの薄闇に、何かが動いているのを感じた。それはいつしか姿を形作ることなく、ただ、冷淡に彼を見つめていた。目を覚ますと、その存在は現実にも付きまとっているかのようだった。
ついにある日、神社の境内で彼は突然倒れた。緊急で駆けつけた村人たちは、その場で奇妙な物を目にした。翔太の周囲には、見えない何かの力によってか、冬のような白い霧が立ち込めていた。それは彼一人を冷たく包み込み、彼の体温を吸い取っているかのようだった。
町の長老が連れてこられ、祈祷が始まった。祝詞の声が響き渡る中、翔太の唇はなにか呟いていた。長老たちは恐怖と戦いながら、祈りを盛んに捧げ続けた。
やがて霧は晴れ、翔太は意識を取り戻した。しかし、彼の心はすでに深く傷つき、一瞬も平穏を得ることはなかった。彼の背後に何かの影がつきまとい、消えることはなかった。それは恐らく、触れてはならない聖域に足を踏み入れた罰の重みであったのかもしれない。
その後、翔太は町を去ったが、霊場を訪れることは決してなかった。村人たちは口伝えに、この出来事を子供たちに教え続けた。神秘と恐怖が入り混じるこの神社の伝説は、今もなお、静寂の中で息づいている。誰も触れようとしないその場所は、やがて再び霧に包まれ、時の流れの中へと静かに消えていった。