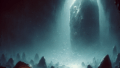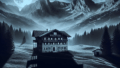その村の名は、忘れ去られた者たちの間でひっそりと語られる。かつてその地を訪れ、命を失った者の魂は、夜空を彷徨いながらこの世を離れられずにいるという。村は山あいに隠れ、日の光はほとんど届かない。密林のごとき森がその境界をなしており、訪れた者たちを迷わせる。神聖なる禁忌に触れる者に対する警告として、風に乗って囁く声があるという。
ある日、都会から一人の若者がこの地へと足を踏み入れた。彼は学校で民族学を専攻しており、卒業論文の研究材料を求めて村々を巡っていた。伝承と信仰、そして人々の生活がどのように結びついているかを知りたかったのだ。だが彼は知っていたがゆえに悟ってはいなかった。ここはただの村ではない。ここは、神々と人間が交わる禁忌の地であるということを。
村に辿り着くと、若者はまず村の中心に佇む古びた教会を訪れた。それは神殿のような役割を果たし、この地の掟を決する場所であった。教会の扉を越えると、中には古代の神々を祀る巨大な彫像が並んでいた。恐れ多いその姿を見た瞬間、若者の心には不安が影を落とす。しかし、その不安は好奇心によってすぐに掻き消され、一心不乱にメモを取り出しては、その詳細を写し取る。
村の者たちは無言で姿を見せ、その目には異界に対する畏怖と敬意が宿っていた。そして、若者が教会を後にしてすぐ、村の長老が現れた。彼は年老いているが、目の奥には古えの知識を宿していた。「ここは神聖な地。君のような若者が簡単に踏み入れるべきところではない」と、長老は静かに語った。
しかし若者は聞く耳を持たず、自らの興味が優先された。翌朝も早くから村を巡り、各家屋を訪ねては人々に問いかけ、伝説や風習を記録した。しかし、誰もが語らない、一つの共通する忌まわしい話があった。それが、この村に代々続く「夜の祭り」である。その祭りの夜、人々は一時的にこの世を離れ、彼岸の者たちと交わるとされていた。
長老は、「夜になれば、決して外に出てはならぬ」と強く戒めた。しかし、その夜、若者の好奇心は抑えがたく、彼は霧に包まれた村の中をふらふらとさまよった。やがて、古い橋の上で若者は奇怪な光景を目の当たりにする。霧が晴れると、異形の者たちが列をなして歩いているではないか。彼らの顔はどこか人間離れしており、それでいて妙に親しみを覚える特徴を帯びていた。
一方で、この村に伝わる神話に、彼がすでにその存在の一部になっていることに、若者は気づいていなかったのである。それは、時を超え、神々の望みを叶えるために選ばれた者の運命。彼はその運命を逃れる術を知らず、再び現れる夜の祭りにおいて、選ばれし者としての儀式を強制されることとなる。
夜の帳が降りた時、村は異界と化した。目に見える全てが現実を越え、無限の時をさまよう。若者はその流れに引き込まれ、やがて意識を失った。目が覚めた時、彼は村の広場に横たわっていた。周囲を見回すと、村人たちが彼を取り囲んでいる。誰一人として言葉を発する者はおらず、夜風が冷たく吹き抜ける中、ただ静かに彼を見下ろしていた。
心を蝕む恐怖は、無言の中で次第に形を成していく。若者は理解した。自らが神々の喰い物にされ、今や言葉では語れぬ存在に変わりつつあることを。やがて彼は、村の神話に新たな一章を刻む存在となり、夜ごとに彼岸を巡る義務を課されたのだ。
その後、若者の行方を知る者は誰もいない。彼の記録も、また一つの消された歴史として、山奥に眠っているのかもしれない。風が囁き、木々がざわめくたび、村はその静寂と共に、彼の魂を永遠に縛りつけ続けるのである。
こうして、新たな神話が生まれた。村の名も、そこに暮らす者たちも、やがて忘れ去られる時が来ようとも、その地を訪れ、夜の祭りを目にした者がいる限り、神話は生き続けるのだろう。それが、人智を超えた存在への敬意と恐怖が刻みつけられた、呪われし村の宿命である。