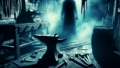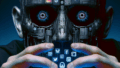村を外れた山奥に、かつて不気味な廃寺が佇んでいた。その場所は、地元の人々の間では「御止寺」と呼ばれ、誰も近づくことを憚る聖域と化していた。御止寺は、時間の経過とともに荒れ果てたが、その地には今もなお、何か得体の知れない力が宿っているかのようであった。
その地を踏み入れた者たちの間で囁かれる逸話は数多く存在した。その寺に一度でも足を踏み入れた者は、何人も戻らなかったか、あるいは戻ってきても正気を失ってしまったというのだ。その原因を突き止めることは誰もできず、ただ言われのない恐怖が村中に広まっていくばかりだった。
ある年のこと、都会から一人の青年が村にやってきた。名前を高橋修二といい、彼の目的はその御止寺の謎を暴くことにあった。彼はジャーナリストであり、『禁忌』をテーマにした記事を求めて全国を巡っていた。村人たちは彼に警告をしたが、修二の好奇心は止むことを知らなかった。
“どんな秘密が隠されているにせよ、それをこの目で確かめたい。”修二はそう思っていた。
秋の陽が傾き始めた頃、修二は意を決して御止寺へと向かった。道中の山道は険しく、彼を嘲笑うかのように影が次第に長くなっていった。そして、木々の合間を縫うようにして現れた寺の姿は、黄昏時の柔らかな光に浮かび上がり、まるで異界への門が開かれたかのようであった。
寺の境内に一歩足を踏み入れた途端、彼の全身を寒気が駆け巡った。風は一切吹いていないのに、何故か彼の身体は凍えるような冷たさを感じたのだ。修二は少し戸惑いながらも、その冷気を振り払うため、自らを奮い立たせた。
――何も恐れることはない。
そう自分自身に言い聞かせながら、彼は寺の中心へと歩みを進めた。主堂の前に立つと、彼の鼓動は高鳴った。苔むした石段が続くその堂は、年月を重ねて不気味なまでの静けさを漂わせていた。
堂の扉を押し開けると、内部は朽ち果てた柱や崩れ落ちた屋根から射し込む一筋の光に照らされて、いっそう深い陰翳を帯びていた。その光景に修二の背筋は自然とピンと伸び、何か見えざるものに見守られているような錯覚を覚えた。
更に一歩を踏み出したその時だった。彼は、息を詰まらせるような不自然な静寂を感じた。耳を澄ましても、風の音や動物の鳴き声すら聞こえない。完全な静寂が境内を包み込んでいた。
突然、背後から軽やかな鈴の音が響いた。振り向いても、そこには誰もいない。なのに、その鈴音は確かに彼の心を捕らえて離さなかった。
“これは……?”
自然な反射で、修二は辺りを見渡した。彼の視線が境内の奥に据えられた小さな祠に引き寄せられた。その祠の中から、鈴の音が再び響く。修二は、未踏の領域への欲望に駆られて、祠へと歩み寄った。
祠内部は薄暗く、そこで彼は古びた鈴と共に置かれた数枚の破れた絵馬を見つけた。その絵馬には、整然と文字が並んでいたが、それは忌むべき過去を物語っていた。
それを手にすると、彼は思わず声を漏らしてしまった。
“これは……いったい……”
紙に書かれていたのは、村人たちの無念と呪詛の呪文であった。この廃寺がどのようにして聖域として人々を遠ざけてきたのか、その理由がそこには刻まれていた。どうやら、かつてこの地で不可解な儀式が行われ、それが原因で多くの命が失われたらしい。その無念が今もこの地に留まり、訪れる者に警告を与えていたのだ。
修二はその事実に寒気を覚えた。その一瞬、自分の周囲の空気が変わるのを感じた。不気味な冷気が彼を包み込み、身動きが取れなくなってしまった。まるで何者かにじっと見つめられているような感覚が、彼の心を締め付けた。
その時、微かに人の気配を感じた。振り向くと、そこには誰かが立っている。しかし、その姿は彼の目にはぼんやりとしか映らず、まるでそこに存在しないかのようでもあった。だが、その影のようなものは確かに修二を見つめていた。
背後から鈴の音が再び響き渡り、彼はその音に導かれるようにして自然に後退りしてしまった。闇が彼の視界を奪い、その中に溶け込んでいく修二の意識はだんだんと薄れていった。
気がつくと、修二は廃寺の外に立っていた。あたりはもうすっかり夜に包まれている。どうやってそこから出てきたのか、彼には記憶がなかった。ただ、一つだけはっきりしていることがあった。それは、あの廃寺に今もなお、何かが住まい、訪ねる者を拒んでいるという事実である。
修二は誰もが恐れるこの聖域からの帰路についた。村に戻った彼は、この出来事を文章に残すことを決意した。しかし、それを書くにつれて、彼の心は次第に苛まれるような思いに駆られていった。
――何故、あの時振り返ってしまったのか。
それは誰にも答えの出ない問いである。しかし、修二はその問いに苛まれ続けることとなる。あの鈴の音が、今でも彼の耳に鳴り響くたび、もう二度とこの村を訪れることはないだろうと思うのだった。
御止寺の謎は、今もなお深まるばかり。人々の心にその恐怖は根付いたままであり、伝説はこうして語り継がれていくのだった。禁忌に触れてしまった者たちへの警告として、そして、忘れてはならない教訓として、終わりなき物語は続いている。