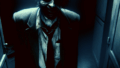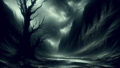その日はまるで何事もないかのように始まった。朝の光が柔らかくカーテンを透けるリビングに差し込み、いつものように俺は新聞を広げた。キッチンではコーヒーメーカーが小さな音を立てている。それは毎朝のささやかな儀式のようなものだった。けれど、その日の静けさの中に、微かな違和感が紛れていたのに気づくべきだったのかもしれない。
最初の異変は、小さなことだった。駅へ向かう道すがら、毎日同じ場所で顔を合わせるパン屋の店主が、「おはようございます」と言わず、ただ静かに微笑んだ。まるで俺を知っているかのように。そして、彼の後ろには見慣れた風景が広がっていたが、どこかしら形が歪んで見えた。普段は気にならない電柱が僅かに傾いているように感じた。その些細な違和感を振り払おうと、俺は足早に駅に向かった。
列車に乗ると、いつもは満席のはずの車内が、なぜか異常に空いていた。まばらに座る乗客たちの顔は、どれも無表情であった。そして、誰一人として携帯や本を手にしていないことに気づいた。車窓を流れる景色の中に、見慣れぬ建物がひとつ混ざっていたことに気がついたのは、車掌のアナウンスが響く頃だった。
オフィスに着くと、日常は一見、何事もなく過ぎていった。同僚たちの声や電話の音、キーボードを叩く音、全てが普段と変わらぬ様子を装っていた。しかし、その日の会議の最中、誰もが持つ資料のジェンダーに、なぜか異なるページ番号が振られていることに気づいた。上司に尋ねても、彼はいつもの厳しい口調で、「そんなことはない」と一蹴した。その言葉には何か奇妙な響きがあって、まるで録音された音声が流れているようだった。
昼休みに外に出ると、街全体がどこかしら見知らぬ場所に変わっていることに気づいた。並ぶ店舗の看板が一つ変わり、見慣れたカフェが別の飲食店に変わっていた。通りを歩く人々の顔が朦朧とした一瞬に見えたのは、俺の目の錯覚かもしれない。あるいは、本当に彼らは少しずつ別のものに置き換わっているのだろうか。
その夜、家に帰ると、背後に何者かの気配を感じた。振り返ると通りには誰もいなかった。それでも、影は不自然に闇の中にじっと潜んでいるようで、俺は早足になった。家に入ると、安心感が胸の中に広がるはずだったが、家具の配置が微妙に変わっていることに気づいた。今までずっとそこにあったはずの観葉植物が、廊下の角に無造作に置かれている。
夜が更けるにつれて、違和感は確固たる恐怖へと姿を変えていった。ベッドに潜り込んだ瞬間、いつもと同じシーツのプレスされた感触が肌に触れず、代わりに冷たい何かが身体中にまとわりつくようだった。眠ろうとしても、頭の中で何者かが囁いているような感覚が襲い、夢の中でさえも、日常が崩れ去る音が耳にこびりついた。
翌朝、目覚めると、すべてが一新されていた。階下へ降りると、家族の姿が嘘のようにそこにあったが、彼らの瞳はどこか空洞で、俺をまるで通り越して見ているかのようだった。新聞の文字が読めない記号に変わっており、テレビから流れるニュースキャスターの声がぐにゃぐにゃと耳に残り、正体不明の言葉を囁き続ける。
究極の崩壊が訪れたのはその日、仕事からの帰り道だった。電車が普段とは違う駅に止まり、車内に不意に現れた乗務員が、どこか異次元の者のように笑みを浮かべた瞬間、俺は全てを悟ったのかもしれない。世界は、日常という彼方の向こうで、緩やかに螺旋を描きながら崩れ落ちているのだ。
その瞬間、無数の目が周囲の闇から飛び出し、俺を見据えた。知らぬ何かが手を伸ばし、俺の感覚を一つずつ奪っていく。気がつけば、俺は見知らぬ街のどこか、いつか行ったことがあるかもしれない場所に立ち尽くしていた。日常はもはや、ただの夢の残骸に過ぎず、現実は歪み、消え失せ、再び形を変え続けている。
そして、今もこうして日々が流れ、街が目の前で崩壊し続ける。俺のいた世界は、もう二度と戻らない。日常の微かな振動が、ついに完全な無音へと消え去った。こんな風になるなんて誰も教えてくれなかったし、俺さえもそれを信じようとはしなかった。しかし今、俺たちはただ、崩壊のその果てにいる。