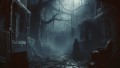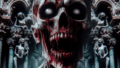私は、何よりも夏の終わりが好きだった。まだ昼間の陽射しが強いが、夕方になると少しずつ涼しさが増してくるあの感覚を味わうのがたまらなかったからだ。そして、その夏も終わりに差し掛かろうとしていたある日、私はベストな形で夏を締めくくるために、一人で近所の山にハイキングに行くことにした。
その山は子供の頃からよく訪れており、裏手には小さな神社もあって、地元の人々には親しまれている場所だ。とはいえ、実際には訪れる人はまばらで、私にとってそれが一人でのんびりするには最高の場所だった。
その日、私はいつもの道を辿って山頂を目指していた。普段通りの道を行けば、小さな川を渡る小さな木製の橋があり、その先で道は二手に分かれている。右に進めば急な坂を駆け上がり、一気に山頂へ。そして左に行けば、より緩やかな道で時間をかけて登ることができる。
私は左の道を選んだ。過去、右を選んで急ぎすぎて酷い筋肉痛に悩まされたことがあったからだ。
ゆっくりと歩き始めてしばらくすると、あることに気がついた。普段なら聞こえてくる鳥の鳴き声や風の音が、どこか遠くに感じられる。むしろ、静けさと共に自分の足音だけが耳を占領していた。私は気のせいだと自分に言い聞かせ、それほど気にしないことにした。
30分ほど歩いたところで、道に分岐点が現れた。そこには見覚えのない小道があり、古びた石碑が立っている。興味を惹かれた私は、何故かその道に進んでみる気になった。
石碑には苔がびっしりと生え、かろうじて文字が読める状態だった。何とか解読しようと近づくと、「道を誤る者、帰路を絶たれるべし」と刻まれているのが分かった。何とも不気味な意味を持つ言葉だと思ったが、私はその時、まるで誰かに呼ばれているような感覚に包まれ、その道を進んでいった。
道は狭く、すぐに鬱蒼とした木々に囲まれ、薄暗くなった。そして、だんだんと霧が立ち込めてきた。心の奥底では不安が募り始めていたが、それでも引き返すことなく進み続けた。
急に辺りが開け、小さな湖が現れた。その湖の周りには誰もおらず、まるで自分がこの世で唯一の人間になったような錯覚に陥った。その時、背後で何かの気配を感じた。
振り返ると、そこには見たこともない着物を着た老人が立っていた。彼はいつの間にか私のすぐ背後にいたが、その存在に気付いたのはその時が初めてだった。彼の目はどこか遠くを見つめながらも、私をじっと見つめている。
「ここに何しに来たんだ?」と彼が尋ねた。その声は静かで、しかし確実に耳に届いた。
「ただのハイキングです。迷ってしまって…」と答えたが、彼は黙ったまま私を見据えていた。何かを訴えかけるように見えるその表情に、私は言い知れぬ不安を感じた。
「ここはお前のいるべき場所じゃない。すぐに戻れ」と彼は続けた。
その瞬間、私の中で何かが弾けたような感じがした。そして正気に戻った私は、足早にその場を後にした。霧が一層深くなり、方向感覚がおかしくなる。道を戻る途中で何度も、振り返ればその老人が再び現れるのではないかと心配になった。
なんとか古びた石碑の前に戻ると、道が元に戻ったかのように明るくなり、普通の山道に変わっていた。安堵の息をつくとともに、私はすぐさま山を下りることにした。
その後、無事に家に戻ったが、奇妙なことが起こり始めた。まず、家の中の家具の配置が微妙に違っていた。家族に説明し、誰かが変えたのかと問うても誰もそんなことはしていないと言う。
そして次の日から、人々が私を見る目が変わったことに気がついた。通勤電車で出会う人々、職場の同僚、誰もがどこか余所余所しく、時には私を避けるように振る舞うのだ。
数週間後、ついに私は気がついた。鏡に映る自分の瞳が、以前とは違う色をしていることに。青みがかったかすかな輝きがあり、自分のものでないような違和感。
それからというもの、私はあの山を訪れることができずにいる。もし再び訪れたら、私は元の世界に戻れなくなるのではないか。そんな気がしてならないのだ。それでもなお、あの日の怪異を忘れることなく、毎日を怯えながら過ごしている。今も心のどこかで、あの老人の目が私を見つめ続けている気がしてならない。