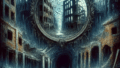小雨の降る夕暮れ、山中の小道を歩くことになったのは、まったくの偶然だった。記憶の中にある古びた地図と、確かな根拠に欠ける方位感覚だけを頼りに、私はその道に迷い込んだ。木々の合間に見え隠れする空には、灰色の雲が広がり、太陽は遠にその姿を消している。森の冷たさが肌を刺し、その不快さはじわじわと心の奥底に染み込んでいく。
足下に転がる石や、湿った土の感触。古い信号のようなノイズが時折風に乗り、耳に不快な音を響かせる。歩みを進めるごとに、別世界に入り込んでしまったかのような錯覚を覚え、恐怖という感情の縁をなぞるような心地になった。突然、周囲が静まり返り、まるで私一人が時間の流れから切り離されたかのようだった。
道の先に現れたのは、巨大な岩のような丸太が積み重なった奇妙な形状の物体だった。その上に乗る何かが、暗闇の中で蠢いている。それは、巨大な顔を持つ異形の存在で、冷たい無機質な眼差しが私を捉えたのだ。その瞳には、理解し得ない異次元の景色が映し出されているようで、見る者の魂を吸い込もうとする力を持っているかのように思えた。
その存在は決して現実にはあり得ないもので、一瞬のうちに、私の理性の範疇を超えたものとして成立していた。恐怖が全身を貫き、背筋を凍らせる。私はその場から逃げだそうとしたが、足が地面に張り付けられたように動かない。恐怖に支配されながらも、私は目を逸らすことができず、ひたすらその存在と向き合わざるを得なかった。
やがて、その存在の口が開き、低く不明瞭な声が空気を震わせる。言葉には意味が伝わらず、ただ響くだけの音として私の耳に届いた。しかし、その音には奇妙な力が宿っており、体の芯を打ち鳴らすように反響し、私の思考をじんわりと蝕んでいく。次第に意識の境界が薄れ、まるで自分自身が溶けてしまうかのような感覚に襲われた。
その異形の存在は、次元を超えた何か、人知を超える存在の一端に触れているのだろう。私の頭には数多の映像が流れ込み、宇宙の彼方、あるいはそれよりもなお広大な何かを垣間見る。そこには常識的な理解を超えた光景が広がり、人間の言葉では表現し難い、全く異質な世界が確かに存在していた。
一瞬の沈黙の後、意識が再びこちら側に引き戻された瞬間、その怪異な存在は忽然と消え去ったように思えた。しかし、私の中には何か形容し難い違和感が残り、現実が薄い膜のように隔てられているように感じた。その時にはすでに日が完全に沈み、周囲は深い闇に包まれていた。私はその場で立ち尽くし、どの方向に進むべきかもわからなくなっていた。しかし、不思議と心は静まり返っていた。
暗闇の中を手探りで歩き始め、自分がどこへ向かっているのかさえ定かでないまま、ただ足を前へ出していた。奇妙に歪んだその世界では、物理的な距離という概念が曖昧であり、時間も遅々として進まないように感じられた。そして、どれほどの時間が経過したのかさえ不明のまま、私は再びその存在が現れることを恐れながらも、一瞬一瞬を生き抜こうとしていた。
時折、背後から聞こえる不穏な音に振り返るが、そこには何も見当たらない。それでも確かにそこに「何か」がいる気配を感じながら、生々しい恐怖に苛まれ続けた。理解を超えたものに触れてしまったことによる心の動揺は、決して拭い去ることができず、私の存在の根幹を揺さぶり続けた。
やがて、霧が晴れるように意識が明瞭になり、私はいつの間にか自分の知る現実の世界に戻っていることに気づいた。そして、その時過ごした時間が、この世のものとは異なる次元であったのだと悟った。しかし、私は決して元の自分には戻れないだろうという予感が、心の片隅にじっとりと居座り続けていた。
誰にもそれを打ち明けることができず、巨大な恐怖を胸に抱いたまま、私は日常に戻るしかなかった。だが、ふとした瞬間、あの異形の存在の眼差しが、今でもどこかから私を見つめているような錯覚に囚われる。理解を超えた世界に触れてしまった者として、私はこの現実の中で何を信じ、何を恐れるべきか、もう分からなくなっていた。