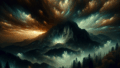ある晩、十月の終わり頃だったと思う。仕事から帰宅し、いつものように夕食を済ませ、ソファに腰を下ろした。日常の喧騒からようやく解放されたこの瞬間が、私にとって一日の中で最も至福のひとときだ。部屋は静かで、時計の針が刻む微かな音だけが耳に届く。何も特別なことがない、穏やかな夜。でもその夜を境に、私の日常は少しずつ、しかし確実に崩れ始めた。
最初の違和感は、何の前触れもなく訪れた。テレビのリモコンを探そうと立ち上がった瞬間、足元に何かが引っかかったんだ。それは、見覚えのない古びたアルバムだった。何故それがリビングの床に転がっているのか理解できなかった。家を出る前にはそんなものはなかったはずだし、自分は一人暮らしだ。他に誰かが持ち込むこともない。
そっとアルバムを手に取って、中を開いた。そこには、懐かしい風景の写真が何枚も貼られており、どれもすべて自分が知らない風景だった。ただその風景の中には、幼少期の自分らしき人物が写っている。なんとも説明しがたい不安感に襲われ、素早くアルバムを閉じた。それからは気にも留めずに、ただ自分の部屋の本棚にしまい込んだ。
次の日もまた、いつもと変わらない生活を続けた。しかし、それから数日もしないうちに、日常の小さな部分に異変が起き始めた。例えば、朝起きて洗面所に行くと、使いかけの歯磨き粉が新品に戻っていたり、食器棚の食器が微妙に配置が変わっていたりした。最初のうちは大したこととは思わなかった。もしかしたら、自分がそんなことを忘れているだけかもしれないと考えていた。
けれども、次第にそれは無視できなくなっていった。ある晩、寝室のドアを開けると、いつもの古びたカーペットがなぜか真新しいものに変わっていた。誰かが入り込んだ形跡はなく、鍵も別段変わりなかった。まるで、見えない誰かが私の知らないうちに、部屋の中を少しずつ改変しているような感覚があった。またその頃から、日常の些細な物音がどうにも気になって仕方がなくなった。何かが直接的に恐ろしいわけではないが、じわじわと精神を蝕むような不快感が付き纏う。
不安に駆られ、友人たちに相談してみても、当然のように気のせいだと片づけられてしまう。「疲れているだけだよ」や、「ストレスが溜まっているんじゃない」といった同情のような言葉しか返ってこなかった。これが自分だけの問題ならば、そうかもしれないと口に出したものの、内心ではむしろ恐怖は増すばかりだった。
またある夜、就寝中にふと目が覚めた。時計を見ると、真夜中を少し過ぎた頃だった。周囲は静まり返り、しかしどこかから小さな足音が聞こえてくる。それは確かに人間の足音のようで、冷たい汗が背中を伝った。音は徐々に寝室へと近づいてきて、ドアの向こうでしばらく立ち止まったように感じた。誰もいないはずの家で。
その夜からは毎晩、足音が確実に聞こえてくるようになった。ましてやその足音は、時折何か話すような声、囁くような声と共にある気がしてきた。その声は何語かすらもわからないが、それはとても悲しげで、冷たく、哀れ声のような感じだ。胸の奥が締めつけられるような感覚があり、夢なのか現実かさえわからなくなっていった。
ある晩、耐えきれずに寝室のドアを開ける決心をした。懐中電灯を手に、恐る恐るドアノブに手をかける。心臓が鼓動を刻む音が、やたらと大きく聞こえていた。ドアを開けると、そこにはただ暗闇があるだけだった。けれども、自分のいるはずのリビングの壁が見知らぬ装飾でいっぱいになり、古びた肖像画が何枚も掛けられている。
そうして、気がついた。見たこともない肖像画の中の一人が、自分によく似ていることに。まるで過去の自分を見せつけられるような、目を逸らそうにも逸らせない恐怖がそこにはあった。そしてそれを見つめる自分の影が、微かに動いているような、どこか別の意思を持っているような奇妙な感覚に襲われた。それ以上を確かめる勇気はなく、ただ必死に寝室に戻り、その日は眠ることにした。
それ以来、家を出ることが怖くなった。昼間はどうにかして外に出ているが、夜になるとあの足音がついて回ることで、固定された日常が崩れ去っていく。その後も何度も何度も、同じことが繰り返され、結局その当時の住居を手放すことに決めた。
新しい場所では、そういった奇怪な現象は収まった。しかし心の奥のどこかに、まだ何かが潜んでいるような不安感を抱えて生きている。あのアルバムの記憶もまだ消え去ることがない。自分の日常が、何かによって崩れ去る可能性があると知ってしまったからだ。
いずれにせよ、あの家が今どうなっているのか、もう知る勇気はない。けれどもそれが現実に存在するものなのか、それとも何かの幻だったのか、一度も答えには辿り着けていない。日常がどれだけ脆く、そして簡単に崩れてしまうものなのか。それを実感した時の衝撃は、決して忘れられない恐怖として、今も胸に残り続けている。