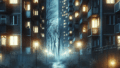私の名前は佐藤といい、都内で普通のサラリーマンをしている。特筆するようなこともない、ごく普通の人生を送っていた。少なくとも、あの日までは。
ある週末の夜、いつものように仕事を終えて帰宅した私は、帰り道で一本の古びた小説を見つけた。表紙は擦り切れていて、著者名すら読めない。その小説を手に取り、私はなぜか不思議な魅力を感じ、無意識に持ち帰ってしまった。そして、その夜から私の人生は静かに狂い始めた。
最初は何の変哲もない夢だった。曖昧で具体的なことは何も覚えていない。ただ、どこか見覚えのある風景の中を歩いている自分がいた。目が覚めたとき、得体の知れない不安に包まれていた。妙な夢だったが、深く考えることなくその日はそれで終わった。
翌日、職場に向かう電車の中でふと、小説のことを思い出した。どうしてあれをあのままで持って帰ったのか自分でも説明がつかない。昼休み、私は好奇心に駆られその小説を読み始めた。読み進めるうちに、ページの印字が薄れ、現実の風景が色褪せていくような感覚を覚えた。内容は何の変哲もない、どこにでもあるような話。しかし、物語が進むにつれて、登場人物の一人が徐々に精神的に崩壊していく様子が描かれていた。
私は次第に自分とその登場人物の境目が曖昧になっていくのを感じた。あれはただの小説だったはずなのに、まるで自分自身の心が侵食されていくような気がしてならなかった。その夜、私は再びあの夢を見た。今度は風景がより鮮明になり、自分が歩いている道の細部まで覚えている。しかし、やはり夢の中のどれも現実感が欠如しているように思えた。
日々が過ぎていくにつれ、私は少しずつ現実と幻想の区別がつかなくなっていった。出勤途中の風景が、小説の中の描写と奇妙に一致することが増えていく。そして、職場でも同僚がぽっかりと姿を消すような感覚に陥り、言葉を交わしてもどこか遠くにいるようだった。
ある時、私は街中であの小説の中に出てきた建物を見つけた。中に入ると、そこは寂れた廃墟で誰もおらず、妙に冷たい空気が漂っていた。その場所を見たとき、胸の奥が息苦しくなるような感覚に襲われた。この建物に自分がどうしてここにいるのかという疑問すら湧かなかった。戻るべき場所がなくなってしまったような気がした。
その夜、自宅に帰った私は自分がどこにいるのか分からなくなった。部屋の家具、壁の模様、窓からの景色、すべてが微妙に違っているように見える。頭が混乱し、手に取った小説を思わず投げ捨てた。小説はまるで意志を持っているかのように部屋の片隅で静かに佇んでいた。
それからしばらく、私は現実と幻想の狭間で過ごすようになった。会社に行けば、当然のようにデスクがなくなっていたり、言葉を失ってうつろに朝を迎える日々。歯を磨き、顔を洗うとき、鏡の中の自分が自分ではないような感覚が次第に増していった。
ある日、何気なく街を歩いていると、知り合いの顔をした見知らぬ人々がすれ違うようになった。彼らは私を知っているのに、私は彼らを知らない。この狂ったような違和感が沸き起こるたびに汗が吹き出し、心臓が不規則なビートを奏でる。
最終的に私は街の雑踏の中で動けなくなり、ただ立ち尽くしていた。すべてが歪み、音が消え、視界が徐々に薄れていく中で、自分がどこにいるのか、何をしているのか、確かなことが何もわからなくなった。ただ、ぽつんと世界に取り残されたような孤独感だけが胸を締め付ける。
時間がどれだけ経ったのかわからない。気がつけば私は病院のベッドで目を覚ました。医師や看護師たちが、心配そうな顔で私を見下ろしている。質問しても、明確な答えは返ってこない。彼らの話では、私は数日間意識不明だったらしいが、どうしてここにいるのか、自分がどうなったのか、誰一人として私に教えてくれる人はいなかった。
唯一の手がかりとして、自分の枕元にあの小説が置かれていた。恐る恐る中を見ると、最後のページが見慣れた筆跡で埋め尽くされていた。そこには、私自身の体験が書かれていた。現実と幻想が交錯し、やがて一つの物語として完成しようとしていた。
その瞬間、私は理解した。すべてが、この小説の中に収束しているということを。現実は幻想となり、幻想が現実を侵食していく。私自身がどちらに存在するのか、もはやわからなくなってしまった。
療養中の医師の言葉が耳元で響く。「もう少しで治りますよ。」そう言われても、治るということが何を意味するのかさえも理解できなかった。ただ、小説のページが再び閉じるまで、私はこの曖昧な世界の中で漂うことしかできないのだろう。現実なのか幻想なのかわからないままに。