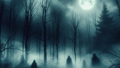ある日のことだ。私はいつものように職場のオフィスに向かっていた。通勤電車に乗り、見慣れた風景が流れる車窓をぼんやりと眺めていた。特に変わったことのない、普段通りの朝だった。オフィスに着くと、同僚たちがいつものように会話をし、コンピューターに向かって仕事に取りかかっていた。しかし、その日の午後、ふとした瞬間、何かがいつもと違うと感じた。
会議室の時計を見たときだ。針は正確に時を刻んでいるはずなのに、なぜか時間がまるで遅れているかのように感じた。会議が終わると、いつもなら昼休みが待っているはずだったが、なぜか時刻は既に午後3時を指していた。頭の中で時間が一瞬飛んだような感覚がしたが、そのときはあまり深く考えず、再び仕事に戻った。
翌日も同じ時間に家を出た。しかし、最寄り駅に着くと、何か違和感を覚えた。駅のアナウンスが微かに狂った音程で流れていたのだ。普通の人なら気にしないかもしれないが、私はどうにもその音が耳について仕方がなかった。周囲を見渡しても、誰一人として違和感を感じている様子はなかった。列車に乗り込むと、隣に座った中年の男性が奇妙な笑みを浮かべてじっと前を見つめていた。彼は何も話さず、静かに次の駅で降りて行った。私の心には、その無言の笑顔が深く刻まれることとなった。
その日から、私の身の回りの「変化」は加速していった。まず、家に帰ると、リビングの家具の配置が微妙に変わっていた。最初は家族の誰かが動かしたのだろうと思ったが、尋ねても誰も心当たりがないと言う。次に、いつも行くコンビニで顔馴染みの店員が、見知らぬ人になっていた。彼は人懐っこく笑いかけてきたが、その笑顔の中にどこか不自然さを覚えた。
時間が経つにつれて、職場でも周囲の様子が変わり始めた。同僚の一人が突如として私に話しかけるのを避けるようになり、ある日、彼から「昨日、君が言ってたこと、本当にそうするの?」と聞かれた。私は何のことか全く分からず、ただ曖昧に「そうかもしれないね」と返事をしたが、その瞬間、彼の顔に浮かんだ不安の表情が今でも忘れられない。
ある晩、疲れて帰宅した私は、リビングの照明がいつもの白熱灯から蛍光灯に変わっていることに気づいた。家族に聞いても誰も交換した覚えがないと言う。何かが確実に狂い始めていることを確信した私は、その夜、はっきりとした恐怖とともに眠りについた。
次第に、道を歩く人々の顔までもが変わり出した。表情がないのだ。まるで作り物のような顔で、ただ無表情に通り過ぎて行く。そして、時には急に笑い出すこともあった。その不気味な光景に慣れることはなかった。街全体がまるで異世界へと変わりつつあるように感じられた。
ある朝、私は職場のビルに着くと、自分のオフィスが別の部屋に移転していたことを告げられた。驚きと共に案内された新しいオフィスは、当然見覚えのない場所だったが、同僚たちは皆、自然に受け入れていた。私は一人で孤立した気持ちになり、どこで自分は間違った道を選んでしまったのだろうと考えながらデスクに座った。
最後の決定打は友人と会った時だった。長年の友人である彼と会ったのは数週間ぶりだったが、彼の顔が別人のように見えた。声は確かに彼のものだったが、顔立ちがどこか馴染まない。話しているうちに、そのことを指摘すると、彼は急に笑いを浮かべ、次の瞬間には何もなかったかのように話を続けた。私は冷たい汗が背中を流れるのを感じ、それ以上突っ込むことができなかった。
その日、家に帰ると、家のドアが鍵をかけられていなかった。恐る恐る中へ入ると、家具は元通りだったが、家族の写真がすべて別のものに変わっていた。見知らぬ人々が私の家族として写っている写真を見たとき、何もできずにただ呆然と立ち尽くしていた。
私は次の行動を決めることができず、家を飛び出した。そのまま夜の街を彷徨い歩き、誰にも声をかけられないことを祈りながら、ひたすら歩き続けた。全てがまるで悪夢の中にいるように感じた。
こうして日常が徐々に崩壊していく中、私は日ごとに現実感を失い続けている。どこに行っても、何を見ても、以前の正常を取り戻すことはできない。変わり果てた風景の中で、私は今も、何が本当で何が夢なのかを見分けられずに生きている。現実と夢の境界が曖昧になり、私自身が消え去ることへの恐怖が湧き上がる。