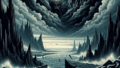山間の小さな村、霧が立ち込める夜な夜な、人々は家の扉を固く閉ざし、灯りを落とした。遠くで犬が吠える声が響き渡り、不吉な予感を漂わせた。村には古くから伝わる言い伝えがあった。夜更けに、何者かが潜んで人を狩る。顔を艶やかな白い布で覆ったその者は、獲物を見定める鋭い目を持ち、気配を消して忍び寄るという。
村人たちの間でその存在は「覆面の狩人」として恐れられていた。だが、その正体を知る者はなく、村は不安と恐怖に包まれていた。ある晴れた日のこと、村の酒場で一人の青年がその話を聞き、興味を持った。名を修司という彼は、普段は都会で生活しているが、田舎の静寂を求め、久しぶりに故郷へと帰省していた。
修司は、半信半疑でその伝説を聞き、心のどこかでそんなことが起こるはずがないと考えていた。しかし、何かに突き動かされるように、彼はその夜、村のはずれにある森へと向かった。月明かりの微かな光が道を照らし、彼の影を長く引き延ばした。
森の中は静寂に包まれ、風が葉を撫でる音だけが響く。修司は心臓の鼓動を感じつつ、慎重に足を進めた。やがて目の前に見えてきたのは、朽ち果てた廃墟のような建物だった。かつての住居であったのだろうか、今は誰も住むことのないその場所には、時間の流れを超えた静けさが漂っていた。
彼が足を踏み入れた瞬間、背筋に冷たいものが走った。ここには何かがいる。直感がそう告げていた。修司は、誠の念を込めて耳を澄ましたが、聞こえてくるのは自分の吐息と、かすかな風の音だけだった。
奥へと進むに連れ、建物の中は暗く、灯りを求める手が懐中電灯に伸びた。その光が照らし出したものは、古びた家具と埃まみれの床だった。しかしその時、何かが彼の気を引いた。それは壁に描かれた一連の不気味な絵だった。猟奇的な光景が色褪せたペンキで描かれ、見る者に不安を与える代物だった。
彼はその絵の意味を理解しようとしたが、その時、不意に背後から感じた強い視線に息を呑んだ。振り向くとそこには何者かの気配が。闇の中からじっと彼を見つめる鋭い眼光が浮かび上がり、その正体を見極める間もなく、修司は激しい一撃を受け、視界が一瞬にして消えた。
目を覚ました時、修司は冷たい床に縛られ、身動きが取れなかった。頭上には古びた天井があり、その傷んだ木材から薄々と光が漏れている。さらなる絶望が彼を襲ったのは、目の前に立つ白い布で顔を覆った人物だった。その者は無言で鋭利な刃物を手にしており、その光が恐怖を増幅させた。
覆面の下の瞳がひどく冷たく、計り知れない狂気を宿していた。それは人のものとは思えないほどの冷酷さを持ち、修司の心を凍てつかせた。刃がゆっくりと彼の方へと迫り、修司は痛みに体を震わせた。それは単に肉体的な痛みではなく、精神を蝕む恐怖そのものだった。
この異常なまでの静寂の中、修司は意識が遠のくのを感じた。それでも彼の心は懸命に生きる望みを捨ててはいなかった。その時、どこからかかすかに助けを求める声が聞こえた。それは修司の内なる声だったのかもしれないが、彼にはそれが確かに届いたのだ。
声を振り絞り、抵抗する意思を見せるが、力は次第に弱まっていく。意識が薄れゆく中、彼は思った。果たして、この狂気の底にある者は何を願っているのだろうか。覆面の狩人は、ただただ何かを求めて人々を狩っているのか、それともその裏にはもっと悲劇的な理由があるのか。その真相は、彼が知ることは決してなく、すべてが闇に消えてゆくようだった。
その後、村では修司が行方不明となったことが広まり、再び不安の種が芽を出した。村人たちは改めて夜の安寧を恐れるようになり、覆面の狩人の存在は現実のものとして語り継がれた。修司の姿を見た者はいない。彼の運命を語れる者もまた、誰一人としていなかった。
ただ一つ、押し留められた狂気の果てに立つのは、静寂な恐怖と、それに囚われた者たちの絶望だった。運命に抗えなかった青年の物語は、今でもこの村の迷信として語り継がれ、夜を歩く者は誰一人としていない。闇の底から声を上げる者たちの叫びが、今もどこかで響き続けているのかもしれないのだから。