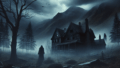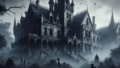私が体験した話を聞いてほしい。あれは今でも忘れられない、信じ難い出来事なんだ。信じてもらえないかもしれないが、本当にあったことなんだ。
ある夏のこと、大学の友人たちと一緒に小さな孤島へキャンプに行くことになった。参加者は私を含めて6人。メンバーは大学のアウトドアクラブの仲間で、皆キャンプが好きだった。そこは小さな無人島で、公にはほとんど知られていない。私たちは自分たちだけの冒険を楽しむため、情報をかき集めてその島を見つけ出し、ボートをレンタルして向かうことにした。
島には手つかずの自然が広がっていて、到着したときはその美しさに心奪われてしまった。砂浜にキャンプサイトを設け、焚き火を起こし、テントを組み立てる。我々は島を探検し、海での泳ぎを楽しんだ。一見すると、何の変哲もないキャンプだった。
夜になると、焚き火を囲んで談笑が始まる。手持ちのランタンが唯一の光源で、月明かりと相まって幻想的な雰囲気を醸し出していた。そんなとき、一人が「この島には何かが居るらしい」と呟いた。
彼の話によると、ここ数年の間に数人の冒険者が行方不明になっているらしい。無人島だが、何かが人を捕らえて離さないという噂だ。皆笑って聞き流していたが、私の心のどこかに小さな不安が芽生えていた。
夜更け、私は水を取りに一人でテントを出た。キャンプサイトから少し離れた場所に小川が流れており、新鮮な水を得るためにはそこまで行く必要があった。森の中を進む足音だけが響く。闇は深く、何かの気配を感じるたびに背筋が冷たくなった。
彼が言っていた「何か」というのが頭をよぎる。一人ではなかったことに気づくのは、ほんの些細な物音だった。誰かが息を潜めて私を見ている。そんな直感があった。
急いで水を汲むと、来た道を引き返した。それでも後ろからつけられている気がしてならなかった。キャンプサイトに戻ったときには、少しの安堵を覚えたが、それも束の間のことだった。
その夜、テントの中でどうしても眠れなかった。風が森を揺らし、何かが近づいてくる音に聞こえる。私は一晩中目を閉じては、また開け、ただひたすら明かりを待っていた。
翌朝、私は焚き火の周りで友人たちと昨夜の話をした。彼らも同じような不気味な感じを受けたらしい。だが、他の皆はそれを気にせず、今日も探検を続けようとしていた。私は内心でそれに反対だったが、結局皆に合わせて行動することにした。
昼下がり、島の奥深く、奇妙なものを見つけた。朽ち果てた木製の小屋だ。自然に飲み込まれながらも、何かを隠しているような気配がある。全員で中を覗き込むと、そこには古びた家具と埃まみれの雑誌があるだけだった。
不意に、足元の床が軋み、私の重みで崩れそうになった。驚いて後ろに飛び退くと、床板の下には更に地下へ続く階段が隠されていた。何かに惹きつけられるように、私たちは階段を降りていった。
地下に広がっていたのは薄暗い洞窟のような部屋だった。湿った土の匂いが鼻をつく。手持ちのランプだけが頼りだ。目の前に朽ち果てた祭壇のようなものがあり、そこに年代を経た人形が載せられていた。恐ろしく不気味だった。何か儀式じみたものが行われていたとしか思えない。
「帰ろう」と誰かが言った時、その場に来て初めて「これは危険だ」と確信した。何かに見られているような冷たさが体を包む。早くここを離れたかった。
私たちは全速でその場を離れ、小屋を後にした。その日から私たちはキャンプの計画を切り上げ、翌朝には島を後にすることに決めた。
その晩、テントの中で再び不気味な気配に苛まれた。今度は風ではなかった。明らかに何者かの足音が一つのテントから次のテントへと回っている。それが私のテントの前で止まるのを感じた。息を殺し、何も聞こえないことを強く願った。
だが、ジッパーがゆっくりと下ろされる音がした。その瞬間、私は声にならない叫びを心の中で上げた。だが、視線を上げてもそこには誰も居なかった。ただテントの外には、砂の上に奇妙な紋様が描かれていた。それはまるで、あの古い祭壇にあったものと同じもののように見えた。
夜が明けると、私たちは何も言わずに島を後にした。振り返ると、島がただ静かにそこに立っていた。それ以来、あの島に戻ることはなかったし、私たちの誰もがその全てを語ろうとはしなかった。友人たちとあの経験を共有してからも、話題に出すことは避けた。
だが夢に見ることがあるのだ。あの祭壇、あの人形、そして砂の上の紋様。それは決して解けない謎のままであり続ける。何かが私たちを見ていたのだ。それが知りたかったが、知ることが恐ろしかった。
あの島に何があったのか、きっと永遠に分からないだろう。それでも、私たちを招く見えない影が存在していたことだけは確かだ。どこにでもある無人島、それが私たちに知らせた恐怖の物語だ。