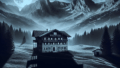私は四国の山奥に住む者です。かつて私が経験した、今でも鮮烈に覚えている不思議で恐ろしい出来事をお話ししたいと思います。これが皆さんに伝わる話かどうかは分かりませんが、私にとっては忘れることのできない体験です。
あれは、私がまだ子供のころのことでした。夏休みのある日、祖父母の家がある山の村に家族で遊びに行ったときのことです。村はとても小さくて、そこには数十軒の家があるだけでした。そして、村の裏手には広大な森が広がっていました。
夏休み中ということもあり、私は毎日のようにその森へ探検に出かけていました。祖父母は、「森にはしゃあな妖怪が出るから、夕方までには帰ってくるように」と言っていましたが、私はそれを大人の迷信だと思っていました。
ある日のこと、私は森の奥へと一人で足を踏み入れていました。深く進むにつれて、周囲の木々は生い茂り、薄暗くなっていきます。不思議と恐怖心は薄れていき、むしろその未知なる場所への好奇心が勝っていました。
その時、不意に誰かの囁き声が聞こえたのです。それは風が草木を揺らす音とも、鳥のさえずりとも違いました。耳を澄ますと、確かに人の声が聞こえます。「こっちへ来い、こっちへ来い」と低い声で誘っているように感じました。心臓が早鐘のように鳴りだしましたが、なぜか、もっと奥へ進まなければならないと感じたのです。
少し進んだところで、突然視界が開け、小さな社(やしろ)が現れました。社は古びていて、苔むしていました。そこには奉られている神様の名はおろか、誰も見たことがない不思議な雰囲気が漂っていました。それでも私は、どうしてかその場を動けず、その社に引き寄せられていくように近づきました。
社を覗き込んだ時、私は自らの目を疑いました。そこには、明らかに人間ではないものが座っていました。それはか細く白い体をしており、狐のような顔を持っていました。その目が、まっすぐに私を見つめています。唐突に恐怖が襲いました。しかし、身体は硬直して動けません。あの不思議な声は、まだどこかで響いているかのように感じました。
「お前は何者じゃ」とその妖怪は言いました。言葉ではない、直接脳裏に響くような声で。それを聞いた瞬間、私は悲鳴をあげようとしましたが声が出ません。ただただ恐怖に震えるしかありませんでした。
その妖怪は、私の反応を見て微笑んでいるようにも見えました。瞬き一つせず、じっとこちらを見つめたまま、ひどく穏やかにそれは続けました。「ここはわしの庭じゃ、他所者に荒らされては困る」と。不思議なことに、その言葉にある種の懐かしさを感じたのです。心がざわめくとはこのことか、と思いました。何が起こっているのか理解できず、ただその場に立ち尽くすほかありませんでした。
ふと気がつくと、周囲の音が戻ってきました。蟲の鳴く声、木々がざわめく音、それらが再び耳に入ってきたのです。そして、先ほどの社も妖怪も、そこには存在していませんでした。ただただ、森の静けさがあるばかり。
家に戻ってからも、その出来事を心の中で何度も確かめました。あれが何であったのか、本当に妖怪であったのか。誰かに話すべきか迷いましたが、結局私は誰にも話しませんでした。日常に戻ったとしても、あの感覚が忘れられることはなかったからです。
そしてある日、祖父が私にあることを教えてくれました。昔、この村の森には狐の神が住んでいたという伝承があったらしいのです。それは村を守る存在であり、村人たちはその神を恐れつつも敬っていたとのことでした。
あの日、私が出会ったのはその神だったのでしょうか。それとも、ただの幻だったのか。今でも分かりません。分かっているのは、あの森には何かが存在しており、人が踏み入ることを好まないということ。以来、私は森を訪れることはなくなりました。しかし、心のどこかでまた会いたいという思いも消え去ることはありません。
もしあなたがこの話を聞いて、ただの作り話だと思われるのであれば、それも良しとしましょう。ただ、もしあなたが同じような場所を訪れたときには、どうかその存在に敬意を払い、そして決して逆らわないでください。彼らは私たちの想像を超えた存在であり、その力は計り知れないからです。
我々の知らぬところで、この世界には不思議なことがまだまだあるのです。それが私の体験から得た教訓であり、いずれまた皆さんにもそのような出来事が訪れるかもしれないと思っています。心の準備は決して無駄ではありません。それを胸に、この話を記憶の片隅に留めておいてください。