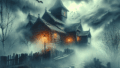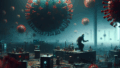深い森の中にひっそりと佇む古い神社があった。木々は何世紀もの時を刻み、その存在を知る者は少ない。神社は今や廃墟となり、苔むした石段とひび割れた鳥居が、かつての繁栄を物語るのみだった。かつてこの地を収めていた名家、桜庭家の者たちが祀られた神社である。
その呪われた地に足を踏み入れたのは、大学で民俗学を専攻する学生、祐介だった。彼は卒業論文の資料を求め、伝承に彩られた地を訪ね歩いていた。ある夜、古い文献に記された「桜庭の呪い」について知ったのが運の尽きだった。
桜庭家は、人の生き血を捧げる異端の儀式を行っていたという。村人たちはその噂を恐れ、やがて怒りを爆発させた。桜庭家の末裔たちは皆、刃の下に倒れ、祀られた神も忘れられた。だが、一夜にして消えたという呪詛が未だに森の中を彷徨い続けているというのである。
祐介はその話に引き寄せられ、その夜、懐中電灯を片手に神社へと向かった。暗闇の中、月明かりがかすかに照らす石段を慎重に登った。彼の背後には、風に揺れる草のざわめきが追いかけるように囁いていた。
やがて彼は神社の前にたどり着いた。木製の扉は腐り、軽く押すだけで音を立てて開いた。その中は思いのほか広かった。儀式に使われたと思しき道具が今も残され、時の止まった空間に息を潜めていた。彼は内部を調査し始め、古びた巻物や置き忘れられた祭具を丁寧に観察した。
しかし、その時だった。祐介は、何かが彼を見ていると感じた。心臓が胸の中で鳴り響き、背筋を冷たい恐怖が走った。彼の全身から汗が噴き出し、息が詰まるような感覚に襲われた。
突然、囁き声が耳元で聞こえた。誰かの声ではなく、無数の声が重ねられたかのようだった。耳鳴りのように、止めどなく彼に訴えかける。「約束を果たせ」と。
祐介は思わず声のする方を振り向いた。だが、そこには何もない。ただ、密度を増した闇が彼を包むだけであった。
その瞬間、祐介は気づいた。この神社が決して人を受け入れる場所ではなかったことに。血に飢えた何かが彼を歓迎したのである。まるで、彼自身が選ばれし生贄であるかのように。
彼は足元に広がる闇を凝視した。そこには影があり、その影は次第に形を取り始めた。そして、ぼんやりとした人の姿が現れたのだ。桜庭家の者たちなのか、彼には分からなかった。だが、その瞳の奥には深い憎悪と悲しみが渦巻いていた。
恐怖に背を向け、祐介は逃げ出した。神社を飛び出し、森の小道を狂ったように駆け抜けた。しかし、彼の動きとは裏腹に周囲の木々は冷たく立ちはだかり、出口を塞ぐように感じられた。
たどり着くべき場所が見えなくなり、方向感覚を失った彼は、森の中でただひたすらに彷徨った。闇はますます深くなり、彼の心を掴んで離さなかった。意識が朦朧とする中、彼は気づいた。神社を訪れたことが、取り返しのつかない過ちであったことに。
やがて、彼は足を止めた。喉が渇き、体力は尽き果てた。頭上には濃密な夜の帳が降り、震える彼を地面に引き寄せた。朽ちた葉が彼を受け止める。
その時、再びあの囁きが聞こえた。「約束は果たされる」。彼は最後の力を振り絞り、声の方向を見据えた。そこに立っていたのは、かつての人々の怨念であった。その姿は、悪夢の中に現れる幻影のように揺らめいていた。
そして、それは祐介に向かって手を差し伸べた。冷たい風がその手から吹き出し、彼の心臓を締め付けた。恐怖と絶望に苛まれ、彼は最期に一度だけ叫んだ――彼の声は森に吸い込まれ、消え去った。
その後、祐介は戻らなかった。探しに出た者も、彼を見つけることはできなかった。森は再び静寂を取り戻し、神社はそのままの姿で眠り続けた。しかし、訪れる者は皆、何処からともなく聞こえる囁き声に気づくのだった。そして、桜庭の呪いが生き続けていることを知るのだった。
森に入る者は、今も忌まわしい伝説を耳にする。その細い囁きは、約束を果たさずに去った者たちへの警告であり、桜庭の怨念が今も生きている証であった。森の静寂は、かつての罪人たちが自らの宿命を背負って生き続ける無言の叫びで満ちていた。