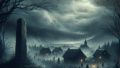警察官時代の友人、藤井から話を聞いたのは、彼が退職して独立した探偵事務所を構えた頃だった。旧知の間柄もあって、よく彼の事務所で酒を飲みながらいろいろな話をするのが常だったが、その日は何か特別な体験を話してくれると言う。
「実はな、ここ2週間ほどある依頼で現場調査をしてたんだ」と藤井は切り出した。「依頼内容は『家に幽霊が出るので調べてほしい』ってやつなんだが、それがいつものいたずらどころじゃない気がしたんだよ。」
藤井はそこから詳しく語り始めた。依頼者の田村さんは40代半ばの男性で、妻と中学生の一人娘がいる一家だった。彼はここ半年ほど家の中で奇妙な現象が続いていて、気味が悪くなり藤井に相談を持ちかけたという。曰く、夜中に脚音が聞こえる、冷気が走る、娘が泣いている声がするが、娘は部屋で熟睡しているなど。
「普段はこういう話には興味がないが、彼の話のまともさに、にわかに信じてしまったんだ」と藤井は言った。「最初は怖がっていた妻も、娘が怯え始めたことで良くない存在を感じたらしく、私を呼んで現状を調査して欲しいと。」
彼が調査を始めて3日目の夜、ついにその「何か」に遭遇する。日が沈んでから田村さんの家を訪ね、リビングで依頼者家族と共に何事もなく夜を迎えたが、深夜1時を過ぎたころに突然、寝室の反対側から冷たい風が通り抜けた。
「最初は窓でも開いてるのかと思ったよ。でも、確認したけどもちろん全部閉まってて、それどころかストーブまでつけっぱなしだったんだ。」藤井はそう説明した。
その直後、階段を上るギシギシという音が響き渡り、天井裏からまるで重い物を引きずるような音が聞こえてきた。それはリビングにいた全員が明らかに確認できる音だった。
「私は思わず娘の部屋に駆け込んだけど、彼女はベッドで眠ってた。しかし驚いたことに、彼女の寝顔が涙で濡れていて、その涙の上に幾重も重なった手形が…」
藤井は悼むように泣くように語る。「あの手形は子供のものだった、絶対に大人の手じゃない。それを見て、私はただ事じゃないと感じたんだ。」
この事件の鍵を握るのは、数年前にこの家で事故死した田村家の前住人、その娘、10歳だった少女の消えた未練があるに違いないと藤井は推測したのだ。
「そのことで田村さんとも話をしたら、その娘はどうやら事故死じゃなく、残酷にも、実は何者かに殺されたかもしれないことが浮かび上がってきた。そこではもう一言で言えないほどの思いが巡っているんだ。」
藤井はさらに調べを進め、いくつかの資料からその少女の声がこの現世に残っていること、その怨念が今もこの家に囚われていることを突き止めた。そして恐ろしい事実にたどり着く。
「以前の警察沙汰になった事件簿を確認して、びっくりしたよ。それが正真正銘、手形の持ち主だったんだ。事故死とされていたけれど、実は現場ではいくつか説明のつかない手がかりが見つかったらしい。」
それからというもの、藤井は依頼者と共に供養のための対策に乗り出す。親しい霊媒師の力を借り、徐々に家の中の奇怪な現象は鎮まっていったが、それでも時折、天井裏で音がするという。
「田村さんの一家も、一度は引越しを考察したけど、最終的にはここを住まいにする決心をしたんだ。それはおそらく、同じ悲劇を繰り返させないため、そういう責任感からだったと思う。それもまた勇敢な選択と思う。」
田村さんのもとにはそれ以来、毎年彼女のお墓に手を合わせに行くことを忘れないという彼らの行いが、どこかこの家に残る少女の魂を多少でも和らげているのかもしれないと藤井は締めくくった。
「それでもね、今でもあの涙にまみれた手形の記憶は残ったままだよ」と藤井は深く一息ついた。藤井から聞いたこの話がもたらした衝撃は私にも色褪せることのない印象を残した。
その魂はやはり未だに自らの死因を語ろうとしているのだろう。彼女を今もこの現世につなぎとめている大きな鎖を思うと、他人事ながら心が痛むのを感じるほどだった。それもまた幽霊話の一つと言ってしまえば、終わりかもしれない。しかし、その家族と少女の話は、きっと終わっていない章の話に他ならないような気がした。