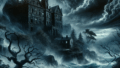森の奥深くに、ひっそりと佇む古びた神社があった。その神社は、地元の人々からは「忘れられた祠」と呼ばれ、語り継がれることなく、人々の記憶からも消え去っていた。だが、それには理由があった。
その神社は、数百年前に村を支配していた名家によって建立されたものだ。この家には、代々伝わるある秘密があった。それは、呪われた御札に関するものである。この御札は、一度誰かに封を解かれたなら、その者に災厄が降りかかるとされていた。名家の者たちは、その御札を封印し続けながら、己の栄華を維持してきたのだ。しかし、ある時を境にその家は衰退し、忘れ去られる運命を辿ることとなる。
この過去の因縁を知らずに入ったのが、若い夫婦だった。都会からこの山間の地域に引っ越してきたばかりの彼らは、自然に囲まれたこの土地を気に入り、休日になるとよく森を探索していた。そして、ある日のこと、ふとした好奇心からその神社への道を見つけてしまった。
初めて足を踏み入れた時から、夫婦には言いようのない不安感が心を覆っていた。まるで、何かに見られているような感覚が体の芯を貫いていた。鳥居をくぐると、さらに異様な雰囲気が漂っていた。呪符が貼られた社の扉は、苔に覆われ、長年開かれることのなかった頑丈な木製のものだった。
しかし、妻の理沙の好奇心が勝り、彼女は手を伸ばしてその扉に触れた。すると、長年の風化を経た蝶番が音もなく動き、扉がゆっくりと開いたのだ。中を覗き込むと、そこには安置された古い木箱が一つ、中央に鎮座していた。
夫の隆也は、その場を立ち去るべきだと主張したが、理沙の興味は止まらなかった。彼女はその木箱の蓋を持ち上げたのだ。すると、中からは一枚の御札が静かに姿を現した。幾重にも絡み合った墨の文字が書かれたその紙は、見る者に恐怖を植え付けるような不気味さを持っていた。
翌日から、彼らの日常は少しずつ狂い始めた。家の中で、異様な音が聞こえるようになり、家具がひとりでに動く現象が頻発した。そして、理沙は何者かに囁かれるような幻聴に悩まされ始めた。それは、はっきりとは意味のない言葉で、自分が何か恐ろしい存在に監視されているという感覚を与えた。
数日が経ち、隆也はかつての名家にまつわる伝承を村の古老から聞き出すことができた。彼の話によれば、「御札には強い怨念が宿っており、それを解いた者には名家が背負った業が降りかかる」ということだった。
隆也は恐怖に駆られ、理沙とともに再び神社を訪れる決意をした。彼は、この災厄を何とか終わらせる方法を探すしかなかった。夜の帳が下りる中、二人は懐中電灯の頼りない光を頼りに森を進んだ。
神社の前に立つと、不気味な静寂が包み込む。再び社の扉を開くと、中には昨日とは異なり、無数の御札が貼られていた。まるで彼らの侵入を拒むかのように。恐る恐る社の中へ進むと、どこからか低い唸り声が響いてきた。それは、彼らの心を一層淀ませるものだった。
箱の前に立つと、理沙は何かに導かれるように手を伸ばし、もう一度御札を手に取った。その瞬間、彼女の瞳の奥にある光が変わり、まるで別人のような冷たい表情に変わったのだ。しかし、隆也が彼女を呼び戻そうと声をかけた瞬間、理沙の体がフッと軽く宙に浮かび、彼の目の前で崩れ落ちた。
彼女は、一瞬のうちに意識を失い、その身体に刻まれたかのように無数の古い漢字が浮かび上がっていた。それは、かつて名家が抱えていたあらゆる罪や穢れが表出したものに他ならなかった。そして、彼女の口からは忌まわしい囁きが漏れ出した。それは彼女自身の声ではなく、何か異形の者の言葉だった。
隆也は己の無力さを呪い、神に赦しを求めた。だが、その祈りに答えるものはなく、神社の闇は彼を静かに飲み込んでいくように見えた。その後、彼は気を失い、深い眠りに落ちていった。
翌朝、神社の外で目を覚ました隆也は、隣にいたはずの理沙の姿が見当たらないことに気づいた。彼は必死に彼女の名前を呼び続けたが、森は何の反応も返さなかった。
絶望に打ちひしがれた彼は、力なき足取りで神社を後にした。その後も彼は幾度となく森を訪ね、彼女の行方を捜し続けたが、二度と出会うことはなかった。
そして、村に戻った彼は、この出来事を誰にも話すことなく、静かに時を過ごしていた。村人たちの中で、その後の隆也を見た者はいない。彼もまた、森の奥深くに引き寄せられ、理沙の後を追うようにその姿を消したのだろう。
かつて、名家に封じられた呪いは、こうして新たな歴史を刻む形で語り継がれることとなった。そして、人々は再び、その場所に近づくことを避けるようになった。それでも、何も知らない者たちがいつか再び、この忘れられた祠へと誘われることだろう。運命の糸に絡めとられ、呪いの渦へと引き摺り込まれて。助けを求める声は、森の深い闇の中で永遠に消え去ることはないのだから。