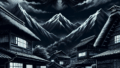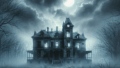村の周囲をぐるりと囲む山々は、かつてから幾多の言い伝えを孕んできた。その中でも、ひときわ人々の心に恐れを残すのが「影の森」と呼ばれる場所だった。森には誰も足を踏み入れない。見上げるほどのデクの木々が空を遮り、昼間でも薄暗く、風が通るとまるで声を潜めるような微かな囁きが聞こえるという。
村に住む誰もが、そこには近づくなと教えられて育った。ある寒い晩のことだった。村に住む少年、悠太は学校の帰り道に友人たちと口論になり、その勢いで誰もいない田んぼ道を一人、怒りに任せて駆け出した。薄曇りに囲まれ、辺りの景色はモノクロームのフィルターを通したかのようだった。
次第に薄れる光を忘れ、悠太は知らぬ間に「影の森」へと続く小道を進んでいた。差し掛かる夜の帳に気づいた時には、すでに森の入り口に立っていた。ふと立ち止まり、振り返っても、帰り道は霞がかって見えなくなっていた。
木々の間から漏れる僅かな光に、全身が包まれた。そして、やがて悠太はその影の中へと、導かれるがまま、足を踏み入れた。
森の中に漂う沈黙は、不気味なまでに絶対的で、静寂が耳に痛いほどだった。木々の間を歩くうち、心に不思議と安らぎとも恐れともつかぬ感情が広がってきた。どこか懐かしささえ感じるが、その理由はわからない。
やがて、彼の目の前に古びた神社が現れた。破れた鳥居は朽ち木のように立っている。悠太は、その奇妙さに目を奪われ、吸い寄せられるように進んだ。入り口に立ち、やがて一歩踏み入れたその瞬間――足元が崩れるような感覚に襲われ、意識が遠のいていった。
目が覚めたとき、悠太は村の中央広場に立っていた。だが、何かが違っていた。空の色は青々とし、あらゆるものが異様に鮮明に見えた。あたりを見渡すと、見慣れた村人たちがいたが、皆、少しも彼に気づいている様子はない。名の知れた老人も、いつも遊ぶ友達も、まるで悠太の存在など感じていないかのようだった。
呼びかけても声が届かない。悠太は立ち尽くし、孤独に包まれた。
時間が過ぎるとともに、村の様子が少しずつおかしいことに気づき始めた。人々の会話の中に、過去には存在しなかった名前や出来事が溢れ始め、周囲の景色もわずかに変化を遂げている。悠太の記憶と完全には一致しない世界が、彼を更なる不安に陥れた。
それでも彼は元の生活に戻る術を探し続けた。あの日の影の森へ何度も足を運んでみるも、再びその異界へと招かれることはなかった。
ある日、村祭りの準備で賑わう広場に立った悠太は、ふと神楽の舞が始まるのを耳にした。舞台中央に立つ舞手の動きには、現実と異なる何かが宿っているのを感じた。どこかで一度見たことがあるような、そんな舞いだった。
その姿が徐々に滲むように消えてゆくのを目の当たりにし、悠太は確信した。彼はもう、完全にはこの世界の住人ではないのだ。かつての日常は、もう戻ることがない。そしてそれに気づいたのも、異界の影に魅入られた者だけが抱える宿命だった。
最後に、ふと彼が見ると、村の人々は彼の存在に気づき始めたかのようで、一瞬彼と視線を交わす者もいた。しかし、それは喜ばしいものではなかった。人々の視線には畏敬と恐れ、そして少しの哀しみが滲み出ていた。
悠太は微かに微笑んで、静かに踵を返した。異界との橋渡しとしての自分を受け入れつつ、悠太はこの新しい現実の中を生きる決意を固めた――誰にも知られることのない、影の森が孕む謎と共に。
その日の月は青く、村の古い伝説がかすかに蘇るような夜だった。悠太の影が、再び静かに森へと溶け込んでいくのを、誰もがただ見守るしかなかった。彼は、消えることもなく、また完全に戻ることもなく、どちらでもない世界の住人として、淡々と奇妙な日々を送っていくことになるのだった。