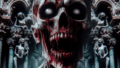これは私の故郷で起こった、ある夏の夜の話だ。まだ子供だった頃、私は祖父母の家に頻繁に遊びに行っていた。祖父母の家は山奥にあり、周囲は古い木々に囲まれていて、時折小川のせせらぎが聞こえるような静かな場所だった。田舎特有の夏の暑さと湿気は、夜になると少し和らぎ、虫たちの鳴き声が心地よいBGMとなっていた。
ある年の夏休み、私と弟は祖父母の家に泊まりに行っていた。毎晩、夕食の後には祖母の白熱した話を聞くのが楽しみだった。祖母は特に妖怪や幽霊話が得意で、夜遅くまで私たちを怖がらせるのが常だった。
その夜も、そんな不気味な話が終わり、私たちは布団に入った。弟はすぐに寝入ったが、私はどうにも眠れず、一人で縁側に出ていた。月明かりが優しく庭先を照らしており、何もかもが儚く銀色に輝いていた。夏の夜風が、肌に心地よかった。
しばらく庭を眺めていると、ふと視線の先に奇妙なものがあるのに気づいた。家の外にある古い井戸だ。本来、昼間でさえ不気味に感じるその井戸に、何故かその夜は目が離せなかった。しばらく眺めていると、井戸の傍に何かがうごめいているのが見えた。
月光がその影をはっきりと浮かび上がらせると、それが何であるのかに気づき、心臓が大きく脈打った。そこには、白い着物を着た女性が立っていた。顔は月の光でぼんやりとしか見えなかったが、明らかにこの世の者ではないオーラを纏っていた。彼女はじっと井戸を覗き込んでいるようで、動くことはなかった。
怖くなった私は、すぐに縁側から部屋に戻り、布団に潜り込んだ。その晩は、なんとか眠りにつくことができたが、あの白い女性のことは頭から離れなかった。
翌朝、祖母に井戸のことで尋ねてみることにした。すると、祖母は顔色を変えてその話を始めた。「その井戸はね、昔から不思議な話があるんだよ」と。
祖母の話によれば、その井戸は「御霊井戸」と呼ばれており、かつて村で疫病が流行った時に、多くの人々が身投げをした場所だったという。その中には、愛する夫を亡くし、絶望のあまり命を絶った女性もいたらしい。彼女の霊は成仏できず、未だに井戸をさまよっているのだと言う。
その話を聞いた私は、背筋に冷たいものが走った。私は確かに、その女性を昨晩見たのだ。再びその井戸を見に行く勇気は、もう持ち合わせていなかった。
それから数日が過ぎ、東京に戻ってもなお、井戸のことが脳裏にこびりついて離れなかった。しばらくして、祖母の家に行ったときに井戸をもう一度見たが、あの女性の姿はどこにもなかった。それでも、時折風が吹くたびに、背後に彼女がいるような錯覚を覚え、振り向くことがあった。
この話を誰かに話すこともあったが、多くの人は興味を示しつつも、笑って聞き流すだけだった。だが、私にとっては笑い話とは程遠く、あの静かな夜に見た光景がずっと心に重くのしかかるのだった。忘れたいと思いながらも、あの井戸と白い女性は、いつまでも私の記憶にしっかりと刻まれている。
そして不思議なことに、あの出来事以来、私は何か大きな選択を迫られる時、必ず夢の中であの井戸を訪れるようになった。そのたびに、あの白い女性はただ静かに佇んでおり、何も言わないまま私を見つめている。彼女が何を望んでいるのか未だにわからないが、その目に秘められた悲しみと渇望だけは、痛いほどに感じ取れるのだ。
今もなお、田舎の家を訪れるたびに井戸の方を見ないようにしている。何故なら、そこに彼女が待っているかもしれないから。そして、もし再び彼女に出会ってしまったら、次はどんな結末が待ち受けているのか、それを考えることに恐れを感じるからだ。
この話は、私が長い間忘れることができず、時折振り返るたびに背筋が凍るような、そんな実体験だ。多くの人にはただの作り話だと思えるかもしれないが、私にとっては未だに現実の恐怖として存在している。もし、この話を信じるならば、あなたもその井戸を覗き込む勇気を持つことは無いだろう。