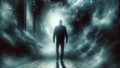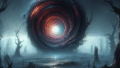その部屋には、常に薄暗い光が漂っていた。古びたランプの淡い光が、年代物の家具をぼんやりと照らしている。壁には、消えかかった絵が額に収められていた。その絵は、色が褪せ、描かれていた人物の顔は、表情を判別するにはあまりにもぼやけていた。
高校教師の藤崎誠は、ここ数週間、奇妙な幻覚に悩まされていた。授業をしている時も、家で読書をしている時も、彼の脳裏にはふと同じ映像が浮かぶのだった。それは、見知らぬ人物が彼をじっと見つめている姿だった。その人物は、無表情のまま藤崎の心に入り込み、まるで彼の内面をむき出しにして覗き込んでいるかのようだった。
その日も藤崎は、教室で数学を教えながら、あの視線が背中を突き刺すのを感じていた。何度も振り返ってみたが、そこにはただ壁に描かれた愚かな落書きがあるだけだ。それでも、彼の心は重く沈んでいった。教室を出ると、彼は廊下の突き当たりにある小さな部屋に向かった。その部屋は、教師たちが一時的に休憩を取る場所だった。
部屋に入ると、彼はまずカーテンを閉め切り、他の教師が使っている机の上の散乱した書類や備品を整理し始めた。次に、ランプをつけ、ソファに腰をかけた。彼の頭痛はますますひどくなり、幻覚がより鮮明に、彼を取り囲んでいた。見慣れた部屋の中に、突如としてあの無表情の人物が立っていた。藤崎は目を閉じ、深呼吸をしたが、人物の姿は消えることなく彼の視界に留まり続けた。
やがて、人物が口を開いた。声音は低く、言葉は不明瞭だったが、何かを告げていることは確かだった。藤崎は必死で聞き取ろうとしたが、それはまるで遠くの雷鳴のようで、意味を成さなかった。彼は汗をかき始め、心拍数が上がるのを感じた。
「何を言っているんだ?」
彼は思わず声を出した。しかし、周囲には誰もおらず、返事があるはずもなかった。困惑と恐怖が入り混じり、彼の精神は次第に削れていった。
その晩、彼は夢の中であの部屋を再び訪れた。部屋は暗く、見覚えのある家具が無造作に置かれていた。扉が音もなく開くと、暗闇の中からあの人物が現れた。今回ははっきりとした言葉を紡いでいた。
「真実を見つけろ、逃げるな」
目が覚めた時、藤崎は汗で濡れていた。彼は自分の呼吸を整え、幻覚が何を意味するのか考えた。しかし、その答えはどれだけ思案を重ねても出てこなかった。職場でも、家庭でも、薄闇の中から彼を見つめ続けるあの視線は消えることがなかった。
次第に、藤崎は学校での仕事に支障を来たすようになった。彼はますます幻覚に囚われ、正常な思考が奪われていった。どうにもならない現実に打ちひしがれた彼は、ついに意を決して医師のもとを訪れることにした。医師は、ストレスによる幻覚と診断し、投薬を勧めた。彼は渋々ながらもその指示に従い、薬を服用し始めた。
しばらくの間、幻覚は消えたように見えたが、完全に消えることはなかった。薬が切れると、再びあの視線が藤崎を襲った。薬を増やしても、効果は一時的でしかなく、彼の心は次第に追い詰められていった。
ある日、彼は自宅でさらに強烈な幻覚に襲われた。リビングの窓から差し込む月明かりが、部屋を妖しく照らしていた。その時、彼の視界に再びあの人物が現れた。今度は、以前よりもはっきりとした姿で、まるで現実の人物のように見えた。彼の精神は限界を超え、混乱と恐怖が爆発した。
「もうやめてくれ!」
藤崎は叫び、立ち上がった。彼は部屋の中をぐるぐると歩き回り、何かを壊した。頭の中では、彼を追い詰める声がどんどん大きくなっていく。彼は叫び続け、無意識のうちに拳を壁に叩きつけていた。痛みが走り、その感覚が現実への引き戻しのきっかけとなった。
彼は次第に落ち着きを取り戻し、呼吸を整えながら、再びソファに腰を下ろした。あの幻覚の人物は消えていたが、彼の心には深い恐怖が居座ったままだった。そして、どこかで何かを見落としている気がした。あの言葉、「真実を見つけろ」というものが、彼の頭にこびりついて離れなかった。
その夜、彼はもう一度夢の中であの暗い部屋を訪れた。今回は、人物が目の前に立って、静かに彼を見つめていた。藤崎は恐れずに、その人物の目を見つめ返した。
「真実って、何を意味するんだ?」と藤崎は尋ねた。
すると、人物は微笑みを浮かべた。その微笑みは、今までの無表情とは対照的で、どこかほっとするようなものだった。そして一瞬の後、部屋全体が光に包まれ、藤崎の意識は夢の世界から現実へと引き戻された。
彼は目を覚まし、自分の周囲を見渡した。何も変わっていなかったが、彼の心には僅かな安堵が生まれていた。幻覚はまだ完全には消えていないけれど、それでも何かが変わった気がした。もしかしたら、現実と妄想の境目は曖昧なままかもしれないが、彼はその曖昧さに立ち向かう力を得たようだった。
そして、彼は決して自分の精神が完全に壊れることはないと、信じることができるようになった。幻覚と共に生きる覚悟を決めた彼は、少しずつではあるが、自分を取り戻すための日々を再び歩み始めたのだった。